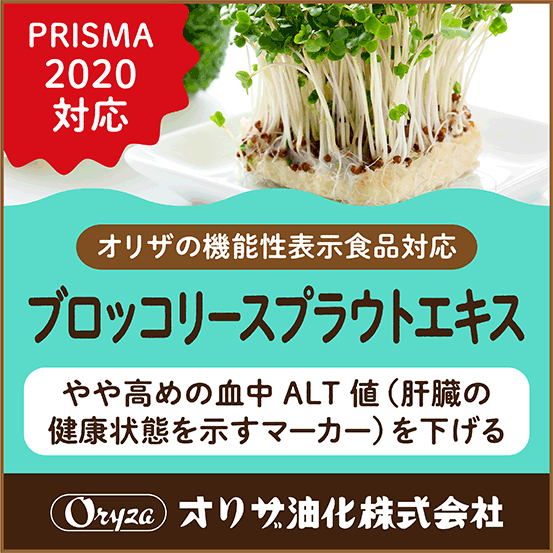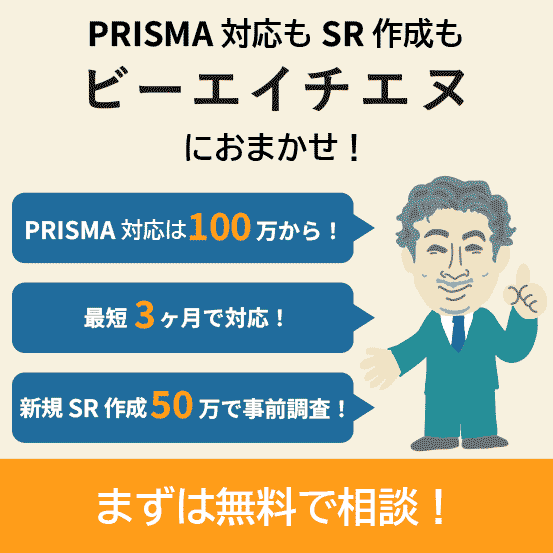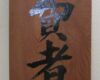健康食品「受託製造」市場の今 足元に横たわる課題と成長エンジン
健康食品・サプリメントの多くは、それらの販売会社ではなく、OEM・ODM(受託)メーカーが作っている場合が多い。販売会社と同様に、大手から中小規模まで多くの企業がひしめく市場だ。それを健康食品受託製造市場と呼び、健康食品の最終商品(消費者が購入する商品)市場と一心同体の関係をなしている。最終商品市場が課題を抱えれば、その影響は受託製造市場におよぶ。その逆も然り。受託製造市場は今、どのような課題を抱えているのだろうか。
成長見せるも業績まだら模様
国内健康食品受託製造市場の規模は小さくない。市場調査会社の調べによれば、2023年度の市場規模は約1,700億円。前年度比は2.0%の増加が予測されている(㈱矢野経済研究所調べ)。
前年の22年度は、コロナ禍で増加した通販需要(巣ごもり需要)の反動減などを受けて0.2%増と低成長。しかし23年度は、コロナ禍の影響を受けて最終商品市場で停滞していた「新商品開発の加速」や「インバウンドを含めた海外需要の拡大」など背景にした伸び率の拡大が見込まれるとする。
一方、この市場規模予測を、当の受託製造企業はどのように感じるだろうか。2.0%の伸びを自分事として実感できる先がある一方で、首を傾げる場合もあるに違いない。
受託製造企業の業績は、顧客の商品の売れ行きにも大きく左右される。売り上げが伸びている商品の受託製造件数が多ければ多いほど、その受託製造企業の業績は、商品の売り上げに応じて伸びていく。逆に、受託製造している商品の動きが悪ければ、業績は低下する。その意味で、市場を構成する受託製造企業の業績はまだら模様だ。
実際、9~10月にかけて受託製造企業に足もとの業績について聞き取りを行ったところ、「2割程度伸びている」とする声が聞かれた一方で、「良くはないが悪くもないといったところ」や「正直、落している」と語る先もあり、一様ではない。
業績伸ばすも消えぬ今後への不安
全体的な雰囲気としては、業績を伸ばしている受託製造企業が比較的多いとみられる。したがって、最終商品市場も堅調に推移していると思われる。だが、そんな推測に疑問符を付けるデータもある。総務省統計局による毎月の家計調査(2人以上世帯)だ。
サプリメントなど「健康保持用摂取品」の支出額推移を見ると、今年1~8月は合計で約8,900円と、前年(22年)同期と比べて増えてはいるものの、増加幅は約100円にとどまる。また、その前年21年同期との比較では約100円の減少であり、20年同期と比べると減少額はさらに大きくなってしまう。
22年同期比では増加傾向を示しているため、コロナ禍で生じた特需の反動減から回復し始めたのが今年だと見ることもできる。ただ、足元で業績を伸ばしている受託製造企業からも、今後の健康食品に対する消費や自社の業績などを不安視する声が上がる。
コスト高の影響「今後も続く」
不安材料のひとつは、昨年後半から顕著になった、原材料費や包装資材費をはじめエネルギーや物流などユーティリティコストの上昇だ。足もとで増収となっている受託製造企業でも、利益は減らしている場合が少なくない。増加したコストの取引価格への転嫁を浸透させられなかったためだ。
「相次ぐ値上げが多品目に及んだため、(顧客に対する)値上げ交渉を十分行えなかった。製造に入ってから値上げを言われることもあって、そうなるともうお手上げ。うちで吸収するしかない」。増収減益となった受託製造企業ではそう話す。
食品業界全体で稀に見るコスト高の要因の1つになった円安は現在も続いているうえ、国際情勢の不透明さはさらに濃度を増している。取引価格への転嫁を十分進められていない中で、今後も海外から輸入する原材料などを中心に価格が上昇していく可能性がありそうだ。「値上げ交渉は引き続き行っていかなければならない」。ある受託製造企業の営業責任者は気が重そうに語る。
売上利益や広告宣伝費を削減するなどして耐えてきた最終商品販売会社が価格改定に転じた時、健康食品を必需品ではなく嗜好品と受けとめている消費者をつなぎ留めることが果たしてできるだろうか。「国内需要は堅調」と見ている受託製造事業者も、「今はいい。しかしこの先が読めない」と話す。
(続きは会員専用ページへ)
不安材料に物流問題や人手不足も
そうした先の読めない不安は他にもある。通販事業者を中心とする最終商品販売会社に対する価格上昇圧力となる物流の「2024年問題」だ。それに対する不安の声は、受託製造企業からも聞かれる。物流コストのさらなる上昇だけでなく、納期に及ぼす影響が懸念されるためだ。
ある受託製造企業の役員は、「これまでどおりの納期に対応できなくなったり、決められた納期を守れなかったりする可能性がある。お客様に迷惑をかけることになる」と語り、ドライバー不足にともなう物流の停滞によって生じる可能性がある納期の遅れを強く恐れる。納期遅れが恒常的に生じれば、顧客だけでなく、通信販売商品の定期購入顧客を中心に消費者にも影響を与えることになる。しかし課題解消に向けた妙案は、「今のところ、ない」
仮に、2024年問題下においても納期を遵守できる策を講じられたとしても、課題は残る。製造現場の人手不足だ。地域によっては、「以前よりも月給を上げて募集をかけているのに全然集まらない」(西日本の受託製造企業幹部)。
少子高齢化を受けた生産年齢人口の減少という、日本社会全体が抱える構造上の問題に健康食品受託製造市場も直面している。製造や検査の工程の一部機械化など、省人化の取り組みが以前から進んではいるが、多品種少量生産が一般的な健康食品の場合、自動化やロボット化がそぐわない面もある。その中で不足する人手にどう対応していくか。業績を大きく伸ばしている中堅の受託製造企業では、「今でもかなり多いが、外注を増やしていくしかない」と話す。
成長材料に高まる海外向け需要
「今後の健康食品市場は国内市場の大幅な成長が見込みにくい」。前述の調査会社はそう指摘する。確かに、健康食品の主要な消費層である高齢者人口の増加がこの先20年ほど続くのだとしても、現時点で健康食品を利用している割合が一定規模以上に達している中では、大幅な需要増は見込みづらい。
もっとも、健康寿命を延ばすためのセルフケアやセルフメディケーションの意識の社会的な浸透と、若年層~中高年層の健康食品未利用消費者からの需要の掘り起こしに成功すれば、国内市場の大幅な成長につながる可能性もある。だが、実現させるには国の健康・医療政策とも連動した普及啓発が不可欠と考えられるだけに、一筋縄にはいかない。
最終商品市場がそうである以上、受託製造市場も「大幅な成長が見込みにくい」ということになる。
ただ、それは消費市場を国内に限定した場合の話だ。日本の外に目を向けると、最終商品市場、受託製造市場ともに見える景色が変わってくる。
前述の市場調査実施者も、海外からの需要の伸びに着目。「インバウンドを含めた海外需要の拡大が期待され、健康食品受託製造企業は海外向け受注の獲得増加により、売上増につながる」としている。
受託製造企業の海外向け受注はすでに増加傾向を見せている。最終商品販売会社が越境ECから貿易まで海外輸出を加速させているためだ。財務省の貿易統計によると、栄養補助食品(健康食品)の国内から海外への輸出額は22年1~12月累計で331億円。菓子類の280億円を上回り、前年比は44%と大幅な増加を示した。国別輸出金額を見ると、トップは中国で168億円。次いで台湾が約57億円、香港が48億円、そして美容飲料の輸出額が大きく増加しているとされるベトナムが28億円で続く。
処理水放出でブレーキも「一時的では」
しかし23年の輸出額は、東京電力福島第一原発の処理水放出後に急ブレーキがかかってしまった。8月単月の中国への輸出額は10.6億円となり、前年同月比でほぼ半減。台湾、香港も減少した。ベトナムなど東南アジア諸国連合(ASEAN)9カ国への輸出額も減少しており、1~9月の累計輸出額は27億円と、前年同期に対して約1割のマイナスとなっている。
処理水放出が、日本国産健康食品の輸出機運の高まりに冷や水を浴びせた格好だ。
だが、受託製造市場からは、「外交カードに利用しようとしている様子の中国は長期化する可能性もあるが、他は一時的なものではないか」との見方も上がる。実際、前年同月実績には及ばないもの、ASEANへの9月の輸出額は前月比で26%増加。中国も9月は前月比で約16%増加した。
受託製造企業の中には、海外法人を設立し、現地での顧客獲得に本腰を入れる動きもみられるようになっている。国内企業からの海外向け受注の拡大に加えて、海外に拠点を置いて新規顧客の掘り起こしを図る。最終商品から受託製造まで、日本の健康食品産業は、海外でも本格的に稼ぐ時代に入った。
6・30措置命令、届出サポートに影響
健康食品の最終商品市場はここ数年、ヘルスクレーム(機能性表示)を行えない一般健康食品から、それが行える機能性表示食品へのシフトが加速度的に進んでいる。
この動きを側面で支えているのが受託製造市場だ。多くの受託製造企業が顧客に対する機能性表示食品の「届出サポート」に取り組んでいる。そのため、ヘルスクレームの科学的根拠の中身にまで踏み込みながら優良誤認の景品表示法違反を認定された「6・30措置命令」は受託製造市場にも衝撃を与えた。
「(原材料事業者などから提供された)SRの中身をちゃんと確認しないといけない。右から左ではいられなくなった」。ある中堅受託製造企業の研究開発担当者は今後の対応についてそう話す。一方、SRの信頼性に対する責任の所在に悩む事業者もいる。「届出内容に対する責任を負うのは届出者であることは分かっている。でもそれはあくまでも制度上の話ではないか。SR込みの素材(機能性関与成分)選定を当社で行っているような場合、ビジネス上の道義的責任が無いとは言えないように思う。だからといって(外部から提供されたSRに対する)責任までは負うというのもどうか」
他方、最終商品市場全体を見渡すと、一般健康食品が機能性表示食品のシェアを大きく上回っているように見える。消費者庁が運用する機能性表示食品の届出データベースによると、サプリメントから生鮮食品まで、現在販売中の品目数は約3,200超(11月5日時点)。国内で現在流通している健康食品の正確な品目数は不明だが、感覚的には、一般健康食品は機能性表示食品の数倍の数に上りそうだ。「委託されれば製造するが積極的に取り組んでいるわけではない」。業績を大きく伸ばしている受託製造企業の中にも、機能性表示食品についてそう語る向きがある
改めて考える必要、製造品質管理レベル
ただ、そのように機能性表示食品制度への対応に積極的ではない受託製造企業も無視できない新たな動きがここにきて立ち上がっている。錠剤やカプセル剤などの健康食品の安全性確保(製造・品質管理)に関する考え方を示した平成17年通知の改正だ。
同通知を所管する厚生労働省の新開発食品保健対策室(食品基準審査課)は、今年度内の改正を目指したい考えを述べている。厚労省が現在所管している食品衛生基準行政が消費者庁に移管される前に決着させ、同庁に譲り渡すということだ。
この改正では、適正製造規範(GMP)に基づく製造を義務付けている指定成分等含有食品の製造・加工基準告示や留意事項の内容に寄せた改正が行われる。それが改正の主要なねらい。
対象は、機能性表示食品などの保健機能から一般健康食品までをひっくるめた「錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の形状である加工食品」(改正案より抜粋)。これまでと同様に、あくまでも「自主的な取り組み」を求められるものではあるが、受託製造企業に要求されるGMPのレベルが高まることになる。
【石川太郎】
関連記事
:唐木東大名誉教授が受託2社に問う 【座談会】受託製造から見た機能性表示食品の今
:22年のサプリ輸出額、331億円超に 日本から海外、前年比44%増と大幅な伸び示す
:中日本カプ、ベトナムに子会社設立 現地密着で日本企業の市場進出サポートも