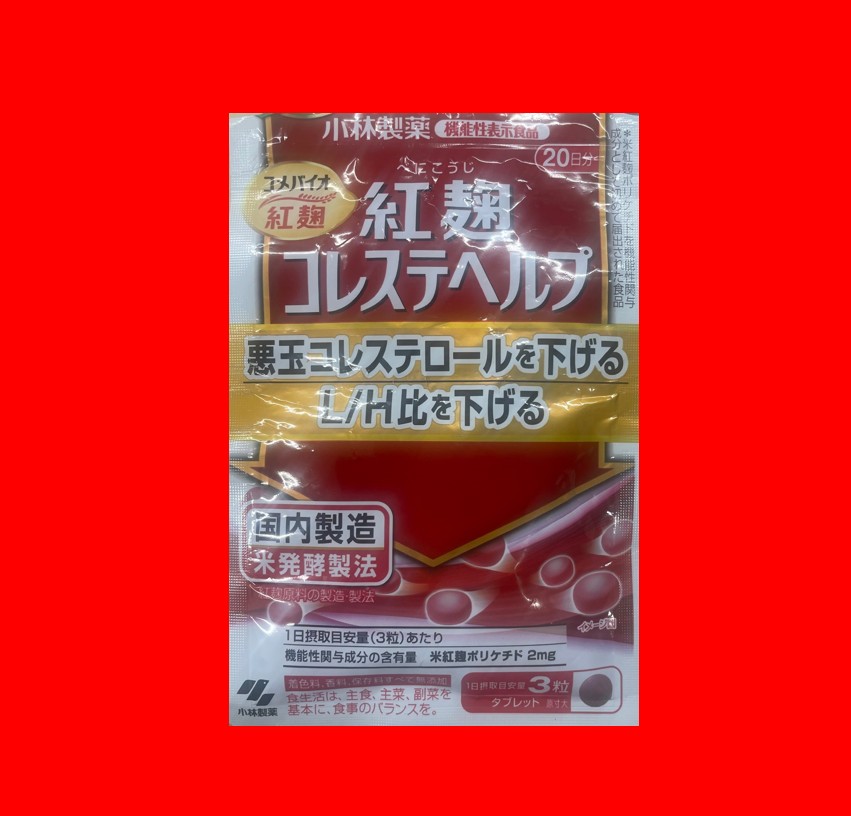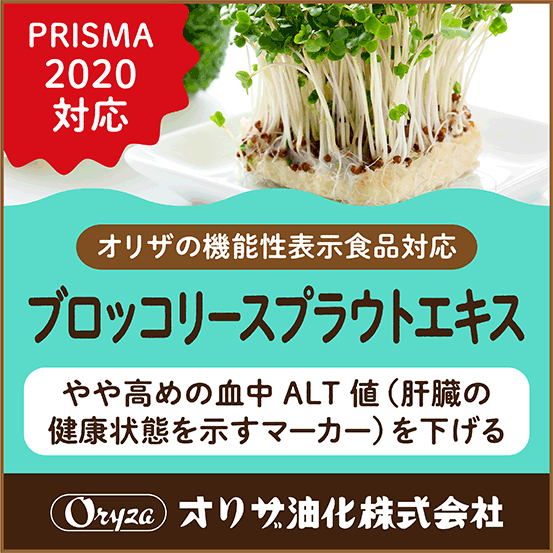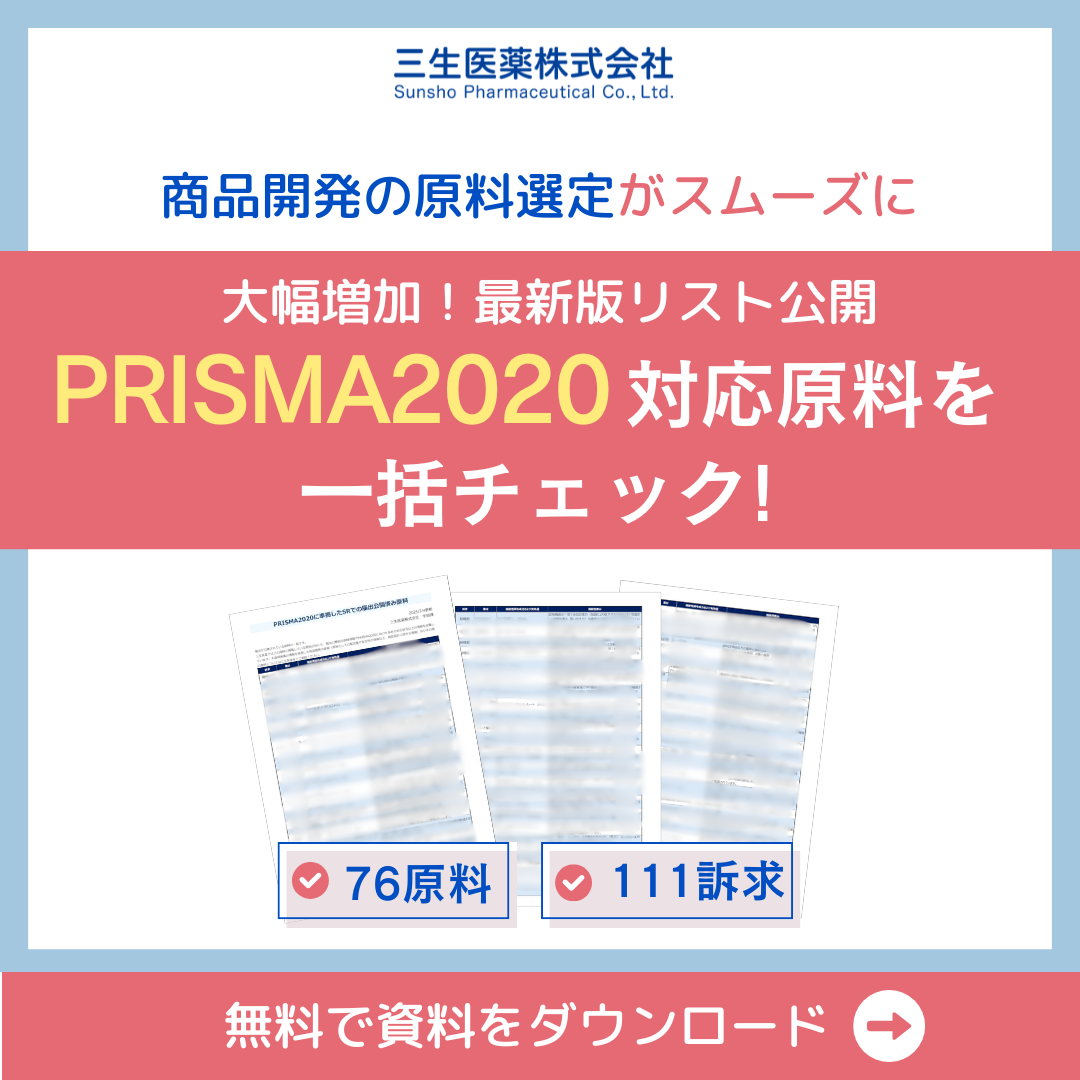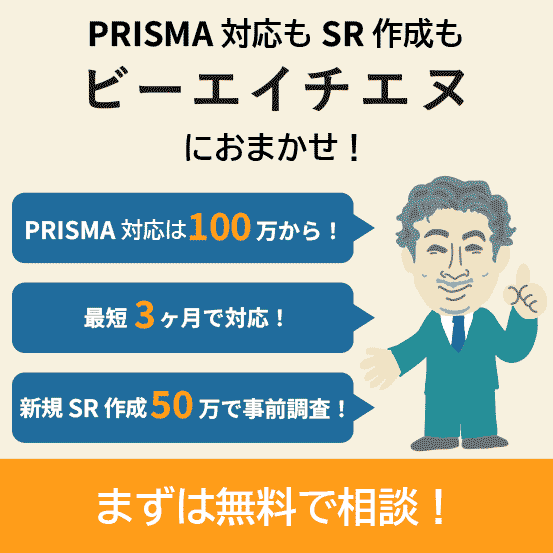紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4) 科学的根拠の乏しさと過信の構造
国立医薬品食品衛生研究所(国立衛生研)が行った動物実験では、PA単独投与でラットに腎障害が発生した。一方、同時に試験された未知の化合物YおよびZについては腎毒性が確認されなかった。この結果を受け、厚労省は「PAが主因」と判断し、行政措置を講じるに至った。
だが、毒性学の専門家である佐藤均教授(静岡県立大学)は、この判断に対して複数の懸念を呈している。最大の論点は、7日間という試験期間の短さである。佐藤教授は、「急性の評価に過ぎず、慢性的な毒性、あるいは複合影響を把握するには不十分」と指摘しており、複数の成分を同時に摂取するサプリメントの実態とは乖離しているとの見解を示す。佐藤教授による試験データに対する評価の概要は以下のとおり。
紅麹サプリメントとプベルル酸毒性試験(佐藤教授の「意見書」より)
この試験では、ラットにPAを7日間連続投与したところ、雌で1例のみ重度の腎障害(グレード5)が認められたが、大多数は軽度から中等度にとどまり、雄では明らかな腎障害や死亡例は報告されなかった。したがって、極めて短期間の毒性試験のみでは、実際の人間で報告されているような重篤な腎障害や死亡例を説明するには不十分。
評価上の限界も多く、まずPAの含有量やヒトの血中濃度が不明である点、さらにヒトからPAが実際に検出された例もない。紅麹菌には腎毒性を持つとされる「シトリニン」を生成する遺伝子はないとされているが、遺伝的変異によって例外が生じている可能性も否定はできず、より踏み込んだ解析が求められる。
注目すべきは、PA単独ではなく、複数の要因が組み合わさった「複合リスク」の存在である。第一に、PAとモナコリンK(ロバスタチンと同一成分)の相互作用がある。PAは肝臓のOATP1B1トランスポーターを阻害することが知られており、その結果、モナコリンKの血中濃度が上昇し、横紋筋融解症などのリスクが増加する可能性がある。
さらに、モナコリンKの代謝に関与するSLCO1B1遺伝子に特定の変異(rs4149056 CC型)を持つ人々は、薬剤に対して副作用が出やすいことが知られている。このような遺伝的要因を踏まえると、すべての摂取者に被害が出ていない事実とも整合的である。
佐藤教授の見解としては、PA単独による毒性では説明がつかず、PAとモナコリンKの薬理相互作用、さらには個人の遺伝的背景が重層的に関与して、今回のような重篤な健康被害が発生したとする考えが最も合理的であると結論づけている。
「行政目的」と「科学的審理の探求」は別か?
こうした疑義が残る中、厚労省の担当官AおよびBとのやり取りについては連載の第2回で報告した。7日間の反復投与試験結果をもって原因特定を「行政的に」完了とする姿勢を示しており、科学的検証の継続に対して消極的な立場であることを意味する。
一方で、B氏は「今後、将来的に調査が必要となる可能性がある」との含みを持たせた発言を行っている。これは、現時点では追加試験を否定するものの、将来に向けて科学的・社会的要請が高まれば再検討の余地を残しているという、行政の“二段構え”とも取れる対応である。「行政目的」と「科学的真理の探求」とを分けて考えていることを意味している。
要するに、厚労省の判断は「行政的収束」に重きを置いたものであり、「科学的解明」とは一定の距離がある。このような姿勢は、国民の健康と安全を預かる立場にある行政機関として、いかに妥当性を持ち得るのか――。佐藤教授をはじめ、複数の専門家が疑問を投げかけている。
8月18日付「FOOCOM」のメールマガジンに、薬学者の畝山智香子氏がプベルル酸に関する論考を寄稿した。畝山氏によると、28日間の予備的な毒性試験がすでに行われており、その結果は学術論文および厚生労働科学研究成果データベースで確認できるというのである。タイトルは「CD(SD)ラットにおけるプベルル酸の28日間亜急性毒性試験」。Received(受理日)は2025年6月11日、Accepted(受理承認日):同7月19日、学術誌へのオンライン公開日は同8月6日となっている。
畝山氏はそこで、毒性が腎臓以外の「胃」にも及んでいる点や性差(オスとメスの感受性の違い)がある可能性に注目している。これらは動物試験でなければ分からない重要な知見だとし、大阪市の疫学解析で健康被害を訴えた人の70%が女性であることも、性差の可能性を示唆しているとの見解を述べている。このことは、王子神谷内科外科クリニックの伊藤院長が診断した「脱毛」や「虫垂炎」の患者の存在を裏付ける有力な証左にもつながるのではないか。
今思うと、8月5日に開かれた小林製薬の記者会見で、某メディア所属の記者が腎障害以外に関する症例について質問をしたのは、この事実を事前に把握していたからだろうか。もちろん、小林製薬は「患者の機微に触れる情報」だとして腎障害以外の症例を明らかにしていない。
その後筆者が確認したところ、小林製薬はこの試験結果を事前に把握していたようである。同社に改めて取材し、症状やその原因について聞いたところ、会見時と同じ答えが返ってきた。いずれにせよ、記者会見場で質問した記者は、「腎障害以外の症例」の存在について、何かの理由で聞き及んでいたに違いない。
静岡県立大学の佐藤教授は、「腎障害以外に何の障害があったのかを言うと、プベルル酸だけのせいにするのが難しくなるのではないか」と意味深な指摘を行っている。
小林製薬が把握している「腎障害以外の患者」に脱毛や虫垂炎の患者が含まれているかどうかを同社に確認したところ、「個別の症例の詳細については回答を差し控える」とした。
次回は、モナコリンKという“医薬品成分”がなぜサプリメントに含まれていたのか、その制度的問題について掘り下げていく。
※佐藤教授の「意見書」全文はこちら(⇒会員専用記事閲覧ページへ)
【健康被害を生じた紅麹サプリメントに関する意見書】
静岡県立大学薬学研究科・客員教授
タイ国立マヒドン大学薬学部・客員教授
佐藤 均
これまでの研究に基づいて、小林製薬製造による紅麹含有製品のうち健康被害を生じたロットから検出されたプベルル酸(PA)が腎障害の原因物質であるとの結論が導き出された。これまでの調査や研究によって明らかになったことをまとめると、「PAを含む紅麹サプリメントによって腎障害が発生した。」ことに加え、「動物にPA (1〜10mg/kg)を投与した結果、腎障害が生じた。」ということである。これまでの研究結果に関して、薬学の専門家としての私の見解を述べる。
◾️ラットを用いた短期反復投与試験に関する見解
まず、短期間(7日間)のラット反復投与試験に関してであるが、PAによる腎傷害は限定的かつ軽微または軽度(グレード1または2)であり、死亡に至った個体は1例もなかった。血液化学検査、病理学検査の結果は、雌において高度な組織変性(グレード5)が1例だけ生じたものの、総じて腎傷害は軽微または軽度であった。雄においては、腎傷害を示す所見は血液化学検査、病理学検査ともにほとんど得られておらず、傷害が見られた項目においても、その程度は軽微なものであった。2〜3ヶ月程度の投与試験も行われておらず、7日間のラット反復投与試験結果をもってこの度の重篤な(死亡を含む)健康被害の発生を説明することは必ずしも妥当ではないと思われる。
その他、上記試験が行われた後に、PAによる腎毒性の可能性について数件の細胞実験や動物実験が行われ、それらの結果が論文として公表されている。すべては国内研究機関によるものである。これらの結果も含め、全般的な私の見解を以下に述べる。
◾️これまでの研究データに関する全般的な見解
(1) 当該製品中に検出されたPA濃度(mg/kg検体)及び被害者が摂取したPA量(mg/kg体重)が知られていないため、研究に用いられたPA濃度やPA投与量が妥当か否かの判断ができない。つまり、実験条件と実際の摂取条件の間に定量的整合性が取れない。
(2) 健康被害を受けた人間の体内(血液あるいは腎組織)にPAが検出されたという証拠がなく、ましてや体内でのPA濃度が不明なため、研究で用いられたPA濃度が過剰濃度であったために腎障害が起こされた可能性が否定できない。
(3) 小林製薬によると、用いた紅麹菌にはシトリニン産生遺伝子がないということであるが、遺伝子復元変異のリスクもある事から、実際にシトリニンが検出されていないという検証データがロット毎に必要と考える。現時点では遺伝子復元変異のリスクに関しては未知であるため、言及を避ける。
(4) 上記の理由により、混入したPAには高濃度で腎障害を起こす性質があるものの、今回のように死亡を含む重篤な腎障害がPAのみで説明するのは無理があると考える。他の可能性として、PA単独ではなく、モナコリンKとPAが同時に存在したために重篤な腎障害が発生した可能性がある。この可能性について、以下に詳しく述べる。
◾️新たな仮説〜PAとモナコリンKの共存によって腎障害が発生した可能性〜
PAはアニオン薬物輸送トランスポーター(OATP1B1)を強力に阻害することが知られている。OATP1B1は肝臓に存在する輸送タンパク質で、モナコリンKのようなスタチン系薬物を肝臓に取り込む役割を担っている。そのため、OATP1B1が阻害されるとモナコリンKが肝臓に取り込まれにくくなり、その血中濃度上昇をもたらす。この血中濃度上昇が、通常なら稀にしか起きない横紋筋融解症のリスク増加につながるのである。
そもそも、紅麹はモナコリンK(医薬品であるロバスタチンと同一物質)を含むことから、海外ではその食品としての使用が禁止されていることが多い。紅麹単独では健康被害が見られないからといって、どんな場合でも健康被害が起きないとは言えないのである。実際、スタチン系薬物であるセリバスタチンは単独使用では安全であったが、OATP1B1阻害薬ゲムフィブロジルとの併用により横紋筋融解症の頻度が高まり多数の患者が死亡した事から、2001 年、世界的にセリバスタチンの販売が中止された。今回も同様に、モナコリンK含有食品に微量のプベルル酸が混入することによって、モナコリンKの肝臓への取り込みが阻害され、本来なら稀にしか起きない腎障害発症とその重篤化がもたらされた可能性がある。横紋筋融解症によって血中に漏出したミオグロビンは、尿細管を詰まらせたり直接的に尿細管障害を起こしたりすることで、急性腎不全を起こす事が知られている。
この度の健康被害事例において血清CK値の上昇が見られない事から、モナコリンKによる薬剤性腎障害(横紋筋融解症を伴う)ではないと考える向きもあるが、原則として筋肉の損傷から時間が経過するとCK値は低下するため、今回のように時間経過とともに腎障害が重篤化してから初めて問題が認識されたケースでは、CK値が低いからといって薬剤性腎障害ではないと断定することには無理がある。実際、この度の腎障害発生事例においては、横紋筋融解症の特徴である尿の泡立ちや褐色尿が報告されている。
ところで、上記トランスポーター(OATP1B1)をコーディングする遺伝子(SLCO1B1)に機能的変異があるヒトではスタチン系薬剤の体内処理速度が遅く、薬剤性副作用であるミオパチーの発現頻度がそうでないヒトに対して数倍も高いことが知られている。この度の健康被害事案においても、PAが混入した紅麹製品を摂取した消費者が全員健康被害を受けたわけではない事から、特定の遺伝子多型(rs4149056 CC型)を有する消費者において腎障害が増幅してしまった可能性がある。
結論として私は、PA自体による若干の腎障害リスクに加えて、PAとモナコリンKの相互作用によるリスク、特定の遺伝子多型によるリスク、の3つが複合して今回の不幸な健康被害が生じたのではないかと考える。
※私の研究室では、HMG-CoA還元酵素阻害薬(モナコリンKを含み)とOATP1B1阻害薬(プベルル酸を含む)との併用で前者の副作用が著しく増強されることを過去に報告している。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15194707/
【概要】紅麹サプリによる健康被害とプベルル酸の毒性試験の評価
●背景
小林製薬製造の紅麹サプリメントの一部ロットから、腎障害を引き起こす可能性のある「プベルル酸(PA)」が検出された。
PAの毒性について、厚生労働省の依頼でラットによる「7日間反復投与試験」が実施された。
● 試験結果のポイント
雌ラットでは1例だけ強い腎障害(グレード5)があったが、全体としては軽度〜中等度の腎障害にとどまった。
雄ラットには目立った腎障害は見られず、死亡例はゼロ。
たった7日間の試験では、実際の人間の重篤な健康被害(死亡を含む)を説明できないというのが専門家の見解。
● 評価上の限界
サプリメント中のPA量や、摂取者が体内にどれほど取り込んだか(血中濃度など)は不明。
人間の体内からPAが検出された証拠はなし。
紅麹菌には「シトリニン」を作る遺伝子がないとされるが、遺伝子変異の可能性も否定できないため、より詳細な検証が必要。
●複合リスクの仮説:PA単独ではなく、複数要因の可能性
①PAとモナコリンKの相互作用
モナコリンK(紅麹の有効成分、医薬品ロバスタチンと同一)は、肝臓で代謝される。
PAは肝臓への取り込みを妨げるトランスポーター(OATP1B1)を阻害する。
結果としてモナコリンKの血中濃度が上がり、まれな副作用(横紋筋融解症など)のリスク増加が起こる可能性。
②遺伝的要因
モナコリンKの代謝に関与する遺伝子(SLCO1B1)に特定の変異(rs4149056 CC型)がある人は、副作用が出やすい。
全員に健康被害が出ていないことから、このような遺伝的要素も一因と考えられる。
●結論(専門家の見解)
PA単独による腎障害では説明しきれない。PAとモナコリンKの相互作用、さらに個人の遺伝的体質が重なって、今回のような重篤な被害が起きたと考えるのが妥当である。」
<佐藤 均氏のプロフィール>
東京大学薬学部卒業後、金沢大学薬学部、米国国立衛生研究所(NIH)、国立がん研究所、スイス・バーゼル研究所・客員研究員、東京大学医学部助教授での研究活動を経て、25年間昭和大学に在籍した。最終講義では「薬学の使命とは何か」を問い、基礎と臨床をつなぐ研究の意義を強調したという。「自己満足に終わる研究ではなく、医療や社会に資する研究を行うことが薬学の本質」をモットーに、薬物動態学を中心に、臨床試験やゲノム解析を含む幅広い研究を手掛けている。
(つづく)
【田代 宏】
関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)
:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)
:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)
:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)
:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)