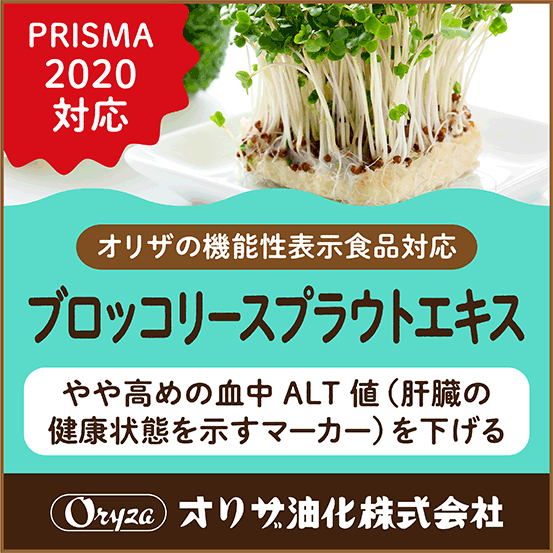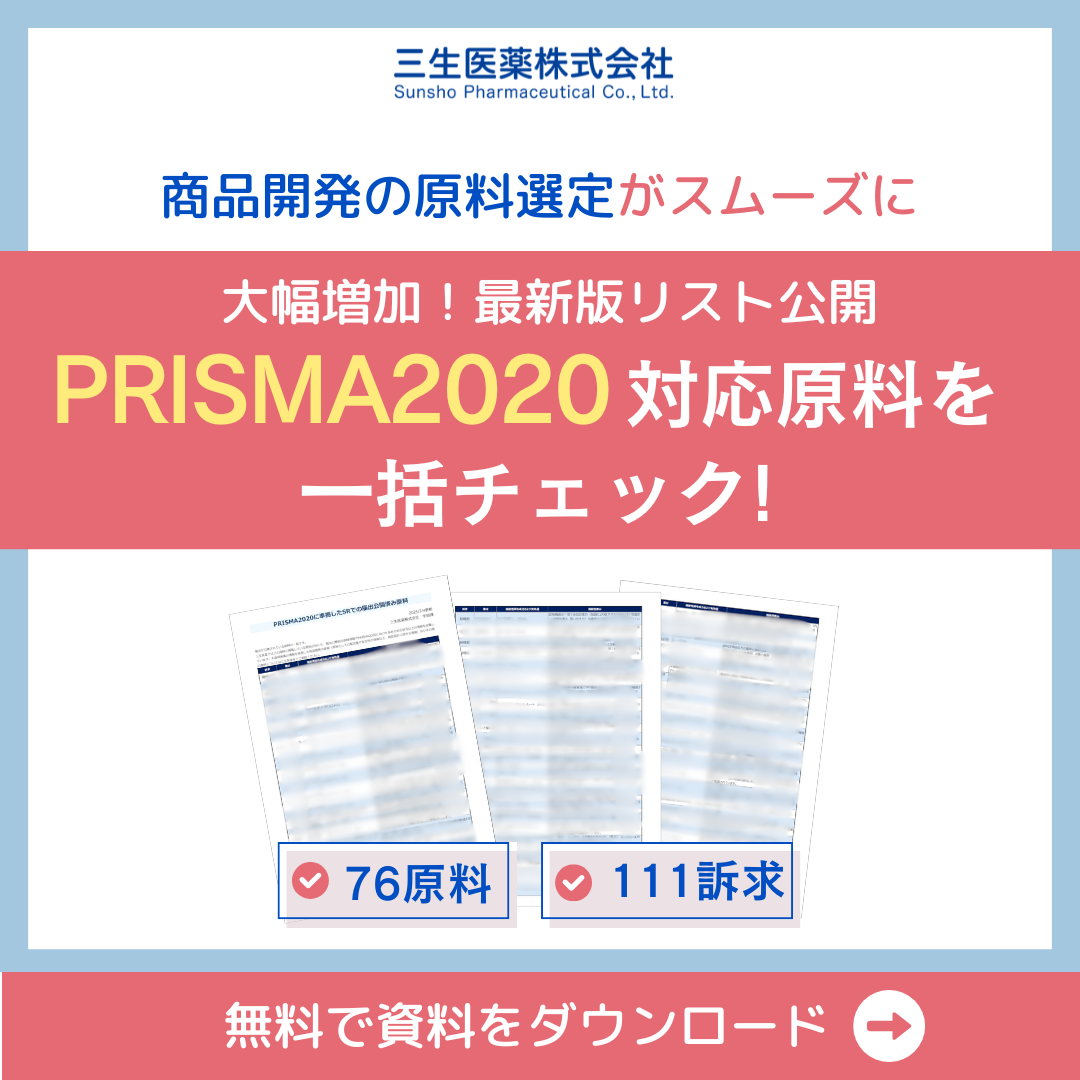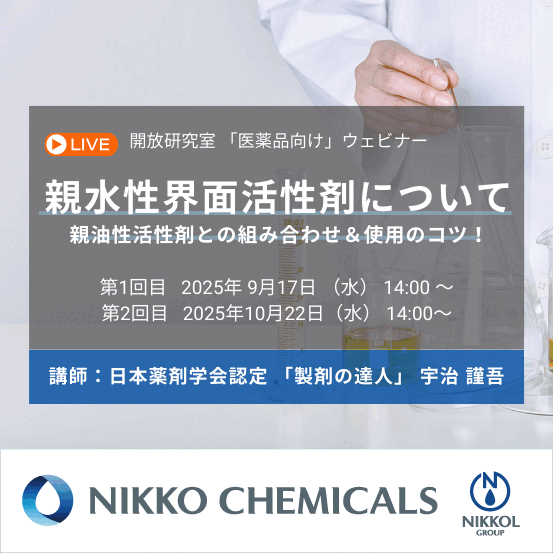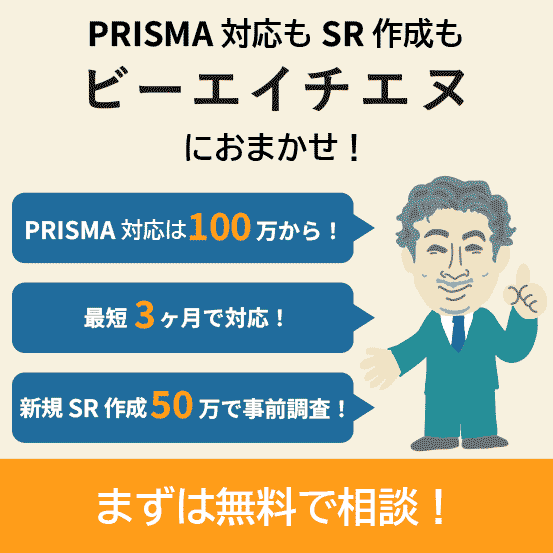インバウンドが市場を下支え ビューティーサプリ&コスメ市場を調査、ジェンダーレスが新たな市場に
物価高・円安の影響で消費の二極化が進むと言われるなか、化粧品は特に節約の対象になりやすく、消費者が化粧品を選ぶ基準はますます厳しくなることが予想される。一方で、コロナ禍を経て消費者の健康への意識は向上した。それを好機と捉え、美と健康を結び付けたブランド展開や、商品ラインアップの拡充も進む。美容をイメージさせる効果を訴求した機能性表示食品も次々と誕生している。ビューティサプリ&コスメ市場の動向をレポートする。
インバウンド需要が復活、幅広い商品が購入の対象に
コロナ以前、東京オリンピック開催決定もあり多くの外国人が日本を訪れていた。特に中国からの来日は多く、彼らによる「爆買い」に日本の化粧品や美容サプリメントは大きく恩恵を受けた。通販市場の拡大による販売チャネルの多角化などで、百貨店の売上が2008年の7兆3,818億円をピークに減少するなか、化粧品は11年の3,230億1,600万円を底に上昇を続けていた。百貨店や量販店には、商品を案内する中国語で書かれたポップを設置、中国語の分かる案内スタッフを配置するなど、中国からの観光客を取り込もうとさまざまな施策がとられていた。
コロナ禍で来日外国人が激減すると、その販売チャネルは越境ECにシフト。Made in Japanブランドの高い品質への信頼感から、通販事業者を中心にその販売量は増加した。ある中堅の美容サプリ・化粧品OEM事業者によると、「コロナ禍で売上が落ちるどころか、逆に伸びた。そのほとんどが中国向けの越境ECによるものだった」と当時を振り返る。中国市場でのマーティングを支援するある企画会社は当時の状況について、「新規参入も多かったが、百貨店や量販店を主な販売チャネルにしていた大手ブランドメーカーからも多数問い合わせがあった」と話す。
コロナが落ち着き訪日外国人が増加、少しずつインバウンド需要が復活した。中国からの入国が遅れたことでコロナ以前の盛り上がりには届かないまでも、多くの外国人観光客によるMade in Japanブランドの化粧品・美容サプリメントの購入が復活した。ある販売会社は、「コロナ前は限られた免税店やドラッグストアでの売上が伸びたが、昨年は、まんべんなく観光客が訪れていたという印象。また、有名ブランドの高価格帯だけなく、名があまり知られていない比較的リーズナブルな商品も広く購入されていたという印象。高級品や有名ブランドへのニーズは揺るがないものの、世界的に認知度の高い人気アニメキャラクターとのコラボ商品や、見た目がかわいいものなど、日本ならではの商品が求められる傾向にある」と話していた。
(⇒つづきは会員ページへ)
展示会も復活、韓国勢の勢いにも警戒
1月17日から19日の3日間、東京ビッグサイト(東京都江東区)で「第14回COSME Week東京」が開催された。本展は、「第14回化粧品開発展東京」、「第12回国際化粧品展東京」、「第7回美容・健康食品EXPO」、「第4回国際エステ・美容医療EXPO」、「第3回化粧品・マーケティングEXPO」、「第2回ヘアケアEXPO」の6つの専門展で構成。事務局の発表によると、化粧品・美容サプリメントの原料メーカーや商社、受託製造、販売会社など約750社が出展、3日間合計で3万3,970人が来場したという。
コロナ禍で人々の生活スタイルが一変し、外出機会の減少によるファンデーションなどのメイクアップ品の売上、マスク着用による口紅の売上は軒並み落ち込んだ。一方、スキンケア、ボディケア、アイメイクなどの売上が伸び、さらには、白髪や育毛といった髪の毛に関する商品ニーズが、特に中高年層を中心に売上を伸ばした。コロナ禍以前の生活スタイルが戻り、展示会において、メイクアップ品の提案も一部復活したが、やはり、引き続きスキンケアやボディケアに関連した提案が多く見られた。
提案内容以上に目立ったのが海外企業による出展と来場。通常開催となった今回、中国や韓国を中心とした海外企業による出展が復活。市場がコロナ以前の盛り上がりを取り戻しつつあることを歓迎する一方で、ここ最近の韓国ブランドの勢いに危機感を抱く声も多く聞かれた。かつての韓国ブームでは、韓流ドラマや韓国アイドルの人気も重なり、安い現地ブランドやトレンドを先取りした韓国コスメを買い求めて、多くの日本人が韓国を訪れ、日本国内にも多くの韓国コスメを取り扱う店が出店した。ブームの落ち着きとコロナ禍でその勢いは収まっていたようだが、再び、韓国アイドルの人気とともに韓国コスメの勢いが増している。ある日本の化粧品メーカーの営業担当者は、「数年前の人気は、円高・ウォン安で現地の有名ブランドが比較的安く手に入るという背景もあったが、今は、値段よりも商品の機能性や見た目といった商品力で、日本のものよりも韓国のものを好むという消費者も増えているようだ」と話す。アイドル人気と相まって勢いが復活した韓国コスメの動向や戦略にも注視する必要がありそうだ。
中国依存のリスクを再認識、新たな中国市場戦略を
「2023年は越境ECが全く振るわなかった」とある販売会社は嘆く。インバウンド需要が増加し、少しずつ減少していた越境EC、なかでもコロナ禍の売上を支えた中国向けの越境ECによる販売が大きく落ち込んだ。9月の原発処理水排出で、これまで厚い信頼を得ていたMade in Japanブランドが拒否。個人的に日本国内で購入する中国人はいるものの、日本産を前面に出した販売は軒並みストップしたという。大手ブランドメーカーの中国国内での不買行動も報道されていた。「ブランドの信頼がなくなったのではなく、あくまでも政治的な問題。時間の問題で必ず復活する」。こう話すのは、ある通販支援会社。とは言え、巨大で魅力的なマーケットである反面、こうした地政学リスクが常にあるということを再認識させられた。
健康食品・化粧品の通販会社を顧客に持つあるOEM受託製造事業者は半年前、「コロナ以降、好業績の通販会社から2回先の受注を含めて次の受注を受けている。特に中国向けが好調のようで、受ける側としてもキャパオーバーを起こさないようコントロールに気を遣う」と話していたが、改めて話を聞くと、「処理水の問題以降、中国向けがストップ。一度、製造サイクルを見直した」と話していた。別のOEM事業者も、「中国向け越境ECの恩恵を受けコロナ禍を乗り切ったが、中国依存がここにきてリスクになってしまった」と話していた。
しかし、中国のリスクはそれだけではない。「処理水の影響は軽微で、これが原因だとされる消費の落ち込みは、これ以上拡大することはないと思われる」と話すのは、中国を中心に世界市場での成長を支えるプラットフォームサービスを提供する㈱NOVARCA(東京都千代田区)の浜野智成社長。同氏は、「処理水以上に深刻なのが中国経済の失速」と指摘。不動産価格の下落など、中国経済の落ち込みは一時的なものとは言えない状況だが、中国が巨大で魅力的なマーケットであることは間違いない。「インバウンドこそ、日本の化粧品ブランドが生き残るカギ」という声も聞かれた。これまで通りの戦略から脱却した中国市場戦略が求められる。
世界的なテーマはSDGs、ジェンダーレスも主流に
美容サプリ・化粧品マーケットにおいて切り離せないのが、持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)。EUを中心にその取り組みは広がり、SDGsはすでに1つのブランドコンセプトになっている。それは開発から製造、販売まで全てのサプライチェーンの共通言語で、それを取引条件の1つとする動きも見られる。
㈱ミリオナ化粧品(大阪市北区、阪本雅哉社長)は14日、北海道美唄市に新工場を稼働させる。同工場は、豪雪地帯である同地域の雪解け水から化粧品用の水を製造する工場。同市が進める「空知団地の雪解け水を活用した新規事業」の取り組みによって実現した。夏場の冷房に雪の冷気を使用する、同じく同団地に建設される予定のサーバー管理会社と連携し、サーバー熱を冬の暖房として活用するといった計画もある。また現在、今秋の稼働を目指し、同敷地内にこの雪解け水を使用した化粧品製造工場の建設を行っている。同市と連携し、『北海道空知地域の雪解け水(仮称)』として水をブランド化し、化粧品のイメージ戦略として活用する計画。
医薬品・化粧品原料の製造・販売を行う日光ケミカルズ㈱(東京都中央区、中原秀之社長)では、事業活動を通じ9つの重要課題(目標3.4.5.8.9.12.13.16.17)への取り組みを推進している。環境マネジメントとして、太陽光発電システムやDO計(溶存酸素計)などを設置し省エネルギー化を進める。その他、重油から液化天然ガスへの転換にも着手。液化天然ガスを使用したボイラを導入し、温室効果ガスを約25%削減した。また、ニッコールグループとして、21年から男性従業員の育児休業を推進するプロジェクトを進めており、啓蒙活動やパンフレットなどの情報発信を通じて、育休を取得しやすい環境を整備した。
SDGsの目標5にもあるジェンダー平等も、次の主要マーケットになるという声もある。これまで「化粧品=女性」とされていた市場から、「化粧品=男性も」として男性化粧品の市場が拡大。「現在、多様性・公平性・包括性が重視される世界では、ジェンダーレスコスメが注目を集めている」。こう話すのは、英国、ロンドンに本社を置く市場調査会社「Mintel Group」の日本法人㈱Mintel Japanで美容化粧品分野の分析を行うアナリストの河端香織氏。世界のジェンダーレスコスメには伸びしろがあり、今後もジェンダーレスを掲げるアイテムが増えることが予想される。ジェンダーギャップで後れを取る日本にとって、独自路線だとしても、新たな市場として確立される可能性は潜んでいる。
【藤田 勇一】