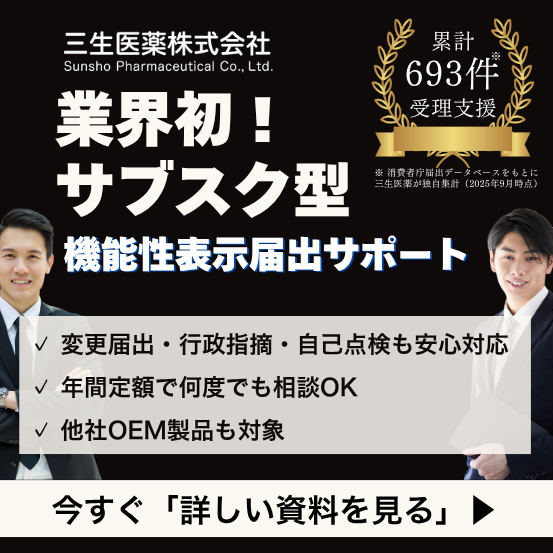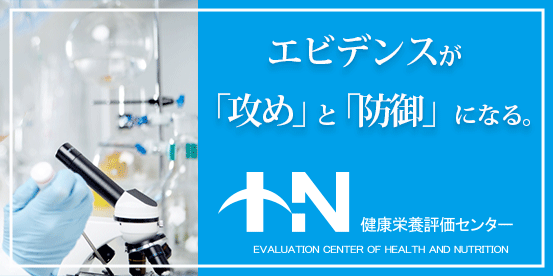永井克也大阪大名誉教授に聞く(3) ヒスタミンと自律神経、たんぱく質の構造解析
体内時計のメカニズムを解明
永井 第2回の対談の時に、動物(ラット)を5℃の寒冷環境に置くと肝臓でのブドウ糖合成(糖新生)が促進されることを糖新生酵素の活性上昇で認め、この酵素活性上昇には自律神経(交感神経)と内分泌(甲状腺ホルモン)が必須の役割を果たす証拠を得たことを話しました。
この試験で、25℃の室温に置いた対照動物(ラット)の糖新生酵素の活性に日周リズムがあることを認めたので、生理的現象の日周リズム(約24時間周期のリズム、すなわち概日リズム、circadian rhythm)の体内時計にも興味を持ち、体内時計の機構の研究にも従事しました。
その結果、その頃、体内時計の存在部位であることが示唆され始めていた脳・視床下部の視神経交叉の真上にあるニューロンの塊(視交叉上核、suprachiasmatic nucleus、SCN)を電気破壊すると、ラットの摂食行動の概日リズムが消失する(1日中何時間か毎に食べ続ける)ことを認めて世界で初めて報告しました。
その後、世界中で行われた研究により、哺乳類の行動(摂食、飲水、活動、など)、生理的現象(睡眠、体温など)やホルモン分泌などの概日リズムの体内時計が、哺乳類では脳・視床下部視交叉上核(SCN)にあり、その時計の周期は地球環境(明暗など)の24時間周期に同調することが明らかになっていきました。大阪大学を定年退職するまでに、私たちはこのSCNの体内時計機構に関与する蛋白質を新たに4つ発見し、3つの既知の蛋白質の役割を明らかにしたのです。
ところで、体内時計は私たちが持っている静的な時計ではなく、体温、酸素濃度、血糖、血圧などの生存に必須な体内環境を体外環境にハーモナイズして調節して指揮を執る動的な時計です。
しかも自律神経系とか内分泌(ホルモン分泌)系、をコントロールしてハーモナイズする、そういう時計なのです。
すなわち、私たち人類を含めて哺乳類は酸素濃度、体温、血圧、血糖などをある一定の範囲内で維持する能力を持っています。これが体内恒常性(ホメオスタシス)維持能力です。この能力があるので、人類はこの地球環境で生存することができるのです。
ところが、私たちはホメオスタシス維持機能が上記の体内時計破壊動物では障害されていることを示す結果に多数例遭遇しました。例えば、体内時計(SCN)電気破壊動物を25 ℃の室温で飼育すると生存するのですが、5℃の寒冷環境にさらすと、体温が低下していって死んでしまうのです。
また、体内時計SCNの同調に関わる蛋白質がリン酸化されると、交感神経が興奮することも認めました。ホメオスタシスは自律神経系と内分泌系が協調して保たれているので、これらの事実は体内時計を破壊すると、自律神経系と内分泌系によるホメオスタシス維持機構が働かなくなること示しています。つまり、体内時計はホメオスタシス維持のための自律神経系と内分泌系の調節に深く関与していることが分かりました。
――もちろん、人間にも体内時計があるということですね?
永井 体内時計はもちろん人間にもあります。実は人間では、体内時計であるSCNのニューロンの密度が低くて、ニューロンを染める染色では染まらず、同定できなかったのですが、ラットではバゾプレッシン(別名、抗利尿ホルモンADH)が体内時計部位である視床下部のSCNにも存在するので、ADHの抗体でヒトのその部位を染めると、ヒトの体内時計部位が染まることが、オランダ王立脳研究所で明らかにされました。同研究所のRM Buijs博士らのグループと私たちはその後、ラットを用いて共同研究をして、多シナプス性に神経経路を逆行性に輸送されるブタの偽狂犬病ウイルス(pseudorabies virus, PRV)とその抗体を使った研究により、膵臓への体内時計SCNからの自律神経(交感神経と副交感神経)の投射が存在することを証明しました。
その他、世界中の学者たちによってSCNから白色脂肪組織、褐色脂肪組織、腎臓、甲状腺、皮膚などの臓器・組織へ自律神経が投射していることが証明されています。これらの事実は視床下部の体内時計(SCN)が体内時計としてのみならず、自律神経系と内分泌系を調節して体内恒常性(ホメオスタシス)維持をつかさどるコントロール中枢として、とても重要だということを証明しています。
カルノシンが交感神経に及ぼす影響
――他にどのような研究成果がありますか?
永井 鶏の抽出物が、血糖や血圧を降下させるというので、研究を進めたところ、この抽出物には「カルノシン」や「アンセリン」がそれぞれ5%という多量含まれることを認めたので、これらの成分の効果を調べたところ、カルノシンは少ない投与量では副腎、肝臓、膵臓、腎臓、褐色脂肪組織、白色脂肪組織、脾臓――をそれぞれ神経支配する交感神経を抑制して、血糖、血圧、体温、脂肪分解――を低下させ、NKリンパ球の活性(NK活性)を上昇させる効果のあることが分かりました(大量では、それぞれ逆の効果を認めています)。ところが、少量のカルノシン投与は骨格筋を支配する交感神経を促進することも分かりました。
また、「カルノシン」のごく少量を脚の骨格筋に振り掛けると、反対側の同じ骨格筋を神経支配する交感神経を促進することを認めました。それまでにβ2アドレナリン受容体刺激薬は骨格筋への血流を増やして、筋肉量の増加や筋力の増強を引き起こす効果があることが分かっているので、オリンピックのドーピング薬に指定されています。私たちはごく少量のカルノシン投与が骨格筋を支配する交感神経を促進して、骨格筋への血流が増加する効果を引き起こすことを認めています。
さらに私たちは、ラットに輪回し運動をさせると血中のカルノシン濃度が上昇する事実を認めたので、運動すると骨格筋からカルノシンが放出されて、上記のような自律神経に対する効果を引き起こすのではないかと考えました。
ところが、ベルギーのカルノシンの研究者(W. Derave教授)からラットでは血中のカルノシン分解酵素(カルノシナーゼ)の活性が高くないので、運動すると血中濃度が高くなり効くかもしれないが、ヒトではカルノシン分解酵素が高いので、(学生達に)運動させてもカルノシンの血中濃度は増加しないので、ヒトでは運動によって筋肉から放出されるカルノシンが運動による効果を引き起こすという仮説を捨てたと言われました。そこで私たちも、運動で血中にカルノシンが放出されて血中のカルノシン濃度が高くなって、上記の効果を引き起こすという考えは捨てました。
しかし、ラットでごく少量(10pg=44fmol)のカルノシンを片側の脚の骨格筋へ振り掛ける(局所注入する)と反対側の脚の同じ骨格筋を神経支配する交感神経を促進して、β2アドレナリン受容体を介してその骨格筋の血流を増やす効果があることを認めました。そこで、骨格筋で運動により放出されたカルノシンが、骨格筋の求心性の(脳に向かって信号を送る)自律神経線維を介して、反対側の骨格筋の遠心性の交感神経に影響を与えるように、他の臓器・組織を支配する自律神経に影響を与えて、運動による良い効果(血圧降下、血糖低下、免疫促進など)を引き起こす可能性はあると考えています。
カルノシンとヒスタミンの相関性
――カルノシンからヒスタミンはどのようにして作るのですか?
永井 カルノシンはβ-アラニンとL-ヒスチジンからできています。ヒスタミンはカルノシンが加水分解酵素であるカルノシナーゼで分解されて生じた、L-ヒスチジンからヒスチジン合成酵素であるヒスチジンデカルボキシラーゼの作用により作られます。
私たちは、カルノシンの役割を調べるためにカルノシン分解酵素であるカルノシナーゼ2がどこにある(局在する)かも調べました。すなわち、乳酸菌のカルノシン分解酵素(カルノシナーゼ)と、相同性のあるマウスの遺伝子を同定し、その遺伝子を使い、大腸菌のシステムでその蛋白質(カルノシナーゼ2)を発現させて、その蛋白質を作り、その蛋白質を家兎に注射して抗体を作成し、この抗体を用いてラットの脳内でのこの酵素の分布を調べました。
その結果、この酵素(カルノシナーゼ2)は、脳内のヒスタミンニューロンの塊のある部分(視床下部乳糖体)に局在することが分かりました。脳内ヒスタミンニューロンは摂食や睡眠・覚醒などの調節に関与していることが分かっています。
そこで、市販のヒスタミン合成酵素(histidine decarboxylase)の抗体を使って、この部分を抗体染色法で調べたところ、脳内のヒスタミンニューロンにはカルノシン分解酵素(carnosinase2)とヒスタミン合成酵素(histidine decarboxylase)が共存することを発見しました。骨格筋にはカルノシン分解酵素(carnosinase2)とヒスタミン合成酵素(histidine decarboxylase)が存在することが他の研究者により報告されているのと、先に述べたごく少量のカルノシンの脚の骨格筋への局所注入が引き起こす反対側の同じ骨格筋を支配する交感神経の活動上昇は、ヒスタミン3受容体阻害剤であるthiperamideにより消失することから、運動によって骨格筋から放出されたカルノシンが骨格筋でヒスタミンに変換されて、求心性の神経を刺激して、この情報が脳に伝達されて、自律神経活動に影響を与えて、血糖低下、血圧降下、免疫促進などの運動の良い効果を引き起こすのではないかと、私たちは考えています。
さて、私は大阪大学蛋白質研究所の所長も勤めておりました。この研究所では蛋白質の発見・同定やその機能の同定だけでなく、構造も決定する部門が存在します。そこで蛋白質結晶構造解析部門との共同研究で、上記のカルノシナーゼ2の蛋白質を大量に大腸菌のシステムで発現させて、阻害剤や金属イオンなどを加えることにより、私たちはこの蛋白質を結晶化することに成功しました。そして、X線結晶解析法でその部門に結晶構造を解析してもらいました。その結果、この酵素は、阻害剤と金属イオンの存在で二量体を形成し、酵素の触媒部位を構成していることが分かり、阻害剤が入ることで水分子が触媒部位に入れないことが分かり、加水分解酵素であるカルノシナーゼ2の阻害剤による阻害メカニズムが明らかになりました。
――要は水が入ってしまったら、酵素反応が起こってしまうというわけですね。
永井 そういうことです。
――その酵素を発見されたということですか?
永井 繰り返しますが、私たちは乳酸菌のカルノシン分解酵素と相同性のあるマウスの遺伝子を釣り上げて、その遺伝子配列を決めて、それを大腸菌の蛋白質発現系で発現させて、この酵素の脳での存在部位を調べるために抗体を作ったり、結晶化するために大量発現させたということです。
自律神経のカギを握る「ヒスタミン」
――私にはお話が難し過ぎるのですが、アンセリンとかカルノシンと、酵素を結晶化させたということが、具体的に人の運動とか体に対してどういう意味を持つのでしょうか?
永井 これまでお話しして来ませんでしたが、臓器組織を神経支配する自律神経活動の変化にはヒスタミンが関与していて、骨格筋以外の臓器・組織を支配する交感神経が興奮する反応はヒスタミン1(H1)受容体阻害剤で阻害され、副交感神経が興奮する反応はヒスタミン3(H3)受容体阻害剤で阻害されます。骨格筋を支配する交感神経の興奮する反応は、ヒスタミン3受容体阻害剤で阻害されます。
したがって、ヒスタミンの合成や分解は、自律神経が変化する場合は非常に重要なので、ヒスタミンの分解酵素や合成酵素の立体構造が分かって、その構造から、それらの活性化や阻害を引き起こす物質は薬剤として開発される可能性があり、重要な知見です。
また、先にも述べましたが、脳内ヒスタミンニューロンは摂食調節や睡眠・覚醒の調節に関与するため、ヒスタミンの代謝に関わる酵素の促進物質や阻害物質の開発のためには、これらの酵素の構造をX線結晶解析法、NMRや電子顕微鏡などで解析することは、ヒトの健康維持や疾病治療に関わる薬剤の開発につながると言う意味で大変重要なのです。
――ヒスタミンとは?
永井 一般的には風邪の場合の紅腫熱痛という炎症症状を抑える薬にヒスタミン1(H1)受容体阻害剤(一般名抗ヒスタミン)を使用するといった、炎症に関与する物質として想起されますが、その他アレルギー反応、胃酸分泌や上記の自律神経のような場合の神経伝達や、繰り返しますが、摂食調節や睡眠・覚醒の調節に関与する物質です。
――なぜ構造を解析することが必要なのでしょう。
永井 一般的に蛋白質の構造解析を行うということは、そのタンパク質が持つ機能のメカニズム解明に重要な役割を果たします。まして、病気に関係する蛋白質であれば、その蛋白質の構造がどう変化するかを明らかにすることによって、疾患のメカニズムが明らかになり、疾病のメカニズム解明にも繋がり、疾病治療や健康維持の薬品開発にも重要な役割を果たします。
私は医学部出身なので、生化学や生理学の知識や研究で健康を維持し、病気を治療するメカニズムの探究を行ってきました。蛋白質の構造を決めて、その機能との関係を構造機能相関というのですが、それらの研究方法が共存するという極めて有利な機関で研究できたということは大変幸せなことでした。大阪大学蛋白質研究所とは全国の研究機関の研究者達が利用できる共同利用研究所として、その研究設備のみでなく、共同研究のための経費の配慮もあるので、これまでにもまして、全国や世界の研究者のみなさんに使用していただければありがたいです。
(つづく)
【聞き手・文:田代 宏】
関連記事:永井克也大阪大名誉教授に聞く(1)
:永井克也大阪大名誉教授に聞く(2)
:永井克也大阪大名誉教授に聞く(3)
:永井克也大阪大名誉教授に聞く(4)
:永井克也大阪大名誉教授に聞く(5)
<筆者プロフィール>
1943年2月10日生
1967年3月 大阪大学医学部卒業(1968年医師免許)
1972年3月 大阪大学大学院医学研究科博士課程修了(医学博士)
1967年4月〜1968年3月 大阪大学医学部附属病院研修医
1972年4月 大阪大学蛋白質研究所助手(代謝部門)
1974年8月〜1976年10月 米国シカゴ大学関連病院客員博士研究員(内科、主任L.A.Frohman教授)
1977年4月 愛媛大学医学部助教授(生化学第二)
1980年4月 大阪大学蛋白質研究所助教授(代謝部門)
1995年12月 大阪大学蛋白質研究所教授(代謝部門)
2000年4月〜2004年3月 大阪大学蛋白質研究所所長
2006年3月 定年退職(大阪大学名誉教授)
2007年4月 ㈱ANBASを設立。現在に至る。
<所属学会•協会>
日本肥満学会(名誉会員)、国際時間生物学会(理事)、
NPO法人 国際医科学研究会(理事)、
(一社)サイエンティフィックアロマセラピー協会(代表理事)