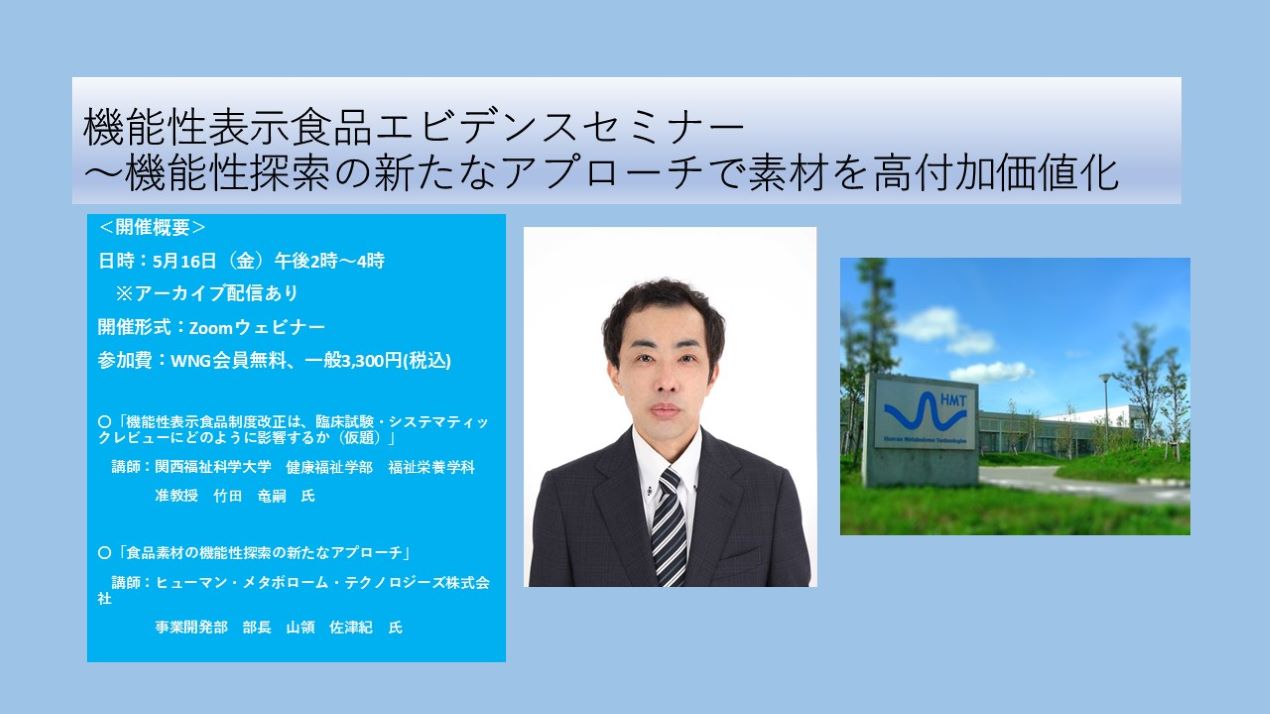消費者庁、デンソー他9社に措置命令 「車両用クレベリン」を使ったサービスにメス
消費者庁は20日、「車両用クレベリン」という役務(サービス)の提供事業者10社に対する措置命令を公表した。
措置命令を受けたのは、世界第2位(国内1位)の売上高を誇る自動車部品メーカー㈱デンソー(愛知県刈谷市、林新之助社長)とその子会社㈱デンソーソリューション(同、新竹敦社長)の他、トヨタカローラ札幌㈱(札幌市豊平区、田中浩至社長)、埼玉トヨタ自動車㈱(さいたま市中央区、嶋田光剛社長)、トヨタモビリティ中京㈱(愛知県名古屋市、山本正夫社長)、ネットトヨタ高松㈱(香川県高松市、朝倉一社長)、東海マツダ販売㈱(愛知県名古屋市、大貫秀樹社長)、㈱神戸マツダ(兵庫県神戸市、橋本覚社長)、㈱広島マツダ(広島市中区、山根一郎社長)、㈱西四国マツダ(愛媛県松山市、江藤忠義社長)などのカーディーラー8社。
今回対象となったのは、商品ではなく役務(サービス)。例えば、「カーディーラーの従業員が消費者から預かった自動車の中で、15分間専用機器を使ってクレベリン(二酸化塩素ガス)を発生させることによって除菌サービスを提供する」(消費者庁)などの行為が行われていた。
また、専用機器に専用カートリッジをセットすることでクレベリンを発生させ、約3カ月有効な除菌効果が得られるというサービスを提供し続ける中、自社ウェブサイトやウェブサイトに掲載していたリーフレットにおいて、少なくとも2022年8月~24年1月までの間「車両用クレベリンの効果」、「効果持続(目安)約3カ月」、「二酸化塩素のチカラでウイルスや菌を99%除去!!」などと表示していた。このような表示に基づき、「車両用クレベリン」は全国のカーディーラーに広く波及していたものとされる。
消費者庁が上記企業に対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料はいずれも根拠を示すものとは認められなかった。
デンソーとデンソーソリューションは自社ホームページで「『車両用クレベリン』に関する景品表示法に基づく措置命令について」とするお知らせを掲載。「車両用クレベリンは、二酸化塩素を発生させる専用カートリッジを発生機に差し込み、車室内に二酸化塩素を噴霧する除菌・消臭サービスです。本命令は、ウェブサイト上で、車両用クレベリンの施工サービスを受けることにより、車室内において除菌等の効果が約3か月間あると誤解される表示がされていたことによるものです。なお、施工中の除菌等の効果について否定されたわけではございません」と釈明している。
サービスに用いられていた二酸化塩素発生器は、「クレベリン」シリーズの製造販売元である大幸薬品㈱(大阪府吹田市、柴田高社長)とデンソーが共同で開発したもの。違法表示の中には「「除菌・消臭サービスメニュー大幸薬品×DENSO共同開発 デンソークレベリン車両用」などが見出されるが、大幸薬品によれば、同社はデンソーに「車両用クレベリン」の部品を提供しているのだという。
大幸薬品は「クレベリン」シリーズの販売に当たり、合理的根拠のない優良誤認表示を行ったため、22年1月20日と同4月15日の2度にわたり消費者庁から措置命令を受けた。今回の件について同社広報部は、「他社の製品のことなので表示にまで関与はできないし、コメントも難しい」としながらも「あくまで効能に対しての措置命令ではない」と付け加えた。
デンソー、大幸薬品共に「除菌効果が否定されたわけではない」、「効能に関しての措置命令ではない」としているが、果たしてその言葉を額面どおりに受け取っていいものだろうか?
(⇒つづきは会員専用ページへ)
デンソーと「車両用クレベリン」の共同開発を行った大幸薬品は2022年1月20日、同社が販売する『クレベリン スティック ペンタイプ』(携帯型)、『クレベリン スティック フックタイプ』(掛け型)、『クレベリン スプレー』、『クレベリン ミニスプレー』の4商品に対して措置命令を受けた。消費者庁が他の置き型2商品(60g・150g)についても調査を進めていたところ、同社が「措置命令の仮の差止請求」を東京地方裁判所に申し立て、それが認められたために執行が遅れる。消費者庁は即時抗告し、東京高等裁判所がその訴えを容れて地裁の決定を覆したことで、同4月15日、置き型2商品についても合理的な根拠がないことを理由に措置命令が下された。
東京高裁で行われた裁判で、裁判所が大幸薬品の主張を認めたところが1つだけある。それは「クレベリン置き型150g」の閉鎖試験空間下における効果だ。大幸薬品はその後、「消費者庁と調整」(同社)の上、刷新したパッケージでクレベリン商品の販売を開始した。昨年12月12日以降、「事実、クレベリン。」という新コマーシャルも全国放映した。これらの根拠となっているのは、先に挙げた「閉鎖空間」での効果に基づいている。したがって、(詳しくはウェルネスデイリーニュース「消費者庁VS大幸薬品(9)」に記載しているが)実生活空間における除菌効果については高裁も認めることはなかった。
この判決は今も効力を有しており、消費者庁はあくまで実生活空間で効果があるかのような表示についてはその後も容赦なく措置命令の大ナタを振るってきた。この点は今回も同じである。今回、消費者庁は「サービス」に関する表示について、「全て優良誤認に認定された」(同庁)と話している。
これらの事実から判断すると、デンソーや大幸薬品の言う「効果は否定されていない」という言葉は、正確には「一定の条件下における閉鎖空間での効果は否定されていない」となる。乗用車とて乗り降りの際にはドアを開閉する。窓の開閉などのいろいろな方法で車内換気も行われる。そのような状態を閉鎖空間と呼べるかどうかだろう。筆者がかつて九州に赴いたとき、乗車したタクシーの車内に「クレベリンによる除菌効果」をうたったステッカーが貼ってあるのをしばしば見かけた。コロナ禍の時期でもあり、大きなセールスポイントとなったかもしれない。しかし窓は開けられていた。今思うと、「車両クレベリン」が全国津々浦々にまで広く普及している証だったかもしれない。
発表資料はこちら(消費者庁HPより)
〇クレベリンをめぐる経緯(まとめ)
:消費者庁、空間除菌商品に措置命令
:クレベリン訴訟、高裁が地裁決定覆す
:クレベリン置き型2商品も根拠なし
:大幸薬品、クレベリンの表示を改訂
:消費者庁VS大幸薬品(1)
:消費者庁VS大幸薬品(2)
:消費者庁VS大幸薬品(3)
:消費者庁VS大幸薬品(4)
:消費者庁VS大幸薬品(5)
:消費者庁VS大幸薬品(6)
:消費者庁VS大幸薬品(7)
:消費者庁VS大幸薬品(8)
:消費者庁VS大幸薬品(9)