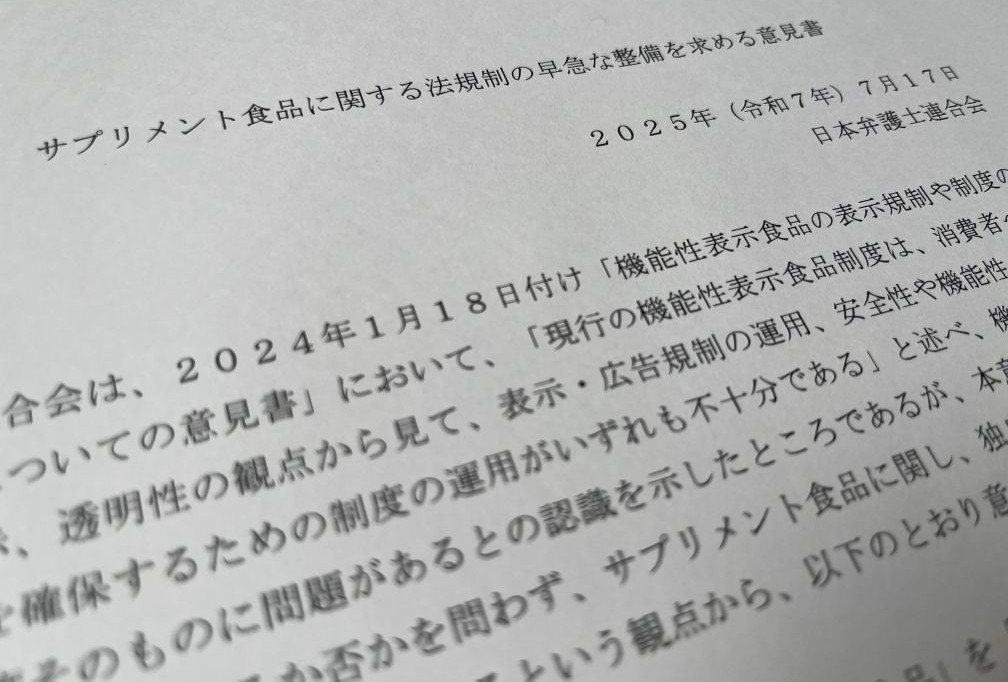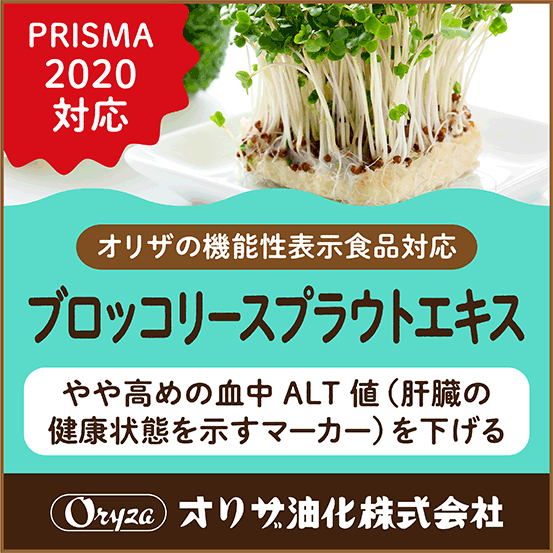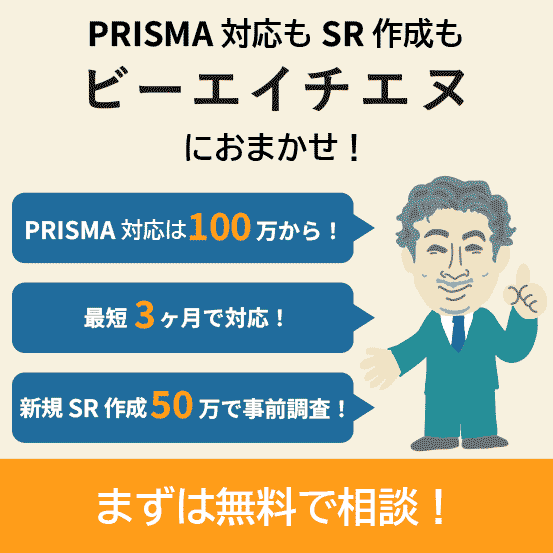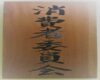日弁連、サプリ法の早期制定を求める 厚労大臣・消費者庁長官らに意見書、営業許可制の導入など主張
日本には現状存在しない「サプリメント法」を制定するよう求める意見書を日本弁護士連合会が取りまとめ、厚生労働大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)・消費者庁長官宛てに提出した。欧米など海外諸国と同様に、その目的や形状などに着目した統一的なルールを定めるべきだと主張。機能性表示食品であるか否かを問わず、サプリの製造、販売、品質管理、広告に関する法規制を早急に整備するよう求めている。
日弁連が厚労大臣らに提出したのは、「サプリメント食品に関する法規制の早急な整備を求める意見書」。今月18日付けで提出したという。
日弁連はもともと、機能性表示食品制度を疑問視していた。だが、昨年生じた小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題をきっかけに、問題意識の矛先をサプリ全体に向けた。今年2月、「サプリメント法の必要性を考える」と題したシンポジウムを開いていた。
日弁連は意見書の中で、サプリの定義を提示。「通常の食事を補完するものとして摂取される食品で、天然由来の抽出物であって分画、精製、化学的反応等により本来天然に存在するものと成分割合が異なっているもの又は化学的合成品を原材料とする錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の食品」とした。
「通常の食事を補完するもの」という定義は、諸外国の先例に倣ったもの。「錠剤、粉末剤、液剤の菓子等が(サプリに)含まれないことを明確にする」ために取り入れたという。現行の通知(3.11通知)や法令(食品表示基準における機能性表示食品のうちサプリの定義)にはない考え方を示した格好だ。
原材料のGMP義務化、表示許可制の導入なども主張
意見書では、サプリを統一的に規律する法律(サプリ法)に設けるべき規定も提示。営業許可制の導入をはじめ、原材料から最終製品までのGMP基準適合義務化、表示内容に対する許可制の導入、健康被害情報の提供及び公表の義務化──などを提案した。具体的には以下のとおり。
(1)サプリメント食品の製造を業として行う場合及びサプリメント食品の原材料(未加工の農畜水産物を除く。以下同じ。)の製造を業として行う場合は、営業許可を要するものとすること。
(2) サプリメント食品及び同食品の原材料の製造については、監督官庁が定める最新のGMP
基準に適合していることを義務付けること。
(3) サプリメント食品を販売に供する場合は、当該製品に係る表示内容についての許可(以下「表示許可」という。)を要するものとすること。
(4) サプリメント食品の表示許可を得た業者に対して、当該サプリメント食品に係る健康被害情報の提供及び公表を義務付けること。
(5) サプリメント食品について、何人もその効果又は機能に関して、明示的か暗示的かを問わず、虚偽又は誇大な広告をしてはならないことを明記すること。
(6) サプリメント食品の過剰摂取等を防止し、健康的な食生活等の健康維持・増進に関する知識の向上を図るための注意喚起及び啓発活動の充実を関連省庁及び地方公共団体に求めること。
以上を示した上で、上記(5)について、「実効性を確保するため、国は、誇大広告等の厳格な取締りを積極的に行うべき」だと訴えた。
食衛法改正による統一規制導入には反対
サプリの統一的な法規制の整備を求める日弁連の主張は、小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題の対応に当たった関係閣僚会合の対応方針と重なる部分もある。関係閣僚会合は、同問題を受けた「今後の検討課題」として、「食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、許可業種や営業許可施設の基準の在り方などについて、必要に応じて検討を進める」ことを挙げているためだ。
一方、関係閣僚会合は、それを食品衛生法の枠組みの中で検討することを示唆しているのに対し、日弁連は意見書で「衛生に関する規律である同法を改正するのではなく、新たに個別の法律を制定すべき」と主張。そうすべき理由について、サプリは「健康被害情報の収集の義務付けや広告に関する規制も一般の食品とは異なるレベルでなされるべき」だと指摘しつつ、「過剰摂取への注意喚起や、日常の食生活の重要性についての啓発活動も重要であると考えられる」とした。
サプリ法の制定を求める日弁連の主張を、当事者である健康食品業界はどう受け止めるのか。原材料から最終製品までの製造に関する営業許可制の導入や、国が定めるGMP基準の原材料も含めた適合義務化のほか、表示内容に対する許可制の導入など、業界の意見を二分、あるいは到底受け入れられないであろう法規制を整備するよう、日弁連は国に求めている。業界としての意見を明確に示していく必要がありそうだ。
【石川太郎】
関連資料:「サプリメント食品に関する法規制の早急な整備を求める意見書」(日弁連のウェブサイトへ)
関連記事:日弁連、サプリ法の必要性を議論 シンポ開催、有識者交えて2時間
:小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題、日弁連が会長声明
:日弁連、機能性表示制度の見直し要求 消費者庁長官らに意見書提出