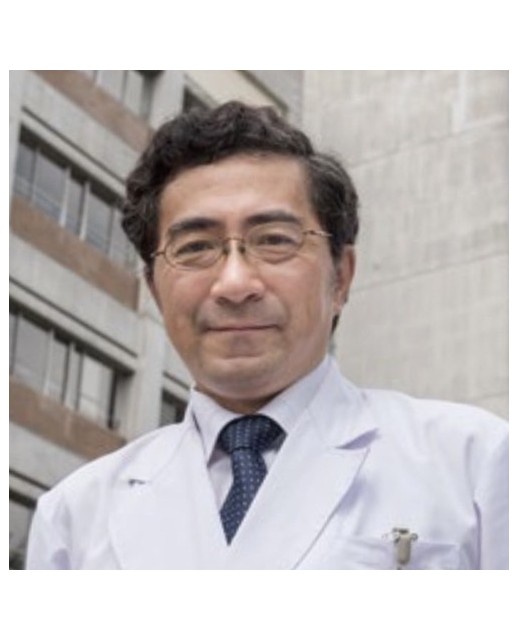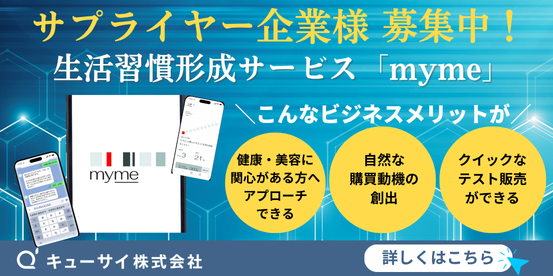CBN規制に関する考察と提言(後) 【寄稿】カンナビノイド研究者の佐藤教授「科学的根拠に基づいた合理的規制を」
大麻草に含まれるカンナビノイドの一種、カンナビノール(CBN)が「指定薬物」に指定されようとしている。指定されると、CBNを含む製品の販売などが全面的に禁じられることになる。だが、市場にはそうした商品が数多く流通されており、カンナビジオール(CBD)関連製品への影響も懸念されている。指定薬物化以外の規制策は考えられないのだろうか──カンナビノイド研究で国内第一人者である佐藤均・静岡県立大学薬学系大学院客員教授(=写真)による寄稿を前後編の2回に分けて掲載する。
本稿は後編。前編はこちら。【編集部】
② 厚労省CBN精神毒性評価レポートへのコメントと「CBNの1日摂取目安量」の提案
続いて、厚生労働省がまとめたCBN精神毒性評価レポートの各項目に対してコメントすることによって、「CBNの1日摂取目安量」に関する私の見解を述べさせて頂く。ただし、CBNが禁止薬物に指定された後は、CBNを意図的に添加して製造販売することができなくなり、1日摂取目安量という概念は意味がなくなる。そのため、あくまでも現在のCBN市場に対する提言である。
1)CB1受容体結合試験の解釈
チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いた細胞実験において、CBNのEC50が算出不可(>10⁻⁵ M)であったことは、CB1受容体活性がΔ9-THCの30分の1以下であることを示している。この結果を参考にすると、CBD製品中に含まれて良いCBNの上限濃度値は、Δ9-THCのそれの30倍までは許容できる、という結論を導くことが可能である。
2)マウスカタレプシー試験の解釈
マウスにおけるカタレプシー様無動状態の発現に用いられたCBNの腹腔内投与量は5〜50 mg/kgであった。FDA基準による体表面積換算(マウス→ヒト換算係数:約1/12.3)とバイオアベイラビリティの違い(腹腔内投与≒100% vs 経口投与≒5〜10%)を考慮すると、マウスの5mg/kgに対応する60kgのヒトの経口投与換算量は約48〜96mgと推定される。
この投与量を基礎にして、安全マージンを考慮すると、ヒトにおいてCBN 20mgを摂取上限量とすれば良い、という結論を導くことが可能である。
3)THCとの力価比較試験の解釈
動物実験(文献4)において、CBNがΔ9-THCの7倍程度の用量で類似作用を発現した。このことから、CBD製品中に含まれて良いCBNの上限濃度値は、Δ9-THCのそれの7倍までは許容できる、という結論を導くことが可能である。
4)睡眠作用試験の解釈
睡眠作用を調べた動物実験(文献5)において、用いられたCBNの投与量は10、30、100 mg/kg(体表面積換算で60kgヒトに換算すると約49、146、488mg)、また活性代謝物である11-水酸化-CBNの投与量は1、3、10 mg/kg(体表面積換算で60kgヒトに換算すると約4、9、14.6、48.8mg)であった。
この実験が示唆することは、高用量のCBNを摂取すると活性代謝物の脳内濃度が高くなることによって強い睡眠導入作用が発現することである。逆にいうと、低い摂取量(例えば上述のように摂取上限量CBN 0.3 mg/kg = 18mg/60kg)であれば安全性であるという結論を導くことが可能である。
5)ヒト臨床研究の解釈
成人男性を対象とした臨床研究(文献6)において、Δ9-THC(25mg)単独では陶酔感、目眩や眠気など精神症状を報告したが、CBN(50mg)単独では、被験者の主観的なスコアはプラセボと変化なかった。これにより、CBNが50mg以下であれば安全性に問題ないと考えることができる。
6)CB1受容体結合試験の解釈
厚労省によるCBN精神毒性評価レポートでは、CB1受容体への結合親和性が精神毒性と同義であるかのような記載がされている。しかし、実際にはアゴニスト(作用薬)とアンタゴニスト(阻害薬)では、結合親和性が同じであっても作用する方向は全く逆である。例えば、リモナバント(Rimonabant)という合成カンナビノイドのKi値は1.8nMと極めて高いが、CB1受容体の活性化は全く行わない。また、同じアゴニストであっても、部分的にしか活性化しない部分アゴニスト(partial agonist)であれば、結合親和性(Ki値)のみで受容体活性強度を定量的に評価することはできない。CBNの場合は完全アゴニストに比べて約29%しか最大効力を示さない部分アゴニストであり、Ki値の大小でその精神毒性を比較評価することには無理がある。
7)山梨学院大学生の飛び降り事故とCBN含有製品摂取との関係性
一般論としては、ヒトにおいて起きた事象と摂取物質の間の因果関係を示すことは容易ではない。だが、CBNの主作用は鎮静や眠気であって、飛び降りのような突発的事故がCBNによるものと断定するには少々無理がある。
あくまでも私の推測であるが、CBNを過剰量含む該当製品にΔ9-THCやTHCHといった幻覚物質が含有されていて、CBN が代謝酵素CYP2C9を阻害したために幻覚物質の血中濃度を上昇させた結果として事故が起きた可能性がある。同様なメカニズムは、厚生労働省作成によるCBN精神毒性評価レポート・引用文献6からも示唆される。その場合、CBN製品の買い上げ調査によって幻覚物質混入製品を市場から排除することによって、健康被害の拡大を抑えるべきであろう。特に、CBNの代謝酵素であるCYP2C19の活性が低い個体(poor metabolizer)の割合が日本人(約20%)では欧米人(1〜4%)に比べて非常に多いことを考慮すると、一部の日本人では非常にリスクが高まる。
私の勘違いであって欲しいことではあるが、CBNを大量に含有する食品を摂取した場合、尿検査によってTHC偽陽性を示す(THC-COOH認識抗体がCBN-COOHと交差反応を示す)ことが知られているため、大量のCBNを摂取させることでTHCの作用を高めるとともに、CBNを隠れ蓑にして捜査撹乱しようとする悪質な意図さえ感じられるのである。その場合、CBNは加害者(perpetrator)ではなくて被害者(victim)といえる。
結論:CBNの1日摂取目安量の提案
以上の科学的根拠を総合的に判断し、私が提案するCBNの1日摂取目安量は以下の通りである。
算出根拠:
• ヒト臨床研究におけるNOAEL(無毒性量):50mg
• 安全係数(Uncertainty Factor):2.5(個人差および経口投与時の不確実性を考慮)
• 算出式:50mg ÷ 2.5 = 20mg
提案する1日摂取目安量:CBN 20mg
この摂取量を遵守できるようにCBN製品の包装単位や含有濃度を調整し、製品ラベルにおいて以下を明確に記載するよう製造販売者には徹底して頂きたい。
最後に
我が国で現在用いられているΔ9-THCの残留上限値は、厚労省が、EUのEFSA(欧州食品安全機関)が設定した急性参照用量(Acute Reference Dose: ARfD)の1μg/kg/dayという値に基づいてCBD製品のΔ9-THC残留上限値を政令で定めたものである。英国やドイツでも、EFSAと同等の基準でΔ9-THCを規制している。
しかし、実際に市場に出回っているCBD製品の買い取り調査結果では、英国では29製品中16製品において平均400ppm のΔ9-THC、平均100ppmのCBNが検出されていた(Cannabis Cannabinoid Res. 2022;7(2):207-213)。また、ドイツでは26製品中13製品において平均536ppm のΔ9-THCが検出された(J. Consumer Protection and Food Safety 2024;19:259-267)。
このような「規制と現実の乖離」は、もともと天然の大麻草から採取した原料からTHCを完全除去することが容易でないことに加えて、CBD製品中でCBD→THC→CBNという化学反応(変換)が時間経過とともに徐々に進行することから、世界的に問題となっているのである。
これを解決するにはCBD→THC変換を抑制する事が求められるが、私が技術顧問を務める日本CBD分析センター(JCRL)では最近、CBD→THC変換を抑制する方法を精力的に研究しており、一定の成果を上げていることは希望が持てる。これに加えて、EFSAによる1μgΔ9-THC/kg/dayというARfD値が相当の安全マージンを考慮して定められたことや、CBDがTHCと共存している状態であればCBDはCB1受容体へのTHC結合(精神賦活化)を阻害することを考慮すると、このARfD値も将来的には少なくともに5倍程度に上げることが望ましいと考える。
Δ9-THC/ THCA分析結果に関しては、超微量分析であるが故の施設間のバラツキや、保管・輸送中のCBD→THC変換に由来する濃度の不確実性などが業界で大きな問題となっており、これが大手企業のCBD市場参入を妨げるだけでなく、製品の遵法性保証に不安を生じさせてしまう状況は好ましくないであろう。
まとめと提言
1.推奨する法整備
方式2(CBNを指定薬物に追加し、Δ9-THCの50倍程度の残留上限値を設定する方式)を推奨する。この方式は、CBD製品中の微量CBNを許容しつつ、中・高用量CBN製品の流通を防止できる規制設計である。
2.業界への要請
• CBN含有製品の用量規制(1日摂取量20mg以下)
• 製品ラベルへの明確な注意表示の徹底
• CBD原料の品質管理徹底(Δ9-THC・CBN濃度の定期検査)
• CBD, CBN, CBG等のカンナビノイド医薬品開発を進める
3.政府への要望
• 食品安全委員会によるCBDのリスク評価の実施
• CBD含有食品の規格基準の早急な策定(厚生労働省令として公布)
• 比例原則に基づいた合理的な規制設計(ゼロ・トレランスではなく残留上限値の設定)
• 業界との対話を通じた実効性のある規制の構築
以上、CBN規制に関する私の考察と提言を述べさせて頂いた。科学的根拠に基づいた合理的な規制が実現され、CBD業界の健全な発展と消費者の安全が両立することを切に願っている。
(了)
<佐藤均教授プロフィール>
東京大学薬学部卒業後、金沢大学薬学部、米国国立衛生研究所(NIH)、国立がん研究所、スイス・バーゼル研究所・客員研究員、東京大学医学部助教授での研究活動を経て25年間昭和大学に在籍。「自己満足に終わる研究ではなく、医療や社会に資する研究を行うことが薬学の本質」をモットーに、薬物動態学を中心に、臨床試験やゲノム解析を含む幅広い研究を手掛けている。
関連資料
:厚生労働省「CBN(カンナビノール)の精神毒性評価について」(政府のe-GOVサイトへ)
:2025年10月28日「薬事審議会指定薬物部会」議事録(厚生労働省のウェブサイトへ)
関連記事
:CBN規制、パブコメ期日1カ月延長 厚労省、意見の検討材料に精神毒性評価データを追加
:CBN規制巡るパブコメで厚労相見解 事故との因果関係「証明は困難」
:どうなるCBN規制 事業者団体が反対意見 指定薬物化に「科学的根拠あるか」
: CBNを「指定薬物」に追加へ 精神毒性の懸念を理由に規制強化、意見募集開始
: CBN製品の安全確保へ 業界団体が共同自主規制宣言を発表