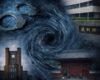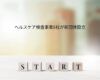健康食品GMP実践的対応ガイド(3) 【寄稿】GMPの基本~「品質は作り込む」という思想とGMP三原則
㈱シーエムプラス シニアコンサルタント 田中良一
前回は、健康食品GMPの全体像と責任の所在について解説しました。第3回では、GMPの根底に流れる思想と、その行動指針となる「GMP三原則」に焦点を当てます。GMPは単なる規制や手順書の集合体ではなく、品質に対する哲学そのものであることを理解することが、実践への第一歩となります。
1.健康食品に求められる品質
GMPを考える前に、まず健康食品の特性を再確認する必要があります。
• 摂取するのは「健康な人」:医薬品が主に疾病に罹患した患者を対象とするのに対し、健康食品は基本的に「疾病に罹患していない者」が、さらなる健康の維持・増進を目的として摂取します 。
•「期待」を裏切らないこと:消費者は、コレステロール値の改善や疲労感の軽減といった「機能性」を期待して製品を手に取ります 。この期待を裏切らないことが、健康食品の品質の根幹と考えます。
o 期待通りの効果:機能性関与成分が、表示された通りに、均一な量で含まれていること 。
o 期待以外のことが起きないこと:過剰な成分の含有や、予期せぬ異物・微生物の混入による健康被害がないこと 。
「これを飲まなければ健康被害は起きなかった」と消費者に後悔させることは、絶対にあってはならないのです。
2.「品質は作り込む」という思想
では、どうすれば常に一定の品質を保証できるのでしょうか。ここで重要になるのが「品質は作り込む」というGMPの基本思想です。
多くの人は、「最終製品の試験検査で合格すれば品質は問題ない」と考えがちです。しかし、それは大きな誤解です。錠剤やカプセル剤の品質を、ロットの中からいくつかのサンプルを抜き取って検査するだけでは、ロット全体の品質を保証することはできません。たまたま検査したサンプルが合格だっただけで、他の製品には成分の偏りや異物が存在するかもしれないのです 。
したがって、GMPでは、最終製品の試験検査だけでなく、原材料の受け入れから製造、保管、出荷に至る全ての製造や試験関連の工程をあらかじめ管理し、品質を確保する(製造管理及び品質管理)ことを求めます。これが「品質は試験で確認するのではなく、工程で作り込む」という考え方です。
3.「GMP三原則」
この「品質は作り込む」という思想を、より具体的に行動に落とし込むための指針として、提唱されているものが「GMP三原則」です 。
1.人為的な誤りを最小限にする
o 人間は誰でも間違いを犯す(ヒューマンエラー)という前提に立ち、標準作業手順書(SOP)の整備、教育訓練、ダブルチェック体制などを通じて、ミスが起きにくい仕組みを構築します。
2.汚染および品質低下を防止する
o 異物混入、微生物汚染、製品間の成分の混じり合い(交叉汚染)などを防ぐため、施設の設計、清掃・洗浄、原材料や製品の適切な保管などを徹底します。
3.高い品質を保証するシステムを設計する
o 上記の2つを確実に実行し、継続的に改善していくための品質保証システム全体を構築します。これには、組織体制の整備、バリデーション、変更・逸脱管理などが含まれます。
GMPの本質は、「常に安全で同じ品質の製品を作り続ける」ための仕組みづくりにあります。その根底には「品質は作り込む」という思想があり、それを実現するのがGMP三原則です。
次回は、この三原則、特に「高い品質を保証するシステム」を設計する上で不可欠な、経営層の責任と主要な責任者の役割について詳しく解説します。
【編集部より】本連載は原則、週1回のペースで掲載します。また本連載は、シーエムプラスが運営する「GMP Platform」にも掲載されます。

関連記事
:健康食品GMP実践的対応ガイド(1)なぜ今、適正製造規範への適切な対応が求められるのか
:同(2)健康食品GMPの全体像~医薬品GMPとの類似性と責任の所在