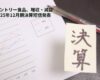東大、社会連携講座を全面改革へ 不適切行為受け倫理・ガバナンス強化を公表
東京大学はきのう3日、臨床カンナビノイド学社会連携講座に関連して発覚した不適切行為を受け、制度の抜本的見直しに着手すると発表した。総長メッセージとアンケート調査結果、改革策を公表し、倫理意識徹底や本部主導のガバナンス強化など4本柱の改革方針を示した。外部資金活用の健全性を担保する体制構築を目指す。
総長「社会の信頼に関わる重大事案」
同大学の藤井輝夫総長は、社会連携講座における不適切な行為について、「社会の信頼に関わる重大な事案」との認識を表明。大学としての責任を重く受け止め、外部弁護士事務所の指導の下で調査を進め、規則違反には厳正に対処する方針を示した。
さらに、同様の事態を再発させないため、コンプライアンス体制を抜本的に再構築する必要性を強調。特に社会連携講座に関しては、(1)教職員の倫理意識の徹底、(2)大学本部によるガバナンスの強化、(3)講座等の設置・契約時のチェック体制の整備、(4)活動開始後の部局による管理強化――という4本柱の改革に取り組むとした。
全教職員対象の記名式アンケート
同大学は、今年7月18日から全教職員1万8,000人を対象とした記名式のアンケート調査を実施し、その結果を公表した。
アンケートの回収率は71.3%で、役員・教職員の回答率は81.5%、その他の構成員(短時間勤務の者等)は62%だった。有為と判断されたアンケート回答およびホットライン通報は計91通で、外部弁護士の助言に基づき以下の4区分に分類された。
① 倫理規程に抵触する可能性がある事案(8通)、②抵触の可能性が否定できず精査を要する事案(37通)、③抵触しないと判断される事案(38通)、④社会連携講座等に関する別途調査対象(8通)だった。
上記のうち、自己申告として「自身が接待・贈与を受け、またはその要求をしたという回答」50通、他の職員による「接待・贈与・要求を見聞きした」41通だった。
外部弁護士による正式調査を開始
上記①の8通については、東京大学コンプライアンス基本規則に基づく正式調査をすでに外部弁護士の下で開始している。倫理規程に抵触すると確認された場合は、厳正に対処するとしている。
上記②の37通については、申告者に対し具体的な内容の確認を行い、必要に応じて追加調査を実施。抵触の可能性があると判断された場合は、同様に厳正に対処する。
教職員の意識や制度に関する課題も抽出
アンケートでは、倫理規程に関する調査に加えて、教職員の社会連携講座に関する問題意識も尋ねている。
2,000件以上の回答があった項目は、「教職員のコンプライアンス意識」(3,188件)、続いて「権威・影響力のある教職員に意見できない風潮・組織風土」(2,502件)、「指導的立場にある者へのチェック機能の欠如・反対意見を言い難い状況」(2,203件)、「教職員の給与・報酬」(2,021件)と続いた。
このほか、「社会連携講座等の設置後の管理・運用」、「教職員に対するコンプライアンスに関する教育研修・啓発活動」、「教育研究資金の調達方法」、「人事考課制度」なども問題点として指摘されている。
自由記述では、実効性あるコンプライアンス研修の必要性、教員個人への過度な権限集中、大学としての統一的な運営体制、外部との連携におけるガバナンス整備、意見を言いやすい職場環境の構築などが課題として挙げられた。
改革の柱は倫理意識と本部主導体制
これらを受けて大学側は、民間企業などとの間で締結される社会連携講座や寄付講座、共同研究、受託研究といった外部資金を受け入れる研究・教育活動について、制度全体の見直しを図る改革策を公表した。本部主導の抜本的なガバナンス強化と、教職員の倫理意識徹底を両輪とする制度改革が打ち出された。
今回明らかとなった事案では、一部教職員の倫理意識の欠如、講座設置相手の確認不足、運営体制の不備などが指摘され、制度全体に共通する構造的な問題として大学は受け止めた。外部資金の活用自体は重要であるとの立場を維持しつつ、その信頼性と健全性を担保するには、組織的・制度的な改革が不可欠であると判断した。
改革策の第1の柱は、教職員の倫理意識の徹底だ。特に、教職員が「みなし公務員」であり、供応接待が禁止される立場にあることを再認識させる必要がある。倫理保持に関するセルフチェックリストの導入や、研修、周知資料の整備などが実施される見通しだ。
第2に、大学本部によるガバナンスの強化が図られる。これまで契約締結から講座設置、管理運営までを主に部局の裁量に委ねていた体制を改め、本部が制度運用全般に関与する構造とする。契約内容に懸念がある場合には、本部に相談できる仕組みを整備し、RRI(責任ある研究・イノベーション)やELSI(倫理的・法的・社会的課題)などの観点から本部が適否を判断する。
資金負担のない契約や著しく低額の契約については、明確な理由説明を求め、内容の精査を行う。また、講座廃止を含めた是正措置の権限も本部が有することとなる。
第3に、講座の設置および契約時の確認体制が整備される。全学共通のガイドラインと審査フローを明確化し、契約相手の財務状況や法人格などを含むリスクベースのチェックリストを用いて精査する体制を構築する。外部資金による雇用人員の採用についても、透明性・公正性の観点から第三者の関与が求められるようになる。
第4に、講座等の設置後における管理運営体制の強化が進められる。部局は案件ごとに入出金のモニタリングを行い、未入金が発生した場合には大学本部に報告、本部が必要に応じて契約相手から事情を聴取する。こうした流れにより、金銭管理の徹底と透明性の確保を図る。
制度設計にあたっては、大学本部に「倫理ワーキンググループ」と「ガバナンスワーキンググループ」の2つの専門組織を設け、具体的な運用ルールや様式の検討を行った。倫理面ではチェックリストの作成や事例集の整備が進められ、ガバナンス面では審査体制や契約書の様式、誓約書、申請書などが再構築された。
大学は今後、これらの改革策を順次運用に移し、継続的な制度の見直しを行う方針。社会との信頼に根ざした外部資金活用の推進を前提としつつも、組織的自律性と説明責任を伴う体制構築により、大学としての健全性と透明性を確保していく考えだ。
【田代 宏】
社会連携講座等検証・改革委員会による「改革策」について(東大HPより)
関連記事:大麻草由来ビジネスが迷走 国内向けてんかん薬の治験「失敗」で暗雲か?
:日本化粧品協会が東大側を提訴か 【続報】臨床カンナビノイド学講座、泥沼化も
:高額接待問題、マスコミ各社が報道 JCA、来週にも民事提訴、近く記者会見も
:東大教授の接待強要疑惑の余波広がる 中小企業団体連盟も講座の継続求めJCAと連携へ
:東大教授の高額接待強要疑惑に思う 国立大学に問われる研究倫理と公的資金の適正運用
:東大のCBD講座巡り訴訟勃発 JCAと中団連、接待強要・講座閉鎖で教授と大学を提訴
:日本化粧品協会が東大と教授らを提訴 【動画公開】エスカレートする接待強要に困惑、記者会見で訴え
:東京大学と化粧品協会の訴訟開始 協会が研究講座閉鎖を巡り契約無効と損害賠償を主張
:東大、社会連携講座を全面改革へ 不適切行為受け倫理・ガバナンス強化を公表
:東京大学と化粧品協会の訴訟開始 協会が研究講座閉鎖を巡り契約無効と損害賠償を主張
:東大と化粧品協会の対立構図鮮明に 契約消滅の是非、接待・恐喝の真偽は?
:訴え一部取り下げでも争点は消えず 確認請求を整理、契約関係と相殺の可否は引き続き審理へ
:東大教授を収賄容疑で逮捕 臨床カンナビノイド講座設置巡り警視庁発表
:日本化粧品協会の引地代表を書類送検 逮捕・勾留はなく刑事手続き進行、代理人が事実認める
:東大医学部不祥事の深層 刑事と民事が照らす研究資金制度の盲点