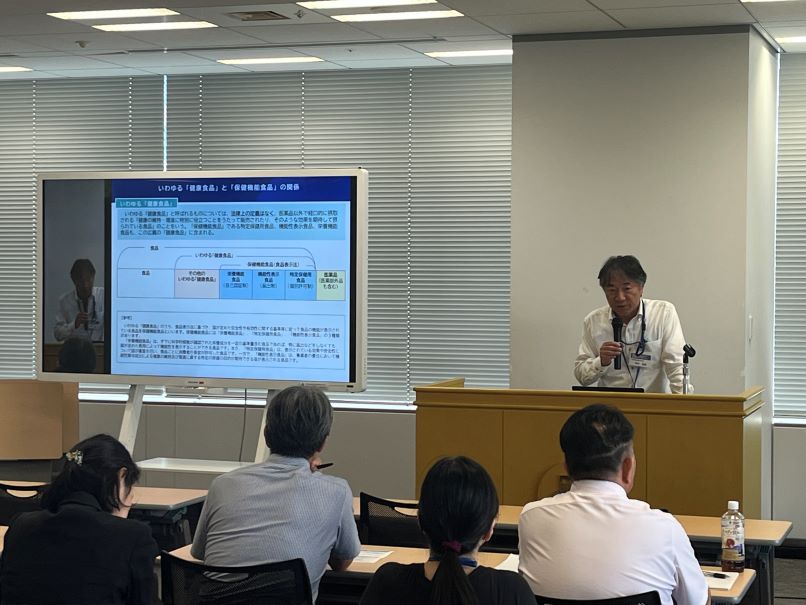厚労省と消費者庁が揃って登壇 日本食品安全協会講演会、GMP実施状況確認や健康被害情報の現状など説明
サプリメントなど健康食品に関するアドバイザリースタッフの育成などを手がける(一社)日本食品安全協会(北市清幸理事長=岐阜薬科大学教授)は25日、関西大学東京センターの会場とオンラインのハイブリッドで毎年恒例の教育協議会講演会を開いた。今回のテーマは、「健康食品のこれから」
事務局によると、会場とオンラインを合わせ、教育関係者や健康食品業界関係者など200人超が参加。厚生労働省食品監視安全課の今川正紀課長をはじめ、消費者庁食品表示課保健表示室の鮫島那奈課長補佐のほか、健康食品業界団体から(一社)健康食品産業協議会(JAOHFA)の櫻井護理事(サントリーウエルネス㈱品質部)、消費者団体から(一社)FOOD COMMUNICATION COMPASS(FOOCOM)の森田満樹代表の4人が講演した。
GMP実施状況の確認・助言、来年1月以降「フォローアップ」も
消費者庁の鮫島課長補佐は、「機能性表示食品制度見直しのポイント」と題して講演。今年4月から全面的に施行している改正機能性表示食品制度の概要を解説する中で、錠剤やカプセル剤などの加工食品(サプリメント)の製造・品質管理に遵守義務をかけたGMPについても触れた。
GMP遵守の義務化は昨年9月に施行。ただし来年8月末までの経過措置が設けられている。そのなかで、食品表示課に今年4月発足のGMPに関する専門チームが、5月末から、全国に点在する機能性表示食品のサプリの製造・加工を行う施設を1つずつ訪れ、GMP実施状況や製造・品質管理体制などの確認、加えて助言を行う活動を開始。経過措置期間が終わる来年8月末まで続ける。
鮫島課長補佐は講演で、GMP実施状況の確認や助言を経過措置期間中に行う目的について、義務化が完全実施される来年9月以降、「GMP遵守が円滑に進められるようにする」ためだと説明。また、今回の確認は「届出毎ではなく、製造等施設毎に実施するもの」で「特定の製品について行うものではない」ことを伝えた。
さらに、今後の確認スケジュールの概略も提示。来年6月末までは初回の確認を行いつつ、追加の確認が必要と判断した施設に対して、再確認などを行う「フォローアップ」を実施するという。それを行う期間は、来年1月から8月末までを予定。そのほか、「調査結果を踏まえて周知等の実施」を来年1月以降に行う予定も示した。
健康被害疑い、報告義務のかかった情報わずか
一方、今年3月末まで消費者庁食品表示課保健表示室長を務め、改正機能性表示食品制度の設計などを行った、現厚生労働省食品監視安全課の今川課長は、「食品安全行政の動向~いわゆる『健康食品』のこれまでとこれから~」をテーマに講演した。制度改正の直接のきっかけとなった、小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題について、厚労省が国立医薬食品衛生研究所と連携して進めた被害原因究明調査の概要を伝えつつ、改正制度に導入した、健康被害疑い情報の収集・報告義務について解説した。
機能性表示食品をはじめとする健康食品に関する健康被害疑い情報は、原則として各地の保健所を通じて厚労省に集約。その上で、厚労省が設置した、医学者らの有識者で構成する「機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会」で、食品衛生法上の必要な措置の要否を検討する。
今川課長は講演で、小委員会におけるこれまでの検討状況について、「いまのところ措置が必要と判断されたケースはない」と説明。また、毎回の小委員会では、機能性表示食品のほか特定保健用食品、それら以外の健康食品を合わせ、健康被害疑い情報が寄せられた「数10製品」について措置の要否を検討している一方で、そのうち医師の診断があるなど、法令に基づく報告義務のかかった情報はわずか「1件か数件かゼロ件」にとどまるとし、「義務がかかっていないなかでも事業者が独自に(自発的に)報告してくれている」との所感を述べた。
厚労省は今年4月、小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題を受けて、「食品健康被害情報管理室(省令室)」を設置した。もとともあった「食中毒被害情報管理室(訓令室)」を廃止し、法令を改正して立ち上げたもので、訓令室から省令室へ組織を格上げしつつ、健康被害情報の収集体制の強化を図る目的がある。またそれに関連し、事業者がオンラインで食品自主回収報告などを行えるようにした「食品衛生申請等システム」を来年3月末までに改修し、機能表示食品の届出者らが健康被害疑い情報の報告、提供を迅速に行えるようにすることも計画している。報告などにかかる事業者の負担を軽減するほか、行政機関が迅速に、同類の健康被害情報を集計・分析できるようにする狙いだ。
健康食品の安全性確保、業界全体で取り組む
この日の講演会では他に、JAOHFAの櫻井理事が「健康食品の安全性確保に対する取り組み」と題し、「原材料安全性チェックリスト」や「体調変化・健康被害対応留意事項」など、JAOHFAら健康食品業界団体が作成した業界自主基準を巡る活動を説明。「健康食品の安全性確保のために業界全体で取り組んでいる」としつつ、原材料の品質保証など、「まだまだ改善すべき部分もあるが、行政やアカデミアとともに、お客様に信頼、利用していただける業界をめざす」とした。
また、森田代表は、「消費者から見た健康食品」と題して講演。消費者委員会食品表示部会の委員でもある森田氏は、同委員会が昨年7月、「サプリメント食品」に関する意見書を取りまとめ、「消費者保護の取組を規律する法制度や組織の明確化」などを国に求めたことを紹介した。
【石川太郎】
(冒頭の写真:講演する厚労省食品監視安全課の今川課長。25日午後、関西大学東京センター内)
関連記事
:健康被害情報、行政提供巡る留意事項 JAOHFAら業界3団体が作成・公表
:機能性の前に安全性、確認どうする? 3.11通知「自主点検」踏まえた新ツールに注目
:機能性表示食品、サプリGMP実施状況確認 「全施設対象」と消費者庁
:健康被害情報収集、課題感じる割合多く JAOHFAが事業者アンケ
:制度改正後、健康被害情報の状況は? 申し出複数あるも医療機関名を確認できず