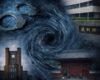動物用ウェルネスフードの基準づくり始動へ 「第2回学術集会」で産官学の連携を確認
「動物と人の予防医学研究会」(=写真:中江 大理事長)は7月25日、帝京平成大学沖永記念ホールで「動物用ウェルネスフードの確立に向けたキックオフ」をテーマに、「第2回学術集会」を開催した。午後からのシンポジウムでは「動物用ウェルネスフードの確立に関する現状と展望」と題して、ペットフードの法律上の規定やサプリメントとして用いた臨床研究などの発表が行われた。
「One Health」実現に向け、プ品質評価体制構築へ
同研究会は、人と動物の健康を「One Health」の概念で捉え、相互作用により双方のウェルビーイングを図る目的から設立された。シンポジウムの冒頭で登壇した中江氏は「現在このビジョンを実現するために、プラットフォーム事業と動物用ウェルネスフード事業の2つの主要な取り組みを準備しており、プラットフォーム事業では産官学が共同して新しいビジネスや学術的リソースの創出を支援。また、動物用ウェルネスフード事業では、動物の健康食品の品質と安全性を確保するシステムの構築を目指している」と述べた。
具体的には秋以降のできるだけ早い時期に、ホームページ上で討論ができるルームの設置や定期的な勉強会の開催を計画しており、情報発信では会員へのフィードバックも提供する。中江氏は「将来的には、動物用ウェルネスフードの規格基準や品質、有効性、安全性の評価方法に関するガイドラインの制定を目指している」とした。

法規制・機能性研究の現状と課題
農林水産省の担当官は、ペットフード安全法の概要と規制について、さらに医薬品医療機器等法(薬機法)の観点から、ペットフードと医薬品の区分について解説した。
また、早稲田大学教授の矢澤一良氏は講演で、オメガ3脂肪酸(DHAやEPA)などの機能性成分や、ペットのストレス軽減に役立つリラクゼーション成分など、既存の研究成果を活用できることを提案。日本獣医生命科学大学教授の松本浩毅氏は臨床結果を踏まえ、ペット用サプリメントの成功基準として安全性と安心感が必要とし、さらに製品だけでなく原料についても安全性の担保が求められると述べた。
その他にも、アジアにおけるペット市場の現況報告やペットの腸内フローラを測定する取り組みの紹介が行われた。
【堂上 昌幸】