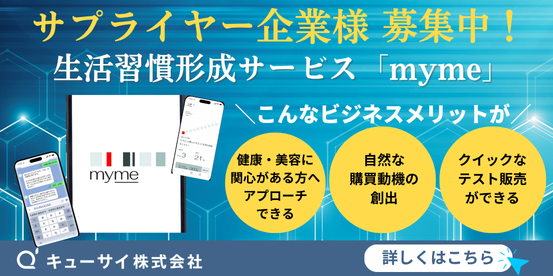日本黒酢研究会、第10回学術研究会開催 矢澤会長「黒酢の基礎・応用研究を加速させ、予防医学に寄与していきたい」
日本黒酢研究会(矢澤一良会長)は27日、「第10回学術研究会」を都内で開催し、約60人の関係者が参加した。同研究会は2014年1月24日に設立。今回、節目となる第10回学術研究会の開催となった。
今回、「黒酢で導く健康寿命~黒酢の温故知新と人生百年時代~」をテーマに掲げ、“Well-being”の視点から、発酵食品の有効性や黒酢の寿命、健康や予防医学に関わる温故知新、学術的な研究成果について講演した。
冒頭、同研究会会長で、早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構、規範科学総合研究所、ヘルスフード科学部門長の矢澤一良氏が登壇。
矢澤氏は、「Covid-19パンデミックで2年間開催を自粛したが、各界における多くのダメージはあるものの、反面教師で『予防医学』の重要さを認識できたようにも思う。これまでの11年を振り返り、今後も『食による予防医学』の視点から、黒酢の基礎、応用研究を加速することで、人々の健康を守り、疾患リスクを下げ、予防医学に寄与するために、各分野の研究者が情報を活発に交換し、討議する場を提供することを継続したいと考えている」と挨拶した。
味噌の腸内改善効果を確認
基調講演として宮城大学食産業学群教授で、NPO法人発酵文化推進機構 副理事長の金内誠氏が「奇跡の発酵食品『味噌』~LPS消去タンパク質の探索~」と題して講演した。
これまでの研究では、ある種の乳酸菌が大腸菌由来のLPS(リポ多糖)を中和(消去)することを確認し、腸内で抗炎症効果をもたらす可能性が示唆されてきた。同氏は、日常的に摂取可能でLPS中和効果を有する食品の探索が求められるとして、日本に馴染み深い味噌に着目。LPS中和効果を測定することで、腸内改善効果の評価を目ざした。
日本全国の異なるタイプの味噌20数種類のLPS中和活性を調査した結果、85%の中和活性を示す味噌が1種類、50~80%が4種類、19~50%が10種類存在した。また、LPS中和活性は、味噌中の可溶性窒素量と強い相関を示し、味噌中のペプチドまたはタンパク質が関与していると考えられる。また味噌中のLPS中和活性タンパク質は、マクロファージ細胞におけるプロスタグランジンD2の産生を抑制し、抗炎症効果も示したという。
これらの結果から同氏は「味噌はLPS中和活性を有し、『腸内環境の改善効果』を持つ新たな健康機能性食品として可能性を示すことができた」と話した。
【藤田 勇一】