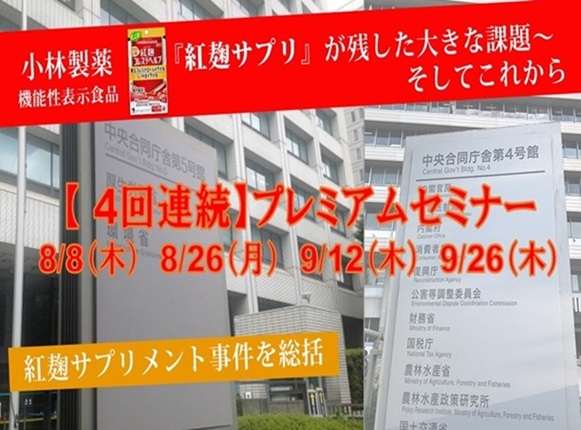急ぎ過ぎた国が見落としたもの(中) 【狂察】自己解釈と責任回避~制度不備が許した企業対応の限界
小林製薬の紅麹サプリメントによる健康被害を巡り、企業の自己解釈による報告遅延が大きな問題となった。事実検証委員会が取りまとめ、2024年7月23日に公表された調査報告書では、「因果関係が明確な場合に限る」という判断が報告基準として30回以上も使われていた。これは、あたかも「被害者の苦情を裏付けなしに取り合わない」かのような姿勢であり、企業の都合による“沈黙の論理”であった。
しかし当時、消費者庁の自見大臣は明言している。「因果関係が不明であっても、報告は速やかに行うべき」と。
「機能性表示食品は、医薬品と異なり摂取が限定されるものではないことから、万が一、健康被害が発生した際には、急速に発生が拡大するおそれが考えられる。そのため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当である」((Ⅳ)健康被害の情報収集に係る事項)、「届出者は、評価の結果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は、消費者庁食品表示企画課へ速やかに報告する」(3.消費者庁への報告)
このように、『機能性表示食品の届出等に関するガイドライン』にもこの原則は明記されており、小林製薬側の姿勢は制度に対する重大な誤解、もしくは意図的な解釈変更であった可能性が高い。
さらに深刻なのは、紅麹原料をOEM供給していた52社、そこから広がる173製品に対する報告義務が小林製薬側で果たされていなかった点である。報告の不備は7月26日に発覚した。
「報告を求めていた」とする厚労省に対して、「OEM委託先の販売会社が報告するもの」と勘違いしていた小林製薬。厚労省の再調査によって報告対象製品の存在が確認された。これも26日に報告した数字を31日になって訂正、謝罪するなど、小林製薬はちぐはぐな対応に追われ続けた。結果として、製品ロットごとの対応遅延と重なり、行政からは是正命令・回収指示が出される事態となった。
このような一連の経過を受けて、小林製薬では取締役会も関与して調査と反省を進めた。挙げられた課題は多岐にわたる――健康被害リスクへの意識の欠如、行政報告の遅延、危機管理体制の不備、社内連絡・検証能力の不足。
検証を進める会議ではある時期からは、「自由な意見が出されることを目的とする」との理由から、録画も議事録も作成されなかった。
調査報告書には今後の対策として、ガバナンス改革や品質管理体制の再構築が掲げられたが、被害者や社会からは「形式的なポーズではないか」との厳しい声も上がっている。
この問題が浮き彫りにしたのは、制度の「自己解釈可能性」である。行政による通知行政と企業の自主性を前提とした機能性表示食品制度は、責任の所在を曖昧にし、「報告をしない自由」を暗に許容してきた。とりわけ、OEM製品における情報共有の希薄さと責任のたらい回しは、健康被害の早期把握を不可能にした。
事件の根底には、情報の出し惜しみと説明責任の放棄という構造がある。こうした構造的欠陥が、実際の被害を拡大させ、制度不信を決定的なものにしたのである。
最近では、兵庫県知事を巡る第三者委員会によるパワハラ認定などの問題、フジテレビ関係者らによるセクハラ疑惑が思い浮かぶ。両事案でまとめられた調査報告書にも、共通した問題が鋭く指摘されている。意識するとしないとにかかわらず、隠蔽に向かって暴走する組織の構造が浮き彫りにされている。
しかしそこには、企業1社だけの問題では済まされない構造的な欠陥も含まれる。例えば、小林製薬と機能性表示食品制度を取り巻く関係省庁の問題。公的補償を前提とした医薬品による健康被害の救済制度と、企業が賠償責任を負う食中毒による健康被害の違い、そして“因果関係の明確性”への過度な依存は、過去の重大事件でも繰り返されてきた構造である。その象徴が1985年のJAL123便墜落事故だ。
当時の航空事故調査報告書も「圧力隔壁の修理不備」が主因であると迅速に結論づけられたが、その背景にある「政府と企業の癒着」や「証拠隠蔽の疑念」は詳細に検証されないまま棚上げにされた。
(つづく)
【田代 宏】
関連記事:急ぎ過ぎた国が見落としたもの(前)
:急ぎ過ぎた国が見落としたもの(後)
(冒頭の画像:昨年のセミナー開催時のサムネイル)