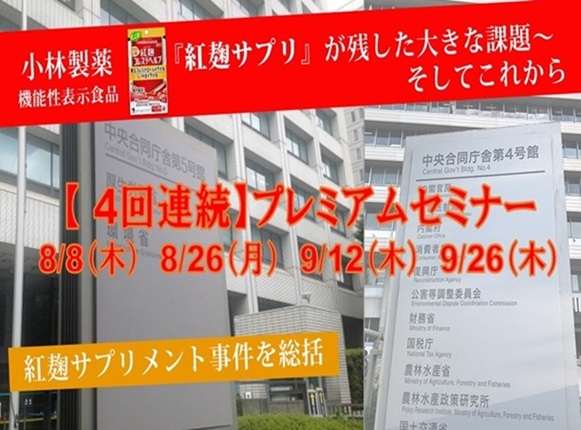急ぎ過ぎた国が見落としたもの(前) 【狂察】制度の空洞がもたらした紅麹サプリ事件
2024年3月に発覚した小林製薬の紅麹サプリメントによる健康被害事件は、同社の品質管理体制や行政との連携、さらには機能性表示食品制度そのものに大きな課題を突きつけた。2024年8月26日に実施したウェルネスニュースグループ(東京都港区)のプレミアムセミナーでは、筆者(田代)が、小林製薬の事故報告書と、御巣鷹山に墜落したJAL123便墜落事故報告書との類似性を取り上げた。
奇しくも、今年は墜落事故から数えて40周年に当たる。国会では、同事故の真相を違う視点から考察した書籍について、「自衛隊への大きな侮辱」として書籍の排斥を叫ぶ議員も現れた。2004年のイラク派兵の時に隊長を務めた、あのヒゲの隊長である。
トランプ政権の混乱ぶりを前に、世間では「オルタナブルファクト」(真実に対するもう1つの真実)という言葉をよく耳にするようになった。ディープステート(影の政府)にトランプ大統領を対比した表現である。新型コロナワクチンや中東における紛争までもが、ディープステートの陰謀という意味で、いわゆる陰謀論者が好んで使用する言葉だが、それでは「陰謀論」の対語は「もう1つの陰謀論」という表現も可能になるのではないか。何が影の政府で、何が真の陰謀論か、国内を騒がせている米騒動1つ取っても分からなくなってくる。そういうわけで、昨年8月に開催したセミナーのパートの一部を振り返りつつ、もう1つの陰謀論に対する記者の狂察に、しばしお付き合い願いたい。
2024年に発覚した小林製薬の紅麹サプリメント健康被害事件は、単なる食品事故ではなく、日本の制度的限界をあらわにした象徴的な事件である。品質管理の甘さ、事業者の初動の鈍さ、そして行政の拙速に加えて、「ガイドライン」という不透明な制度運用のほころびが重なり、多数の被害を招いた。
消費者庁は食品表示基準(府令)を、厚労省は食品衛生法施行規則(省令)をそれぞれ急改正し、法改正を経ずに制度対応を可能にしたが、その背景には、通常国会や総選挙日程への配慮があったとの見方もある。制度改革というよりは「国会審議を避けるための先回り対応」とする批判も根強い。
一方、立憲民主党は独自に法改正案を提出していた。つまり、紅麹事件は“制度の空白地帯”を行政が慌てて埋めようとした結果、より複雑な「行政・企業・立法の三重構造」の混迷を生んだのである。
こうした行政の構造的問題に加え、小林製薬の対応も大きな波紋を広げた。「誰一人取り残さない社会の実現に向けた貢献」をスローガンに掲げる同社だが、当初5人とされた死亡疑い数が、6月28日時点で76人へと急増。厚労相・武見敬三氏(当時)はこれを「極めて遺憾」とし、TVニュースで怒りを露わにした。報告遅延の要因として、「因果関係が不明な場合は報告不要」とする小林製薬側の自己判断が繰り返し報道されたようだが、これは当時においても、明らかにガイドラインの趣旨に反する。
この“自己解釈”の構造は、まさに「通知行政」ゆえの曖昧さを生んだ。行政からの通知は法的強制力を持たないため、企業は恣意的に判断できる余地があるとの解釈を生みがち。制度設計そのものが、責任の不明確化と“抜け道”の温床となっていたのである。
この構図は、40年前のJAL123便事故との共通性をも示唆する。JAL事故でも、「圧力隔壁修理ミス」に原因を絞り込み、政治的背景や構造的問題に踏み込まないまま、政府は事故の“決着”を急いだ。紅麹事件もまた、行政と企業が共に「早期収束」を志向するがあまり、真相追及と再発防止を後回しにした事例と言えるのかもしれない。
次の第2回では、企業側の組織的ガバナンスとOEM製品に関する責任の所在、報告遅延の構造にさらに深く迫る。
(つづく)
【田代 宏】
関連記事:急ぎ過ぎた国が見落としたもの(中)
:急ぎ過ぎた国が見落としたもの(後)
(冒頭の画像:昨年のセミナー開催時のサムネイル)