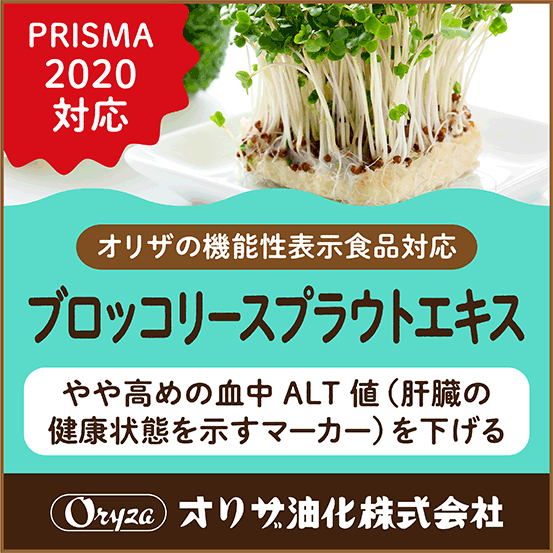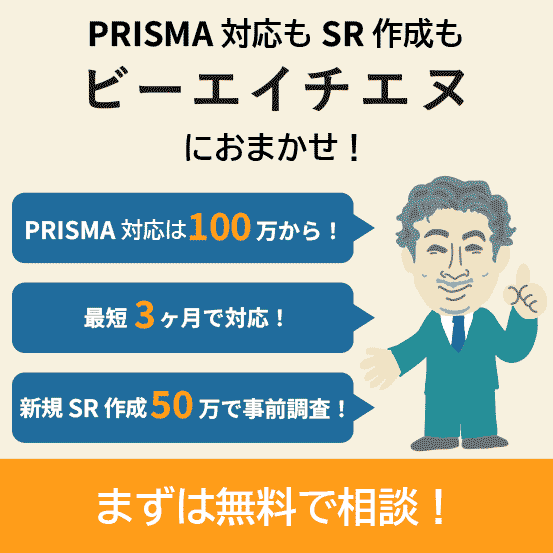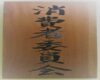急変するSNS事情、広告の落とし穴 広告の仕組みと消費者を取り巻くリスク
SNSに表示される広告は信頼できるのか? SNSが日常生活に浸透する現代、利用者の関心を引く広告がタイムライン上に頻繁に登場するようになっている。「ちょうど欲しいと思っていた商品」が表示され、思わずクリックしてしまう場面は誰しも経験があるだろう。しかしその背後には、広告技術の巧妙化とともに、消費者トラブルの種が潜んでいる。東京都はこのほど、「東京くらしWEB」でSNSに関する注意喚起を行った。
急増するSNS被害については、消費者庁も令和7年版「消費者白書」でSNSを巡る消費者問題に多くの紙幅を割いている。SNSに関係する消費生活相談件数は年々増加しており、2024年には過去最多の8万6,396件に達した。急変するSNS事情の傾向と対策を考える。
ターゲティング広告の仕組み
SNS上に表示される多くの広告は、ターゲティング広告と呼ばれる手法に基づいている。これは、利用者の年齢や性別、検索履歴、視聴履歴、「いいね」の傾向など、さまざまな行動履歴をもとに、最適な広告を自動選定して表示する仕組みだ。中心的役割を担うのは「Cookie」と呼ばれる技術で、これは利用者がWebサイトを訪れた際にブラウザへ保存される小さなデータである。Cookieを通じて収集された情報が、パーソナライズされた広告配信に活用されている。
一見すると便利なターゲティング広告だが、その裏では利用者が意図しないかたちで膨大な個人情報が収集・分析されている。位置情報、交友関係、さらにはSNS以外でスマートフォンを使った行動履歴までもが追跡対象となり、利用者のプライバシーが知らぬ間に侵害されるリスクをはらんでいる。SNSは有用な情報収集ツールであると同時に、広告業者にとっては消費者の行動を可視化する強力な装置でもある。
偽広告と詐欺まがいのリスク
SNS広告には事前審査が不十分な場合もあり、悪意ある出稿者が偽広告を巧妙に忍び込ませるケースも存在する。広告はシステムによって自動的に選定され配信されるため、虚偽の内容や詐欺的手法が混入しても一見して気付きにくい。こうした広告に騙された結果、高額請求や個人情報の流出といった被害に発展することも少なくない。
若年層に広がるSNS型トラブル
10代~20歳代の若者のSNSの平均利用時間は、2023年度において250分を超えている(全体平均200分)。比例するかのように、23年の消費生活相談では、SNS関連のトラブルは依然として高い水準で報告されている。10代後半から20代の若年層を中心に、インフルエンサーの投稿をきっかけとした誤認広告、副業や投資詐欺などの相談が目立った。中には「本当に儲かる」、「無料で簡単」といった安易な文言で誘引し、実態と異なる体験談風広告を掲載する手口も横行している。
このような状況を受け、消費者庁はインフルエンサーやアフィリエイターに対して、事業者側が表示内容の適正な管理責任を果たすよう求めている。また、消費者に対しては「情報の出所確認」や「複数情報源による真偽の確認」の重要性を強調している。
SNSを悪用した事例として、「簡単に稼げる」と称した副業勧誘が報告されている。例えば、無料のエステ体験と称してSNS投稿を促し、「1万円の報酬が得られる」と勧誘した上で、実際には高額な健康食品を購入させるという手口だ。報酬が一部しか支払われない、あるいは最初から連絡が取れなくなるケースもある。
中高年層でも相談急増、定期購入・健康食品に集中
一方、60歳代以上の高齢層でも相談の比率が拡大している。2020年時点では4万496件だった相談件数は、24年には倍以上に拡大している。
SNSが関係する相談内容の上位商品・サービスは、全年代に共通して健康食品や化粧品に関する相談が多く、特に20〜30歳代では「化粧クリーム」、「ダイエットサプリ」、「美顔器」など美容関連が多い。一方、60歳代以上では「ファンド型投資商品(全般)」が上位に見られ、悪質な投資勧誘によるトラブルが懸念される。
通信販売の「定期購入」が大きな問題に
SNSが関係する相談の中でも「通信販売の定期購入」に関する相談が顕著だ。24年は2万5,543件と前年に続き高水準を維持しており、特に50〜60歳代の相談件数が約7,000件と群を抜いて多い。
取扱商品としては、「他の健康食品」(2万4,715件)、「化粧クリーム」(1万5,277件)、「乳酸菌」(8,267件)などが上位を占め、いずれも継続購入を前提とした定期契約が多い。これらの多くはSNS広告やインフルエンサーによる紹介を通じて誘導されるケースが多く、消費者が意図せず定期契約に巻き込まれる被害が発生している。
SNS広告がトラブルの導線に
相談件数が急増している背景には、SNSを通じたターゲティング広告の巧妙化があると考えられる。利用者の属性・行動履歴に基づきパーソナライズされた広告が表示され、消費者は無意識のうちに広告を信用して契約に至る傾向がある。また、広告の審査が緩く、悪質な業者による虚偽・誇大広告も容易に出稿されており、トラブルの温床となっている。
高齢者のデジタル消費拡大がリスク要因に
60歳以上のインターネット利用率は9割近くに達しており、高齢者もSNSを通じて商品・サービスに接触する機会が増えている。これに比例して、定期購入型契約や健康食品をめぐるトラブルも高齢層で顕著に現れている。年齢層別の分析において、デジタルリテラシーが十分でない利用者が被害に遭いやすい傾向が明らかになっており、消費者教育と広告規制の両面からの対策が急務である。
電子商取引の拡大と世代を超えた影響
こうしたトラブルの背景には、SNS広告と連動する電子商取引市場の急成長がある。白書によれば、2023年の国内BtoC(企業対消費者)電子商取引市場は24兆8,435億円に達し、2014年比で約2倍に拡大した。特に食品、衣類、生活家電といった物販系分野が顕著である。また、CtoC(消費者間取引)市場も2兆4,817億円規模に成長し、個人間取引の普及が進んでいる。
インターネット利用率は全年代で上昇しており、60歳以上の中高年層でも約9割がネットを利用している。SNSやECサイトを通じた商品紹介や広告は、もはや若年層だけでなく全年代に影響を与える存在となっている。
キャッシュレス決済の普及と新手の詐欺
決済手段の多様化も、トラブルの温床となるリスクを孕んでいる。2024年にはキャッシュレス決済の比率が42.8%に達し、その内訳はクレジットカード82.9%、コード決済9.6%、電子マネー4.4%、デビットカード3.1%となっている。コード決済の普及に伴い、「逆送金」などの詐欺手口も報告されており、十分な警戒が必要である。
行政の対応と今後の課題
消費者庁はSNS広告の表示管理を巡って、景品表示法の観点から監視体制を強化するとともに、プラットフォーム事業者に対しても自主的な取り組みを促している。また、教育・啓発活動の強化を通じて、情報の受け手である消費者のリテラシー向上を図っている。
デジタル社会の進展は消費生活に多くの利便性をもたらす一方で、悪質な誘導や誤情報によるリスクも日増しに高まっている。利用者自身が情報を吟味し、冷静な判断力と慎重な行動を身に付けることが、被害防止への第一歩といえる。
【田代 宏】