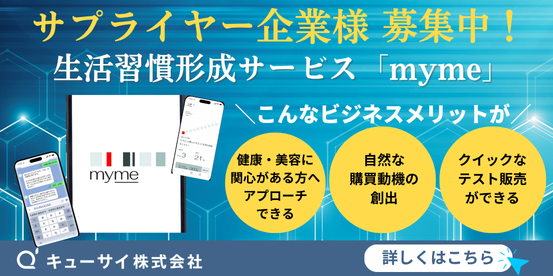個別品目表示ルール改正へ本格化 果汁飲料から旧法ルールまで年度内改正に向け議論加速
消費者庁は26日、第16回個別品目ごとの表示ルール見直し分科会を開催し、果汁飲料、ドレッシング類、豆乳類、旧食品衛生法由来ルールの4議題について集中的に議論した。
業界団体からの改正要望や文言修正の提案が相次ぎ、果汁飲料では別表規定の削除、ドレッシング類では酵母エキス追加、豆乳類では定義の明確化などが了承された。旧法由来ルールについては監視体制の実態を踏まえ、表示維持の必要性が確認された。年度内の食品表示基準改正に向け、最終案の取りまとめが進む。
果汁飲料ルールは別表規定削除へ
冒頭、消費者庁が(一社)日本果実協会からの申し出に関して、個別ルールの見直しについて説明を行った。同協会は食品表示基準における別表第4(原材料名)および別表第22(表示禁止事項)について検討を重ねた結果、関係規定を削除する方向で取りまとめたという。
この見直し決定に伴い、協会から以下の3点の要望が寄せられた。①食品表示基準の改正に関するQ&Aの早期作成、②業界向けガイドライン作成にあたる消費者庁の指導、③公正競争規約改正時の消費者庁内連携の円滑化。
消費者庁は補足として、別表第4の「その他」規定の削除方針を説明。国内柑橘の有効利用の観点から「その他」に位置付けられていた柑橘類については、「柑橘類」という表示も認める方向でQ&Aを作成し、対応していくこととした。
ドレッシング類は「酵母エキス」追加で整理
全国マヨネーズ・ドレッシング類協会からは、第12回分科会で議論されたドレッシングおよびドレッシングタイプ調味料の別表第三の定義について、改正要望が提出された。資料2に沿って、改正理由と背景を説明した。
協会側は、マヨネーズおよびサラダクリーミードレッシングの原材料として「酵母エキス」を追加する要望が示された。協会によれば、マヨネーズ類は食品表示基準別表第三により使用可能な原材料が限定列挙されており、酵母エキスは規定外であるため、使用すればマヨネーズ等の名称表示が認められない仕組みとなっている。これに対し、酵母エキスとたんぱく加水分解物は性状・用途が類似しており、実際の製造現場では同様の“うま味・コク付与”素材として広く使用されていると説明した。
たんぱく加水分解物は加水分解による製造に限定されている一方、酵母エキスは加水分解に加え熱水抽出でも製造される点が異なる。現行制度では、熱水抽出型の酵母エキスは位置付けがなく、今回の要望はその受け皿を設ける趣旨であると説明した。
さらに、別表第三の他食品では「たんぱく加水分解物」と並列で酵母エキスを認めている例が存在するため、それに準じて記載を追加するかたちで改正案を提示したとしている。
委員からの質疑の後、要望どおり酵母エキスを追加する方向で取りまとめた。
豆乳類の定義改正と旧法由来表示の最終整理
続いて、日本豆乳協会が、豆乳類に関する別表第三の定義見直しについて報告を行った。同協会は、前回議論時は検討中としていた項目を今回取りまとめ、提案として提示した。
まず、豆乳の定義における「乳状の飲料」を「乳状の液体」に変更する共通改正案が示された。豆乳が飲用だけでなく加工原料として利用される場面が増えているため、より実態に即した表現に改めようというもの。
次に、調整豆乳の定義について、従来の文言が「油脂添加が必須」と誤解されかねない点を修正するため、「および」を「又は」に改め、調味料と油脂の順序を変更する案が示された。また、「風味に影響を及ぼさない原材料」の使用を認める旨を追記し、「調製豆乳液」を調製脱脂大豆豆乳液との整合性をとるため、「調製大豆豆乳液」に変更した。
さらに、近年普及が進む粉末豆乳の扱いに言及し、現行では粉末大豆たんぱくに一括されているが、豆乳粉末と大豆粉末では風味・用途が異なるため、「大豆豆乳粉末」と「大豆たんぱく粉末」に区分することを提案した。これに伴い、別表十九および別表二十の文言変更も併せて求めた。
豆乳飲料については、無調整の大豆豆乳液にコーヒーや紅茶等の風味原料を加える場合でも豆乳飲料と認めるべきとの提案が行われ、これを反映した定義改正が示された。また、粉末豆乳から豆乳飲料を製造する道を開く規定整備も併せて求められた。
これらの要望に対して異論はなく、要望どおりの方向性で取りまとめた。
旧食品衛生法由来ルールの見直し議論が最終局面に
旧食品衛生法に由来する個別品目ごとの表示ルールについて、前回からの続きとして議論が行われた。特に分類4に位置づけられる「監視の観点から維持が望ましい事項」について、厚生労働省および東京都の担当課長から監視指導の実態が詳述され、その必要性が確認された。
冒頭、消費者庁による資料4に基づく説明が行われた。説明に入る前に同庁は、前回の分科会で「クリームの乳脂肪分」の表示について規約にあるとした点について、正しくは「ガイドラインにある」と訂正した。
消費者庁は、前回指摘された「わかりにくい表示」への対応として、食肉製品および冷凍食品に関する表示例を再度整理し、食品衛生法上の規格基準との1対1対応が本来の目的である点を強調した。
食肉製品では、乾燥食肉製品、特定加熱食肉製品、加熱食肉製品における「である旨の表示」や、「包装後加熱」か「加熱後包装」かを示す規定について説明した。消費者からの問い合わせはほとんどなかったという。
一方、冷凍食品については事業者アンケートにおいて、消費者から一定程度の問い合わせがあるとした。現行の表示では、表示例に示されているように、「凍結前加熱の有無(加熱してあります)」と「加熱調理の必要性(加熱して召し上がってください)」が並んで記載されている。前者は凍結直前に加熱しているかどうかを示し、食品衛生法上の規格基準のどこに該当するかを示す技術的な表示。一方、後者は実際に飲食する際に加熱が必要かどうかを示すものであり、両者は目的が異なる。
しかし、同じ「加熱」という語句を用いながら異なる趣旨の情報が上下に並ぶことにより、「加熱してあるのに、なぜ加熱して食べる必要があるのか」という誤解が生じやすい。
このため消費者庁は、次長通知に補記を行い、表示の整理を図る方針である。具体的には、「凍結前加熱の有無」を冷凍食品の名称の後方に外枠で示し、摂食時の加熱方法とは明確に区別して記載する方向性を示した。これにより、技術的情報と摂食方法が混在する現行表示の課題を一定程度解消できると考えている。
続いて厚生労働省が、食品衛生法に基づく全国的な監視体制とその状況について説明した。輸入食品を扱う検疫所32カ所、国内監視を担う157自治体、462保健所が役割を分担し、年間約10万件の収去・買上げ検査を実施しており、不良検体は毎年度400〜500件程度、その中には規格基準違反や腐敗・異物混入などが含まれると説明した。
東京都は、流通末端での収去検査が都の監視業務であるとし、製品の分類(食肉製品の区分、冷凍食品の凍結前加熱の有無など)が検査項目決定に不可欠であると説明。表示がなければ検査の前提が成立しないとし、表示維持の必要性を強調した。
消費者庁は、令和7年度内の食品表示基準改正に向けたスケジュール案を整理した。今年1月~11月にかけて、個別品目ごとの表示ルール見直し分科会が集中的に開催。同12月19日には、分科会で議論し取りまとめられた改正内容案「個別品目表示ルール(旧JAS法由来)の見直し」、「個別品目表示ルール(旧食品衛生法由来)の見直し」、「その他の改正事項」を食品表示懇談会に報告する。
懇談会は、準備が整い次第、食品表示基準改正案についてパブリックコメントを実施し、年度内に消費者委員会(食品表示部会)に諮問する。
消費者委員会での最終了承後、食品表示基準の改正告示が行われるが、2030年3月31日まで の経過措置が設けられている。
【田代 宏】
配布資料はこちら(消費者庁HPより)