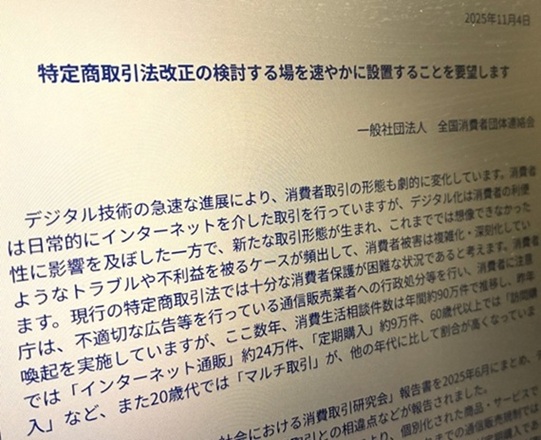脆弱性包摂へ、特商法を立て直せ! 全国消団連が意見書、デジタル時代の消費者保護を問う
(一社)全国消費者団体連絡会(全国消団連、東京都千代田区、郷野智砂子事務局長)は11月4日、「特定商取引法改正の検討する場を速やかに設置することを要望します」と題する意見書を消費者庁および消費者委員会、国民生活センターに提出した。
同団体はすでに2023年6月、「特定商取引法の速やかな抜本的改正を求めます」とする意見書を提出しているが、このたび、近年相次いで公表された2つの報告書、消費者庁による「デジタル社会における消費取引研究会報告書」(2025年6月)と内閣府消費者委員会による「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会報告書」(2025年7月)の内容を踏まえ、再度、立法府と行政に具体的な行動を促すこととなった。
2つの報告書が示した制度転換の潮流
全国消団連は意見書の中で、デジタル技術の急速な進展により消費者取引の形態が劇的に変化し、新たなトラブルや不利益が頻発していると指摘する。通信販売、定期購入、訪問販売、マルチ取引など、相談件数は年間約90万件に達し、被害は高齢者から若年層まで広範に及ぶ。とりわけ、ネット通販や定期購入における「ダークパターン」的手法、SNSを媒介とした詐欺的投資取引、高齢者宅を狙った高額リフォーム勧誘など、被害の構造は複雑化・深刻化している。
意見書は、こうした現状に対し「現行の特定商取引法では十分な消費者保護が困難な状況である」として、悪質事業者の排除を可能にする法整備を急ぐべきだと訴えている。
この訴えは、単なる消費者団体の要望にとどまらない。背後には、2つの報告書が示した大きな制度的転換の潮流がある。
両報告書の論点と意見書の主張とを照合しながら、特商法改正の意義と方向性を探る。
まず消費者庁「デジタル社会における消費取引研究会」報告書は、デジタル化がもたらす構造転換を前提に、「消費者が納得感を持って取引に参加できる市場の形成」が必要だと明示した。同報告書は、加速的に変貌するデジタル取引について「上書きの歴史を重ねる取引ツール」と表現し、インターネットやSNSを介した新たな取引の拡大により、もはや従来の通信販売規制では対応できない現実を指摘する。
デジタル取引がもたらす「脆弱性の普遍化」
報告書によれば、AIや個人データの活用によるパーソナライズド・マーケティングが増加したことにより、取引の主体は曖昧化し、消費者自身が販売者にもなり得る構造にある。情報や時間、関心、アテンションの経済的価値化による個人情報そのものの価値の増大と、その分析を通じたターゲティング広告やレコメンデーションなどの手法を用いた消費取引の手法が発達した結果、情報の出し手、受け手と販売事業者のみならず、情報の取得、管理、流通、処理、提供を担う者が複層的に、系統立たずに関与する構造となっている。「サイバー空間」、「フィルターバブル」、「エコーチェンバー」などが介在することで、適正な情報の選択が妨げられ、自立性・自律性が損なわれている。
このような取引環境では、情報の非対称性に基づく従来型の保護論理だけでは限界がある。
報告書は、「脆弱性が普遍化した社会」を前提に、行政対応の迅速化、国際的連携、PIO-NET情報の活用などを求めている。
現行法では追いつかない詐欺的取引の実態
全国消団連の意見書は、この報告書が示した問題認識を具体的事例とともに裏付けている。
すなわち、定期購入における「注文した覚えがない」、「解約できない」といった被害の多発、SNSを起点とした投資詐欺などの新たな類型、そしてダークパターンによる心理的誘導。こうした実態は、研究会報告書のいう「個別化された商品・サービスの販売手法」による情報操作・行動誘発の典型である。
意見書は、行政処分や注意喚起だけでは不十分であり、法的枠組みそのものの見直しが必要であると明言する点で、報告書の問題提起を政策要求へと具体化したものといえる。
理念転換の鍵「関係的自律」という新しい視点
一方、消費者委員会の「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会」報告書は、消費者法制度全体の理念的基礎を問い直すものとなっている。そこでは、従来の「強い個人による自由な意思決定」モデルを離れ、全ての人が多様な脆弱性を抱える存在であることを前提とした制度設計への根本的転換が提起された。
報告書は、脆弱性を①年齢や経済状況などによる「類型的・属性的脆弱性」、②認知バイアスや情報処理の限界に起因する「限定合理性による脆弱性」、③環境や関係性によって一時的に生じる「状況的脆弱性」――の3パターンに分類している。この3類型はいずれも、現代社会において誰もが経験し得るものである。従って、「消費者の脆弱性」に対応する制度を設計する際は、どのような脆弱性に対する制度なのかを明確にし、その要件・救済手段・効果を具体的に定めることで、制度の目的と期待される行動が理解されやすくなる。制度ごとに必要な範囲で脆弱性を具体化すればよく、消費者法全体で脆弱性を網羅的に定義する必要はない、という考え方を示している。
この認識は、全国消団連の意見書に通底する。
意見書は、消費者教育やリテラシー向上だけでは被害を防げないと断言し、「悪質な事業者を排除できる社会構築のための法整備」を求める。これは、自己責任論を超えて、社会全体で脆弱性を支える構造を整えるべきだという報告書の理念に通底する考え方である。
また、報告書が提唱する「他者との適切な関係性の中で、自らの価値観に基づく『自分自身の選択』であると納得できるような『自律』的(autonomous)な決定が可能となること(関係的自律)」は、意見書が強調する「納得感を持って取引に参加できる市場」への要請と方向を同じくする。つまり、2つの報告書が示した思想的転換を、全国消団連は特商法改正という具体的立法課題として位置付けているのではないか。
半世紀前の法体系では捉え切れない現実
1976年に制定された特定商取引法は、通信販売や訪問販売などを想定した枠組みである。当時の通信販売は郵便や電話注文を念頭に置いており、現代のAI主導型マーケティングやSNS広告を射程に収めることは想定されていなかった。研究会報告書も指摘するように、現行法は「販売者と購入者」という2者関係を前提に設計されており、多層的・分散的な取引主体を持つデジタル市場では機能不全に陥りつつある。
全国消団連は、詐欺的定期通販による購入トラブルを例に挙げ、「現行法では十分な保護が困難」と述べる。特に「解約しようにも事業者と連絡が取れないなど、いわゆるダークパターン」と呼ばれる手法は、従来の「勧誘行為の明示性」、「契約書面の交付」といった概念では評価し切れない。
これに対し、専門調査会報告書が提唱する「金銭の支払に限られない消費者取引の拡大(情報、時間、アテンションの提供)への対応」という視点は、これらの新しい搾取形態を捉える理論的基盤を与える。同意の形式ではなく実質的理解・選択の自由を重視する枠組みは、まさに定期購入型被害に対応するものだ。
「攻めの消費者保護」への転換
さらに、研究会報告書が強調する「信用・信頼性の高い情報がやり取りされる基盤」(トラスト基盤)の構築も、全国消団連の要請に通じるものである。同報告書は、制度的規制だけでなく、消費者が安心して意思決定できる環境整備として、情報の開示、不当な介入・操作の排除など信頼回復の仕組みを提起することで、「国際的にも透明性ある市場としての評価を高め、結果として我が国の国際競争力の向上にも寄与する」としている。
意見書が求める「悪質事業者の排除」とは、この信頼基盤の確立を実効的に担保する法的支柱の整備にほかならないだろう。
全国消団連の意見書は、統計や事例を通じて現場のリアリティを明確にしている。年間約90万件の消費生活相談のうち、インターネット通販が約24万件、定期購入が約9万件に上る。これらは一過性のトラブルではなく、制度的限界の表れである。
特に高齢者層を狙った訪問購入やリフォーム契約、若年層に多いマルチ取引など、被害の分布も多様化している。報告書が示す「誰もが脆弱になり得る社会」の実証的裏付けがここにある。
また、消団連は、行政処分や注意喚起といった事後対応に依存する現行体制の限界を批判する。
PIO-NETによる情報共有が進んでも、被害発生後の救済には時間と労力がかかる。消費者被害を「未然に防ぐ法制度」こそが必要であるという主張は、研究会報告書が掲げた「攻めの消費者保護」と軌を一にする。両者をつなぐ言葉が「実効性」である。制度の存在だけでなく、運用が消費者にとって現実的救済となる仕組みこそ問われている。
「共創型ガバナンス」への挑戦
専門調査会報告書は、今後の制度設計においてハードローとソフトローを組み合わせた「ベストミックス」を提唱した。
ハードロー的手法・ソフトロー的手法、民事・行政・刑事法規定、インセンティブ設計、技術の活用等の種々の規律手法を念頭に、それぞれの特徴を踏まえながら各手段を相互補完的に運用し、事業者団体・消費者団体・行政が協働して秩序を形成するという、いわば「共創型ガバナンス」である。この構想は、全国消団連が実践してきた消費者ネットワークの延長線上に位置付けられるのではないか。
同団体は、行政と市民の間を媒介する「社会的仲裁者」として、制度の現実適合性を担保する役割を果たしてきた。
同報告書が重視する「市場を健全化させる能動的主体としての消費者教育」も、同団体の理念と重なる。消費者教育を「自己防衛の手段」にとどめず、市場の公正性を支える社会的行為として再定義すること。そのための制度設計こそ、デジタル時代の消費者法の根幹であると報告書は示唆する。意見書の要望――「検討の場を速やかに設置せよ」――は、この共創の第一歩を促す具体的なアクションといえる。
全国消団連の意見書は、単なる法改正要求ではなく、デジタル社会における「信頼の再構築」を求める声である。研究会報告書が描くのは「納得感を持って取引に参加できる市場」、専門調査会報告書が目指すのは「脆弱性を包摂する法体系」、そして意見書が訴えるのは「悪質事業者を排除し、安心して暮らせる社会」であり、3者はいずれも、異なる立場から共通の方向性”包摂的で信頼できる市場の形成”を指し示している。
【田代 宏】
意見書はこちら(全国消団連HPより)
2件の報告書は以下のとおり
:デジタル社会における消費取引研究会
:消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会