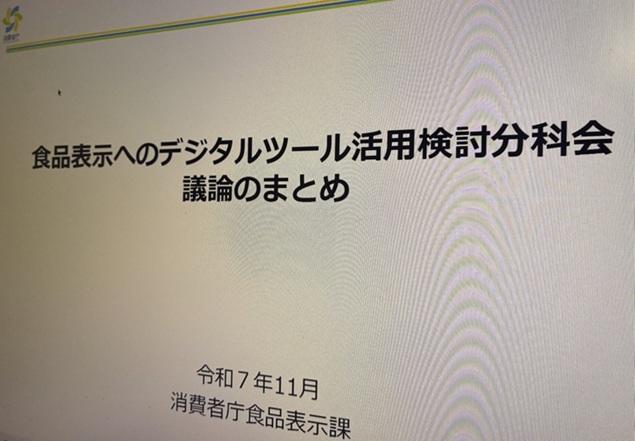食品表示デジタル化、最終審議まとまる 論点取りまとめ食品表示懇談会へ報告
消費者庁は14日、「第7回食品表示へのデジタルツール活用検討分科会」を開催し、制度化に向けた最終的な論点整理を取りまとめた。これまでのヒアリングや技術的課題の議論を総括し、1対1対応の方式、データ管理方法、広告表示の扱い、修正履歴の確保など主要論点が提示された。今後は食品表示懇談会での報告を経て、消費者庁がガイドライン策定や実証の検討を進める方針。制度設計は来年度以降、実証段階へと移行する。
デジタル化の利点と負担、1対1対応方式を検討
同庁は、参考資料1「食品表示へのデジタルツール活用検討分科会 議論のまとめ」に基づき、検討の経過について説明した。第1回で現状整理と海外動向および実証調査の課題を共有し、第2回から第4回で事業者ヒアリング、第5回および第6回で技術的課題の集中的議論を行い、今回の取りまとめに至ったと報告した。
技術的課題の整理として、まず制度運用のメリット・デメリットについて説明した。デジタル化は見やすさの向上や包材制約の緩和といった利点がある一方、消費者にはスマートフォン操作の負担、事業者にはデータ管理のコストが生じるとした。制度は任意導入を前提とし、対応可能な事業者から開始する設計が適切とした。
データ管理方式については、一元管理は仕組みが単純だが国による維持管理は現実的でなく、分散管理は事業者の体制整備が必要なものの運用面で適していると説明した。アクセスツールにはスマートフォンが前提となり、二次元コードの活用が最適と整理した。JANコードは必要情報を保持できないため、採用が困難とした。
1対1対応の方法としては、商品と情報が確実に結び付くことが不可欠で、直接表示と選択画面を経由する方式のいずれも許容し、ロット番号を手入力する方式は負担が大きいとの指摘があったため、採用は現実的でないとした。技術仕様については、URL形式など一定の統一ルールが必要だと説明した。
保管データの範囲については、義務表示に限らず任意表示や利便情報なども保管可能とする方向だが、具体的項目は今後検討するとした。
広告の扱いについては、全面禁止ではないものの、義務的食品情報より先に広告が表示されないこと、食品情報より広告が目立たないことなど、コーデックスの整理を踏まえたルール設定が求められるとした。
修正履歴については、デジタル表示は修正が容易で誤表示を痕跡なく改変できる懸念があるため、修正履歴の保管を制度的に求めること、流通期間を通じ行政が確認可能であることを条件とする必要があると説明した。
来年度以降の進め方としては、取りまとめは食品表示懇談会に報告される見込みであり、分科会としての技術的議論は一区切りとなる。今後は、消費者庁が1対1対応の具体方式、データ範囲、広告の扱いなど詳細ガイドラインの作成を進め、制度化に向けた検討を継続するとされた。
取りまとめ案を巡り自由討議、修正点を確認
第7回食品表示へのデジタルツール活用検討分科会では、事務局説明に続き、取りまとめ案に対する自由討議と総括が行われた。
議論は主として取りまとめ本文の修正点確認、第3章の今後の進め方、ガイドラインや標準化の論点整理、容器包装上に残すべき情報の線引き、委員発言の扱い確認、最終的な修正方法と今後のスケジュール、そして各委員・事務局による総括に及んだ。
まず、取りまとめ案のうち「1 はじめに」、「2 食品表示へのデジタルツール活用検討分科会における議論の結果」について、加藤座長が意見を求めた。
早川敏幸委員(日本生協連)は、表記誤字および5ページ26行目の「一元管理と異なり」という部分について、「JANコードと異なり」とすべきとの表現修正を指摘した。消費者庁は誤記を認め、早川委員の提案を採用する方向を示し、座長は修正を前提として当該箇所を了承した。
続いて第3章「令和8年度以降の食品表示へのデジタルツール活用検討の進め方について」(10P)に関して、早川委員は11P5行目に「消費者庁において検証した上で」との記載があるが、実証実験などの予定があるか聞いた。
これに対し消費者庁は、詳細なガイドラインを策定した上で検証方法を検討する考えを示し、制度をいきなり本格運用するのではなく、消費者の声を聞いた上で、段階的な展開を想定していると説明した。
また、現行法制上、既存の容器表示を除いた状態での実証を行うと違反となる。どういう実証方法が適切かを考えながら、来年度の早い時期に着手する予定と述べた。
小川美香子委員(東京海洋大学)からは、今後の制度設計に関わる3点が提起された。第1に「BtoBデータはそもそも消費者向け開示を前提としていないため、どの項目を開示対象とするか慎重な検討が必要である」、第2に「開示情報が問題を生じた場合の事業者リスクの整理が必要である」、第3に「消費者が実際にデジタル情報を利用しなければ制度の意味がないため、啓発・広報が重要」とし、これら3点を書き加えてほしいとした。
これに対し、消費者庁の説明を受けた加藤孝治座長(日本大学大学院)は、「デジタル表示の実装に向けた“保管データの範囲”について、分科会では情報を幅広く格納できる仕組みを整えることに重点を置き、どの情報を実際に表示として出すかという整理は扱わない方針で議論してきた」とし、「表示内容の選別は常用な課題として食品表示懇談会で検討すべきところ、分科会としてはその前段となる器づくりを行おうということで取りまとめている」と説明。食品表示に関する啓発に関しては、「デジタル化に限らず重要な課題。制度が大きく変わる時期こそ従来以上に取り組む必要がある」と述べ、取りまとめを懇談会へ報告する際には、この点も併せて伝えたいとの考えを示した。
ガイドラインと標準化に向けた実務課題を協議
ガイドライン策定と標準化の論点では、小野和彦委員(ハウス食品)が、店頭で消費者が実際に二次元コードをかざすのかという実用面の課題と、デジタル化の第一歩としてガイドラインが極めて重要であることを指摘した。
加藤座長は、実用可能性の検証が非常に重要であり、データ形式の標準化、例えば全角・半角の扱いなどの統一が不可欠であると述べた。消費者庁も、消費者の利用状況や使い勝手を踏まえた制度設計を行う姿勢を示した。
容器包装上にどこまで情報を残すかという線引きについては、消費者が二次元コードをかざさないことによって不利益が生じるような情報はデジタル化すべきではなく、より深い情報や詳細情報をデジタルで取得できる構造とするべきだという基本的な方向性が共有された。
委員から期待と不安の声、デジタル化の課題も浮上
総括コメントでは、各委員からデジタル化への期待と課題認識が相次いだ。
小川委員は、デジタル化は消費者が負担なく情報を活用できる社会への一歩。制度整備に向けて努力を続けてきた事業者の取り組みに感謝するとした。
小野委員は、BtoBデータの多様性や事業者の負担がある一方で、デジタル化が統合・標準化を進める契機となってほしいと述べた。
金田建一委員(生活品質科研)は、多様化する消費者ニーズに正確に応えることが重要であり、小規模事業者のサポートも必要であるとの見解を示した。
工藤操委員(消費科学センター)は、デジタル化の進展に期待を表明し、利用されてこそ制度に意味があると強調した。
河野浩委員(食品産業センター)は、項目が未確定でシステム要件も不明な点が多く、事業者側には不安が残るとし、実証を通じた課題抽出が重要であると述べた。
早川委員は、「参考資料1」の8ページの中にメリット・デメリットを示す表を追加すべきであると指摘した。また、生協はその性格上、消費者団体と事業者の両側面を持ち合わせている。組合員からは容器表示の維持を求める声、またデジタル化を歓迎する声などさまざまな声が出る可能性が高い。今後、ガイドラインや実証事業を検証しより良い制度にしてほしい。また、PB商品における表示責任のあり方について課題を示した。
平賀早織委員(国分グループ本社)は、事業者として、また消費者として今後も継続的に動向を注視すると述べた。
南田聡美委員(セブン-イレブン・ジャパン)は、食品表示への関心の高低を踏まえると、実証や周知が重要であり、社外データ連携には負担が大きいことから、ハードルの軽減を望む意向を示した。
情報非対称性の解消と標準化の必要性を強調
座長総括としては、情報の非対称性を解消する流れは大きな社会潮流であり、食品表示のデジタル化はその一環として必然であるとした。その上で、多様な情報ニーズに対応するためには、リアル表示とデジタル表示を組み合わせることが不可欠だと述べた。
また、事業者の立場から見たデジタル化の意義について、標準化や共同化により社会的コストを下げる流れが広がっていると指摘した上で、分科会でも、経済産業省から物流分野でJANコードの見直しが進められていることが報告され、現状ではデータのプロトコルが統一されていないため無駄なコストが生じていると説明があった。こうした課題を踏まえ、「今回の検討はガイドライン整備や標準化を進める好機だった」との認識を示した。
また、「デジタル化には消費者目線と事業者目線の双方に意義があり、その両面を踏まえて議論を重ねてきた。その成果を食品表示懇談会を通じて適切に発信していきたい」とし、引き続き協力を求めた。
今後、12月19日に開催する食品表示懇談会で「取りまとめ」を報告し、修正案は委員にメールで確認する。
【田代 宏】
資料はこちら(消費者庁HPより)