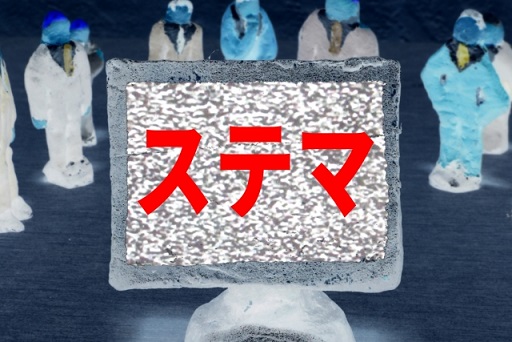ステマ規制2年、確約手続が新局面に 措置命令6件・確約3件、企業は是正体制の整備急務
2023年(令和5年)10月1日に、景品表示法第5条第3号に基づく「ステルスマーケティング(ステマ)告示」の施行によってステマ規制が導入されてから、今月で2年が経過した。当局による措置命令も相当数が蓄積し、どのような表示が措置の対象となりやすいか、その傾向が把握できる段階に入っている。さらに24年10月1日には、23年改正景品表示法によって新設された確約手続が導入され、ステマ規制違反の疑いに関しても複数の確約計画が当局によって認定・公表されている。
制度施行2年、執行状況を整理
のぞみ総合法律事務所(東京都千代田区)の山田瞳弁護士は、同事務所のニュースレターにおいて、制度施行から2年を経たステマ規制の執行状況を整理し、消費者庁および地方自治体による措置の特徴を分析している。その内容を紹介する。
山田弁護士はこうした執行状況を踏まえ、ステマ規制違反として措置命令の対象となった表示や、違反疑いに係る確約計画の認定条件の傾向を正しく把握することが、企業にとって予防措置の実施や、調査を受けた際の手続・対応を適切に講じるために不可欠であると述べている。
確約手続が新たに導入 事業者に第三の選択肢
景品表示法では、ステマ規制違反に対して、従来から①行政指導と、行政処分としての②措置命令が予定されており、いずれも国(消費者庁長官)と都道府県(知事)が主体である。なお、課徴金納付命令はステマ規制違反には適用されない。
これに加えて、23年改正法により、24年10月1日から新たに③確約手続が導入された。不当表示の疑いがある事業者が、自ら是正措置計画(確約計画)を作成・申請し、消費者庁の認定を受けた場合には、その行為について措置命令などの行政処分の適用を受けない。ステマ規制違反の疑いに関する表示もこの対象に含まれており、確約手続の通知および認定の主体はいずれも国(消費者庁長官)である。
措置命令6件・確約3件 2類型が中心
23年10月1日の規制開始から現在までに公表されている、ステマ規制違反に対する各措置の件数は、措置命令の対象となった6件および確約手続の対象となった3件の計9件で、これら9事案で問題とされた表示内容は、大きく2つの類型に分類される。
1つ(類型Ⅰ)は、Googleマップなどのプラットフォーム上で、第三者(または従業員)に高評価の口コミ投稿をさせる類型。次(類型Ⅱ)は、自社や商品公式サイトの感想・体験談欄に、第三者がSNS上で投稿した使用感などを抜粋して掲載する類型である。これらの事案では、いずれも事業者から第三者に対価提供や無償提供を条件とした投稿依頼がなされていたと認定されている。
調査容易な表示が中心 今後は拡大も
この2つの類型のみが措置の対象となってきた理由について、当局から明示的な見解は示されていないが、山田弁護士は、当局の調査限界が一因と考えられると述べる。
すなわち、景品表示法上のステマとは、本来事業者が行っている表示であるにもかかわらず、消費者にはそれが事業者によるものと判別しにくいものを指す。そのため、当局にとっても表示の外見だけから事業者の関与を把握することは困難であり、ステマ疑いの端緒を得るのが難しい。
ただし、類型Ⅰは短期間に不自然な数の高評価口コミが集中するなどの特徴があり、また類型Ⅱは、公式サイト上の「お客様の声」欄に第三者のSNS投稿が転載されているのに「PR」や「広告」表示がない場合など、外見から広告主の関与を推知できることが多い。このため、当局が比較的容易に調査対象を特定しやすい類型として、これらが措置の中心になっていると考えられる。
山田弁護士は、今後も類型ⅠおよびⅡに該当する表示は厳格に取り締まられるとみられるため、現在実施している同様の表示は速やかに取り下げ、再発を防止する措置を徹底する必要があると指摘する。
また、当局による措置がこの二類型に限定されているのは、あくまで調査限界によるものと考えられる。今後の調査体制の進展次第では、これ以外のステマ表示に対しても措置が及ぶ可能性があるため、ステマ規制運用基準に示された表示類型については、該当しないよう十分な注意が求められる。
制度改正で「自主是正」ルートが確立
改正前の景表法では、ステマ規制違反を含む不当表示の疑いで調査を受けた場合、事業者に選択肢はほとんどなく、措置命令を受け入れるか、行政指導への軽減を求めるしかなかった。
しかし、23年改正により、令和6年10月1日からは確約手続という第三の選択肢が加わった。これにより、ステマ規制違反疑いに対しても、事業者自ら是正措置計画を作成・申請し、認定を受けることで行政処分を回避できるようになった。
なお、確約計画の認定条件をめぐっては、「消費者への返金措置を盛り込まなければ認定されないのではないか」との懸念があった。しかし、ニュースレターの【表3】で示されている認定事例を見ると、優良・有利誤認表示疑いでは返金措置が含まれている一方、ステマ規制違反疑いの確約計画では返金措置がなくても認定されている。このため、ステマ規制違反疑いに関しては、返金措置を認定の必要条件としていないというのが消費者庁の考え方とみられる。
早期の確約申請が有効な防御策に
以上を踏まえ、山田弁護士は、現行法下では、ステマ規制違反疑いの調査が開始された場合、ステマ該当性を争えないと判断した段階で、早期に確約手続の適用を希望する旨を申し出ることも有効な選択肢になり得ると述べている。
ステマ規制の施行から2年を経て、措置命令と確約手続の事例が並行して現れるようになった。
現時点で当局が重視しているのは、事業者が広告主であることを隠して第三者を装う表示であり、その中でも調査可能性の高い表示形態が中心となっている。
一方で、制度改正により、違反疑いに対する対応の幅が広がり、事業者が自主的に是正措置を講じるルートが確立されたことも大きな変化である。
山田弁護士は、企業にとって重要なのは、過去の措置事例や確約計画の傾向を正しく把握し、適法な広告表示と迅速な是正対応の体制を整備することであると結んでいる。
【田代 宏】
出典:山田瞳弁護士「施行から2年・景表法ステマ規制の執行動向~措置の対象となる表示類型から確約手続まで~」(のぞみ総合法律事務所ニュースレター、2025年10月16日)