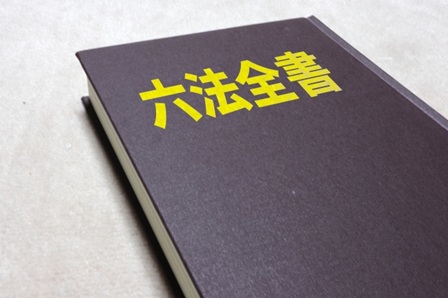ワクチン訴訟「第5回期日」後分析 対立構図鮮明に、書証分析で見える法廷戦略
Meiji Seikaファルマ㈱(東京都中央区、永里敏秋社長)が衆議院議員・原口一博氏を名誉毀損で提訴した裁判は、10月14日の第5回弁論準備手続で新たな局面を迎えた。原告側の主張は「発言の違法性」に焦点を絞り、次回から損害論の審理へ進む見通しとなった。本稿では、裁判所に提出された原告と被告双方の「書証」の数に注目し、その戦略を分析する。
書証の圧倒的分量、原告が立証構造を形成
本件訴訟の特徴の1つは、原告側の書証が圧倒的に多い点だ。閲覧記録によれば、原告が提出した甲号証は「第1号~第48号の12」、被告側は乙号証(第1号~9号証の4)となっている(10月14日現在)。我が国の民事訴訟では、原告側の証拠は「甲」、被告側の証拠は「乙」で示す決まりとなっている。
原告(Meiji Seikaファルマ側)の書証内容は、コーポレートプロフィールをはじめ、医薬品医療機器総合機構(PMDA)における審査報告書、被告による各メディア発言の記録、そして日本感染症学会・日本呼吸器学会・日本ワクチン学会によるワクチン定期接種の見解などである。
これらは、単に個別の事実を裏付ける証拠ではなく、自社の行為が行政・学術の正統な手続に基づくものであることを体系的に立証する構造を示している。
すなわち、原告は「科学的・制度的正当性」という外部的権威を積み上げることで、自らの企業活動を社会的に擁護し、被告の発言を“根拠なき攻撃”として位置付けようとする戦略を採っているともみられる。
第5回弁論手続で提出された「第3準備書面」でも、原告は「被告が主張する論評の前提事実の真実性・真実相当性は争点にすべきでない」と明言した。つまり、原告は“事実の真偽”ではなく、“発言の違法性”に焦点を絞り、言葉そのものの影響力と社会的評価の低下に訴訟の軸を移しているかに見える。
被告は「政治的論評」として防御構成
一方、被告である原口議員の提出書証は少数ながら、内容面での方向性は一貫している。提出された9点の書証には、薬事審議会審議参加規程や感染症・予防接種審査分科会の審議結果などの行政資料、川田龍平議員による国会質問主意書、そして村上康文氏の「mRNAワクチンの健康に対するリスク」論文などで構成されている。
これらはいずれも、制度批判・政策論争の文脈を維持し、補強する性格をもつ。被告側は、これらの資料を通じて「発言は特定企業を攻撃するものではなく、ワクチン行政や承認制度のあり方に対する政治的論評である」と主張しており、論点を「表現の自由」、「公益目的」、「公正な論評の法理」の枠内に位置付けようとしている。
つまり、被告は個々の事実関係の真偽ではなく、「政治的言論の自由」によって違法性が阻却されるという構成を採用している。原告が科学的正当性を積み上げるのに対し、被告は制度的問題提起を基盤に据えるという対照的な構図が浮き彫りとなっている。
立証戦略の対立 科学と政治の応酬
ここで「書証」の数に注目してみよう。「書証」とは、裁判所に提出された主張の根拠(証拠)である。
既述のとおり、10月14日現在において、原告側の書証は「甲1~48号証」の48点であるのに対し、被告側の書証は「乙1~乙9号証」の9点。比率で表すと、原告側の書証の数が被告側を5倍以上上回っている。
原告が証拠の積み重ねによって「行政・学術・法令に基づいた企業行動の正当性」を立証し、発言の非合理性と悪質性を浮かび上がらせようとしているのに対して、被告は制度の構造的問題を根拠に「公共の利害に関する論評」として発言の正当性を主張し、違法性の阻却を狙っている。
それでは、5倍以上の分量を誇る原告の主張の方が有利に働くのだろうか――。
書証は主張を裏付けるための資料である。裁判は、「立証」ができたかどうかによって動いていくが、「立証」は、十中八九、真実であるらしいという程度の資料の裏付けがある状況で認められる。
専門家の評価はこうだ。
「“名誉棄損”とは“社会的評価の低下”なので、社会的評価に関する資料の提出が増えるのは自然な流れ。立証で重要になるのは、最後は質。書証の多寡から、どちらに有利かどうかは一般的には言えない」
「(原告側は)社会的評価の立証が必要となるがゆえに、必然的に(結果的に)、科学的・制度的正当性という外部的権威の積み上げが必要となる」との見方を示している。
いずれにせよ、両者の訴訟姿勢は「公的承認と科学的正当性」(原告)、「公的制度批判と政治的言論の自由」(被告)という対立軸を形成している。
責任論を争うこれまでのステージから、次回以降は損害論の有無と立証方法が焦点となるが、書証の性質上、裁判所が量よりも文脈的関連性と説得力をどのように評価するのかが注目される。
他の名誉毀損訴訟に見る構図の類似
筆者が裁判記録を閲覧した10月21日、同じ東京地裁で、㈱幻冬舎(東京都渋谷区、見城徹社長)がアーク・タイムズ㈱(東京都千代田区、尾形聡彦社長)を名誉棄損で訴えた民事訴訟の判決が行われた。結果は、原告側が敗訴した。
同訴訟は、YouTube上で配信されたアーク・タイムズのYouTube動画における発言が、幻冬舎側の名誉を毀損したとして提起された裁判で、原告は「不法行為に基づく損害賠償および謝罪広告の掲載」を求めていた。
争点は大きく2点である。アーク・タイムズが配信した動画内で、①テレビ朝日の番組で幻冬舎が出版した書籍の広告が、広告であることを隠して放送されたかのような発言があったか、②動画内で、テレビ朝日の番組コメンテーターの降板が、幻冬舎側の意向で行われたかのような発言があったか――というもの。
裁判所の判断は、「発言の趣旨にそのような事実は含まれない」だった。
つまり、被告らの発言は「幻冬舎が関与してテレビ朝日番組内で広告を行った」との事実を述べたものではない。また、「コメンテーターの降板が幻冬舎側の意向による」との事実を述べたものでもない。すなわち、発言の趣旨はあくまで「社会的な状況を論評・意見として述べた範囲」にとどまっており、名誉毀損に当たる“事実の摘示”は認められないというもの。
裁判では、事実の摘示そのものが認められなかったという結果に終わった。そういう意味では、アーク・タイムズの尾形社長が今回の訴えを「スラップ訴訟」と呼ぶのもうなづける。いずれにせよ、YouTubeなどのネット報道に対し、企業側が名誉毀損を理由に提訴するケースが増える中で、この判決は「事実の摘示」と「意見・論評」の線引きを明確にし、報道・言論活動における表現の自由の範囲を広く認めた判決となった。幻冬舎側が控訴するかどうかは今後の判断次第だが、現時点ではアーク・タイムズの全面勝訴という結果で結審した。
原口一博議員のYouTube配信は報道とは言えないものの、対立軸としては上記に似た構図を示している。次回からは損害論という新たなステージに入るが、同議員とMeiji Seikaファルマの訴訟からも目が離せない。
【田代 宏】
関連記事:コロナワクチン訴訟、第1回口頭弁論 裁判長、Meiji Seikaファルマに証拠補充を指示
:新型コロナワクチン訴訟の行方は? 18日、第3回弁論準備手続き開催へ~明治製菓ファルマVS原口議員
:コロナワクチン巡り名誉毀損裁判進展 Meiji Seika ファルマと原口議員の対立深まる
:原口衆院議員訴訟、損害論へ移行か Meiji Seikaファルマが第5回弁論準備で争点整理