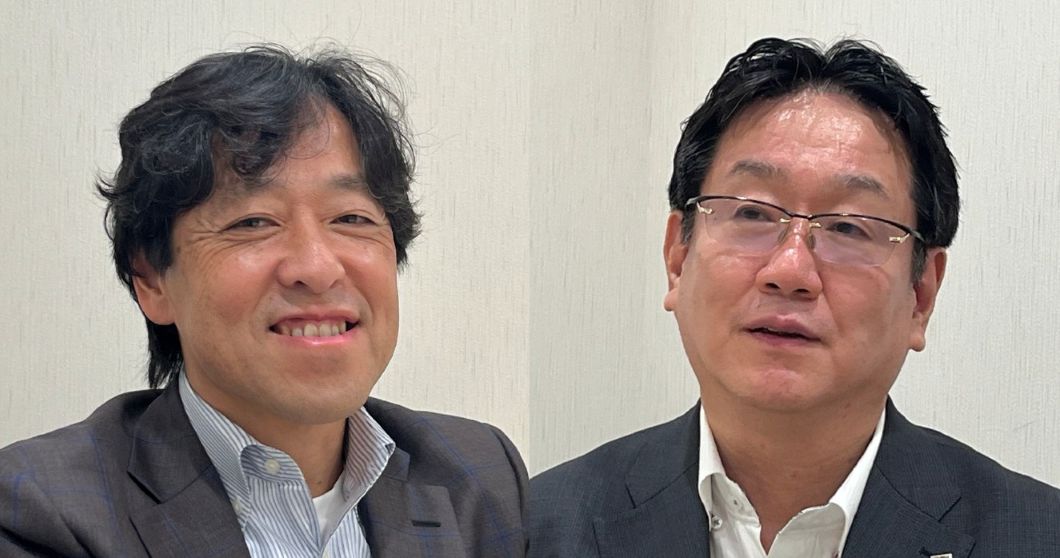日本健康食品工業会インタビュー(後) 【特集・サプリ受託製造の今とこれから】「受託製造業界全体の底上げも役割」
(一社)日本健康食品工業会(日健工)──サプリメントをはじめとする日本の健康食品のバリューチェーンの真ん中に位置付けられるOEM/ODMに特化した、国内健康食品業界にこれまでなかった「ものづくり」の団体だ。今年3月に受託開発・製造企業25社で船出してから約半年。展望はいかに。会長を務める野々垣孝彦・アピ㈱社長(=写真右)と、専務理事の今村朗・三生医薬㈱社長(=写真左)に訊いた。前後編のうち後編。
受託製造業界全体の品質レベル底上げめざす
──機能性表示食品のサプリについてGMPが義務化されました。来年8月末までは経過措置期間ですが、その間、消費者庁の担当官が工場に立ち入り、GMPの実施状況の確認などを行います。すでに6月から始まっていますが、会員企業から戸惑う声が上がっていませんか?
今村 これまで無かったことですから、戸惑う企業がいらっしゃったのは事実です。「これから何が起こるのか」と。ただ、我々も消費者庁とコミュニケーションを取っていて、「審査するわけではない。リラックスしてご対応いただきたい」と伝えられています。
野々垣 要は、「過度に恐れる必要はありません」ということです。健康食品の分野ではこれまで、行政機関が工場を訪問し、実際に現場を見る機会はほとんどありませんでした。そのため、初めての場面では不安を感じるのも自然なことです。しかし、医薬品の監査と同じで、仮に指摘を受けても、それを改善すれば問題ありません。大切なのは、指摘を放置しないことです。重大な問題は別ですが、指摘を受けた段階で「裁かれる」ということでは決してなく、むしろ改善のきっかけになります。
今村 消費者庁が経過措置期間中にGMP実施状況を確認するのは、サプリの製造現場をしっかり理解した上で来年9月以降に臨みたい、という思いもあるのだと思います。行政としても、健康食品の製造現場を実際に見た経験はほとんどないはずです。実際、確認が始まる前、日健工のメンバーを含む複数社に対して消費者庁から「工場に行かせてほしい」と連絡が入り、それぞれ対応させてもらいました。
野々垣 実際に確認を始める前に目線合わせをしておきたい、ということだと思います。
今村 そうしたことができるのも、工業会ができたことのメリットの1つです。行政サイドと、我々製造サイドの目線合わせはこれからも必要で、将来的にサプリ全般にGMPが義務付けられることになるのだとしても、そこが第一歩になると思います。
──消費者庁によれば、経過措置期間中の確認対象となる工場は約300施設もあります。一方で、日健工の会員は30社足らず。受託製造業界全体の製造・品質管理レベルの向上についてはどう考えていますか。
今村 日健工の会員企業の売上高を合わせると、国内健康食品受託製造市場規模の相当量を占めます。しかし、国内の受託製造企業は200社以上と言われますから、日健工メンバーはそのうち30社にも満たないわけです。そのなかで、健康食品GMP認証を取得していなかったり、日健工メンバーでなかったりするところの品質管理レベルをどのように引き上げていくかということは、消費者庁も関心を抱いているでしょうし、我々としても重要なアジェンダ(検討課題)の1つになると考えています。非常に難しい課題ですが、我々工業会が行政から期待されているのはそこなのだと感じています。
野々垣 GMPを含めた製造管理や品質管理などについて勉強する場を作っていく必要があると考えています。ものづくりの環境、ルール、あるいは人材育成といったところを組織的に教育したり、勉強したりしながら、受託製造業界全体のレベルの底上げを図っていくことは、工業会の活動方針の1つです。そこは実際に取り組んでいきたいと考えています。
もし、受託製造のところで問題が起きてしまうと、たとえ一企業が起こした問題であったとしても、それによって健康食品業界全体の信頼を低下させたり、市場に重大な影響を与えたりしてしまう。去年の健康被害問題のように、です。そうならないように、サプリの製造管理や品質管理を是正しなければならないと国は考えているのでしょうし、私ども工業会としても、受託製造業界全体の管理レベルの底上げを考え、活動していく必要があると思っています。
バリューチェーンの真ん中に立つからこそ
──最終製品にだけGMPを義務付けることになった機能性表示食品制度の改正にせよ、微生物等原材料の受け入れに関する指針が新たに盛り込まれた「3.11通知」の改正にせよ、受託製造企業の負担が大きく高まっているように思います。
野々垣 会員企業に対してアンケートを行いました。その結果、さまざまな意見や声が上がったのは事実です。それに基づき、各委員会の検討テーマを具体的に選定し、優先度合いも考えながら各課題の解消に向けて取り組んでいきます。
──去年の健康被害問題がそうでしたが、そもそもの原因は原材料にあります。また、最近では、機能性表示食品に限らず健康食品全般に多用されている原材料に医薬品成分のエフェドリンが微量混入していたことが判明、最終製品の大規模な自主回収に至りました。原材料を受け入れる立場の団体である日健工として、そういった原材料を巡る課題にどのように対応していきますか?
野々垣 品質安全管理委員会で検討することになります。多種類の原材料を取り扱う必要のある我々のような受託メーカーが、原材料をどのように受け入れていくのかということは、業界全体の課題だと思います。実際、我々がGMP管理を運用していくなかで、原材料の受け入れ検査などの管理をどのようにしていくかというのは今、非常に大きなテーマになっています。まずはGMPが義務化された機能性表示食品のところから管理手法を詰め、その手法を健康食品全体に引き上げていく必要があると思っています。
もちろん、現実を見ないとなりません。全ての受託製造企業が同じレベル感で対応できるのかといえば、それは難しいはずです。それに、原材料の品質確保は、受託メーカーだけで全てに対応できるはずがなく、原材料メーカーと必ず連携する必要があります。我々受託メーカーが原材料をどのように管理していくべきなのかということについては、行政を含めた多方面と協議しなければならない要素が山積しているのです。
今村 野々垣会長の言うとおり、原材料にどう対応していくのかというのは今、我々受託開発・製造企業にとって、とても悩ましい問題になっています。この点については私も、行政との対話を進めていく必要があると思っています。その上で、今後も起こる可能性がある同様の問題に対して、我々工業会としてどのように対応していくのかということについて言えば、運営委員会や品質安全管理委員会が中心になって対応チームを即座に組織し、会員企業のネットワークを使って情報収集であったり、外部の有識者の意見や見解の聴取であったり、販売会社とコミュニケーションであったりを進めながら、迅速に対応指針を取りまとめ、発信していく。そのような取り組みが必要だろうと考えています。
ふたたび重大な問題が起きることを考えたくはありませんが、何か問題が生じてしまった後、いかに安心・安全を消費者に感じていただけるようにするか。工業会として取り組むべき大きなポイントの一つになると思っています。
──品質安全管理委員会で「品質基準」を検討するという話がありました。その中身はどのようなものになりそうですか。
今村 具体的な検討はこれからです。ただ、健康食品の安心・安全を本当の意味で守れるのは、我々受託開発・製造だと私は考えています。そのためにやれることを我々は分かっていますし、逆に、できないことも分かっている。そうした立場である我々が、健康食品の安心・安全を守るために最大限必要なことは何であるのかということについて意見を表明し、それを守るために求められる健康食品の品質に関する基準を適切に作っていくという役割を、我々は担っていると考えています。
野々垣 私ども受託メーカーは、健康食品のバリューチェーンの真ん中に立っています。川上の原材料メーカー、川下の販売会社、それぞれと直接つながっている立場です。だからこそ我々の立場には厳しい面もあるのですが、健康食品に対する行政の目線が、これまでの広告表示を含む販売手法から品質に変わってきたというのも事実です。今村専務理事の今のお話は、そのような変化の中で、バリューチェーンの真ん中に立つ受託メーカーだからこそできることをやっていこうということです。
(了)
前編はこちら
【聞き手・文:石川太郎、取材日:2025年7月29日】
【特集・サプリ受託製造の今とこれから】関連記事
:規制の矢面に立つ受託メーカー 品質への信頼、回復させる役割担う
:医薬品GMP専門家・櫻井信豪教授に聞く 規制強化とともに品質文化の醸成を
:製造現場を業界団体はどう支えるか JAOHFA「GMPチーム」の取り組み
:エフェドリン混入問題、経緯と考察 見えざるリスク抱えた原材料にどう対応するか
:制度改正、9割超が対応に困難感 健康食品OEM企業アンケート調査
日本健康食品工業会関連記事
:活動を本格化 4委員会発足 初年度重点課題に制度対応・品質管理両面からの連携強化
:サプリ受託製造25社で船出、設立記念祝賀会開催 野々垣会長「連携による業界発展目指す」
:日本健康食品工業会が始動 サプリに対する信頼回復、「受託開発製造企業の集結必要」
関連記事
:消費者庁食品表示課保健表示室に聞く 改正・機能性表示食品制度の運用実態と課題(前編)
:同上(中編)
:同上(後編)