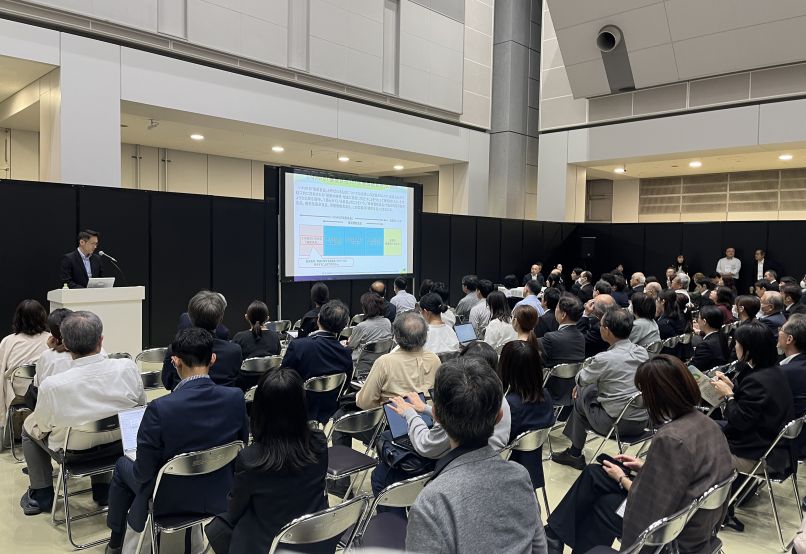民間認証取得で「対応スムーズ」 消費者庁保健表示室が見解、機能性表示食品のサプリGMP義務化実施控え
消費者庁の食品表示課保健表示室課長補佐は15日、健康食品業界団体の(一社)健康食品産業協議会(JAOHFA)が都内で開いたセミナーに登壇し、サプリメントGMPに関する民間の第三者認証の取得を推奨した。
サプリGMP認証を取得している製造・加工施設は、取得していない場合に比べ、機能性表示食品のうち錠剤・カプセル剤などの形状を持つサプリのGMP義務化への対応がスムーズに進むとの見方を示した形だ。
民間によるGMP認証の取得は法令要件では一切ないが、同庁としてサプリ製造・加工施設のGMP実施状況の確認・助言を進める中で得た感触を、率直に述べたとみられる。
民間GMP認証、義務ではないが望ましい
JAOHFAは、同日開幕した「食品開発展」内で、「行政との合同セミナー」を開催した。行政からは、消費者庁食品表示課保健表示室の増田利隆課長補佐が登壇。増田氏は、機能性表示食品など保健機能食品の制度改正をテーマに講演しつつ、JAOHFA分科会長らとのパネルディスカッションに参加した。
増田氏はパネルで、同課内に今年4月に組織された「GMPチーム」が5月末から順次進めている、機能性表示食品のサプリの製造・加工施設におけるGMP実施状況の確認・助言の進め方や状況などを解説。その中で、実際に工場を訪れたGMPチームの感触について、「(サプリGMPの)民間認証を取得していると(確認が)スムーズなところがある」と述べ、逆に取得していない場合は、「多くのご説明をしなければならなかったり、(助言すべき)ポイントが多くなったりする」などと説明した。
そのうえで、「(制度上)必須ではないが、今までの蓄積がある民間認証も取得していただきながらやっていくのが良いのではないかと思う」と述べ、来年9月に完全実施を控える機能性表示食品のサプリのGMP基準遵守義務化を円滑に進めるためにも、民間認証の取得が望ましいとの見解を示した。
日本のサプリ・健康食品GMPの民間認証制度は、厚生労働省が取りまとめたGMPガイドライン(錠剤・カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方=平成17年通知)の公表を受けて2005年にスタート。それ以来現在まで、(公財)日本健康・栄養食品協会と(一社)日本健康食品規格協会の2つの民間認証機関が、サプリや健康食品の品質・安全性を確保するため、第三者として定期的な監査を実施しながら原材料を含めた製造・加工施設などに対してGMP認証を行っている。現在、200を超える国内サプリ製造・加工施設が同認証を取得しているとされる。
機能性表示食品のサプリの製造・加工施設が遵守する必要があるGMPの要件は、食品表示基準の規定に基づく内閣府告示「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」(GMP基準)に規定されている。サプリGMP認証などの民間認証を取得しているからといって、告示の要件を満たしていることにはならない。ただ、保健表示室の前室長は昨年12月、ウェルネスニュースグループの取材に対し、次のように語っている。
「民間認証を受けている中で、全てを説明できるのであればそれで良いと考えています。
GMPについては、国内では2つの機関が『平成17年通知』の頃から『3.11通知』の現在まで、通知を念頭におきながら民間認証を進めていただいています。認証を受けている製造施設は当然、認証を受けるに見合った体制や書類などを整えているはずです。GMP基準は「3.11通知」の別添2をそのまま落とし込んだものですから、民間認証を受けている中で説明できるところが多いはずですし、FSSC22000などのGMPとは考え方の異なるところがある食品安全に関する民間認証にしても、説明できる部分は少なくないと思います。
不足しているところを確認し、それを補っていただければよいと考えています」
【石川太郎】
(冒頭の写真: 15日午後、JAOHFAが「食品開発展」内で開いたセミナーの様子)
関連記事
:告示に規定されたサプリGMP基準 【改正・機能性表示食品制度の全貌】推奨から義務へ、立入検査も実施
:消費者庁食品表示課保健表示室に聞く 改正・機能性表示食品制度の運用実態と課題(後)
:サプリ安全性確保、行政の考え(前) 改正機能性表示食品制度にどう反映されたか、消費者庁食品表示課に聞く