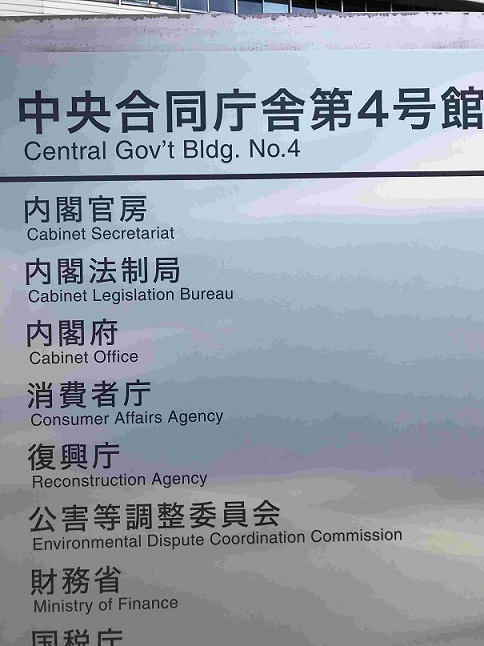細胞培養食品の呼称と安全性を議論 消費者庁新開発食品調査部会、制度設計の課題整理
消費者庁は29日、新開発食品調査部会を開き、細胞培養により製造される食品の呼称や適用範囲、安全性確保の制度設計について議論した。呼称は「細胞培養食品」(仮称)で合意し、現時点では動物由来タンパク質を対象としつつ、将来的に植物や昆虫などにも対応可能とする柔軟な整理が行われた。安全性確保の手続きについては、医薬品や遺伝子組み換え食品と同様に行政機関が製品ごとに確認審査する「類型①」を当面採用するべきだとの方向で一致した。未知のリスクやガイドラインの厳格化による参入障壁などの課題も指摘され、制度運用のあり方が今後の焦点となる。
将来を見据えた柔軟な呼称を整理
部会では、細胞培養により製造される食品の呼称について議論した。事務局案では「動物性細胞培養食品」とされていたが、委員からは「動物性」と限定すると将来的な植物培養食品やコーヒー・チョコレートなどの事例に対応できないとの指摘が相次いだ。
国際的にも「セルカルティベイテッドプロダクツ」(シンガポール)、「セルベースドフード」(WHO)といった「アニマル」を含まない呼称が主流であることから、最終的に「細胞培養食品」(仮称)とする方向性が確認された。
適用範囲についても当初は「魚類を含む動物由来の細胞」とされていたが、北嶋聡委員(国立医薬品食品衛生研究所)からは「魚介類」と広くすべきとの意見が出され、さらに植物や昆虫、真菌も将来的な対象となり得るとの指摘があった。結果として「細胞培養技術により製造されるもの全般」を対象とし、ただし「現時点ではタンパク源としての動物に由来する細胞を当面のターゲットとする」との留保を付けることで合意形成した。
安全性審査の4類型を提示
安全性確保の手続きに関する議論に移り、事務局は現行制度における手続きの類型を提示した(資料1-2)。細胞培養食品(仮称)をどの類型で位置付けるべきか、委員の意見を求めた。
まず類型①として、行政機関による個別製品の確認審査型が紹介された。これは製造販売の許可申請において、あらかじめ定められた規格基準や評価指針に基づき、行政機関が製品ごとに確認審査を行う方式であり、医薬品や高度管理医療機器、特定保健用食品、遺伝子組み換え食品などがこの方式を採用している。
次に示された類型②は第三者認証型であり、規格基準や審査評価指針への適合性を認定を受けた第三者認証機関が製品ごとに確認する方式である。例として、国に登録された認証機関によるJISマーク認証や農林水産省登録の認証機関によるJASマーク認証が挙げられた。
さらに類型③として届け出型が説明された。これはあらかじめ定められた規格基準や審査評価指針に適合して製造された製品について、企業が行政機関に届け出を行う方式である。一般医療機器や化粧品、機能性表示食品、ゲノム編集技術応用食品などがこれに含まれる。
最後に類型④として、自主管理型が示された。これは製造者が定められた規格基準に基づき自らの責任で製品を製造し、行政機関に対する届け出や個別審査を必要としない方式であり、栄養機能食品などがこの類型に当たる。
事務局は、現行の遺伝子組み換え食品等の安全性審査について説明した。輸入販売には安全性審査の実施が必須であり、審査を経ていない遺伝子組み換え食品やそれを原材料に用いた食品の製造・輸入販売は食品衛生法で禁止されている。審査は種目ごとに食品安全委員会の意見を踏まえて行われる仕組みだ。
2001年の義務化以前は、製造者が施設や生産物のガイドライン適合を厚生省に確認することが求められていた。また制度開始当初は、製造指針や安全性評価指針を基盤とするガイドラインにより運用されていたことが示された。さらに現行のゲノム編集技術応用食品については、製造者がまず消費者庁へ事前相談を行い、その後に届け出を行う流れで、事前相談で安全性審査が必要と判断された場合には、消費者庁から食品安全委員会へ審査依頼を行う体制となっている。
未知リスクへの対応と制度運用
議論では、動物細胞・植物細胞に共通するリスクとして病原体やホルモン生成が挙げられた。また植物特有のリスクとして、アルカロイドなどの二次代謝産物による毒性の可能性も指摘された。ただし、既存のハザードリストの枠組みで多くは対応可能であるとの見解が示され、未知のリスクにどう対応するかが焦点となった。
石見佳子委員(東京農業大学総合研究所)は「危害発生の可能性があるなら類型①、そうでなければ類型③もあり得る」と述べ、安全性の程度に応じた柔軟な制度運用の必要性を強調した。
一方、曽根博仁委員(新潟大学大学院)は「遺伝子組み換え食品が類型①である以上、細胞培養食品をそれより低い規制にするのは難しい」との見解を示し、厳格な対応を求めた。
類型①を基本とした行政関与の必要性
松尾真紀子委員(東京大学大学院)は「リスクアナリシスの枠組みを踏まえて考えると、例えば類型①にしても、疑義があればリスク評価機関(食品安全委員会)に諮問する体制を整えるべき」と指摘。北嶋委員は「米国のFDAとEUのEFSAではそれぞれ制度設計が異なるが、日本では国が関与しない体制は考えにくい」とした。
石見委員は、「ゲノム編集食品については自然の突然変異で起こる変異体と変わらず、遺伝子を新たに導入しているわけでもなく、安全性に問題がないことが繰り返し議論されてきた結果、現在の評価システムが構築されている」と述べた。その上で、細胞培養食品についても食品衛生上の危害発生の可能性を議論する必要があると指摘。「危害の可能性があるなら食品安全委員会を通すリスク分析の原則を徹底する類型①を採用すべきであり、安全性に大きな問題がないのであれば類型③のシステムでもよい」とし、安全性の程度を議論しなければすぐに結論を出すことは難しいとの考えを示した。
「遺伝子組換え食品が類型①である以上、これよりレベルの低い規制は考えにくい」との曽根博仁座長(新潟大学大学院)の見解を受けて、小泉聡司参考人(科学技術振興機構)は「開発が進んでいる海外企業からの申請が多くなることを考えると、消費者に安心感を与えるためにも行政機関のチェックが大切」と述べた。
他方、加藤将夫委員(金沢大学)は、今回の細胞性食品は幅広い形態が想定されるためリスクはあると考えると述べた。その上で、「行政機関が関与することは必要だとしつつも、医薬品と同じ水準で厳密に扱うのはしっくりこない」と指摘。「細胞性食品は主にたんぱく質供給を目的とするものであり、健康に悪影響を及ぼす可能性は否定できないものの、たんぱく質という性質を踏まえると、過度に厳密に考える必要があるのか疑問もある。原則は類型①でよいが、開発のスピードを落とさないよう緩和的な配慮が必要ではないか」との考えを示した。
瀧本秀美委員(医薬基盤・健康・栄養研究所)は、「まずは類型①で運用し、知見が積み重なってから他の類型に移行するのが望ましい」と発言。松﨑典弥参考人(大阪大学)も同調しつつ「シンガポールでは審査に数年かかる例がある。柔軟に移行できる仕組みが必要」と述べた。岡田由美子委員(国立医薬品食品衛生研究所)、柴田識人委員(同)、五十君静信参考人(東京農業大学)も類型①の採用を推した。
厳格なガイドラインと参入障壁の懸念
一方、児玉浩明委員(千葉大学大学院)は、遺伝子組み換え食品の審査を担当してきた経験から意見を述べた。類型①で始めること自体には異論はないとしつつも、ガイドラインの作り方が重要であると指摘した。「最初に非常に網羅的で細かいリスク評価を求める厳しいガイドラインを作ってしまうと、その後に緩和するのは非常に難しく、長期間にわたり厳格な運用が続いてしまう」と述べた。実際に遺伝子組み換え食品の分野でも「当面の間」とされた規定が外されないまま運用され続ける事例があるという。
また、厳格なガイドラインは資金力のある大企業のみが対応可能となり、資金面で制約の大きいベンチャー企業には参入が難しくなる問題を指摘した。遺伝子組み換え食品では厳しい基準が設けられた結果、実際に申請できるのはグローバルに展開する数社に限られる状況となっており、「細胞培養食品では同様の事態を避ける配慮が必要」だと述べた。
さらに、遺伝子組み換え食品は申請が義務化されている一方、ゲノム編集食品はボランタリー(届出)であるとし、法律に基づいて義務化するのかボランタリーにとどめるのか、その点も考慮して制度設計を行う必要があると強調した。
議論のまとめとして、原則、類型①の「個別確認審査型」を採用。運用に関しては、今後の議論も含めて規制のあり方を考えていく方向が示された。
【田代 宏】
当日の配布資料はこちら(消費者庁HPより)