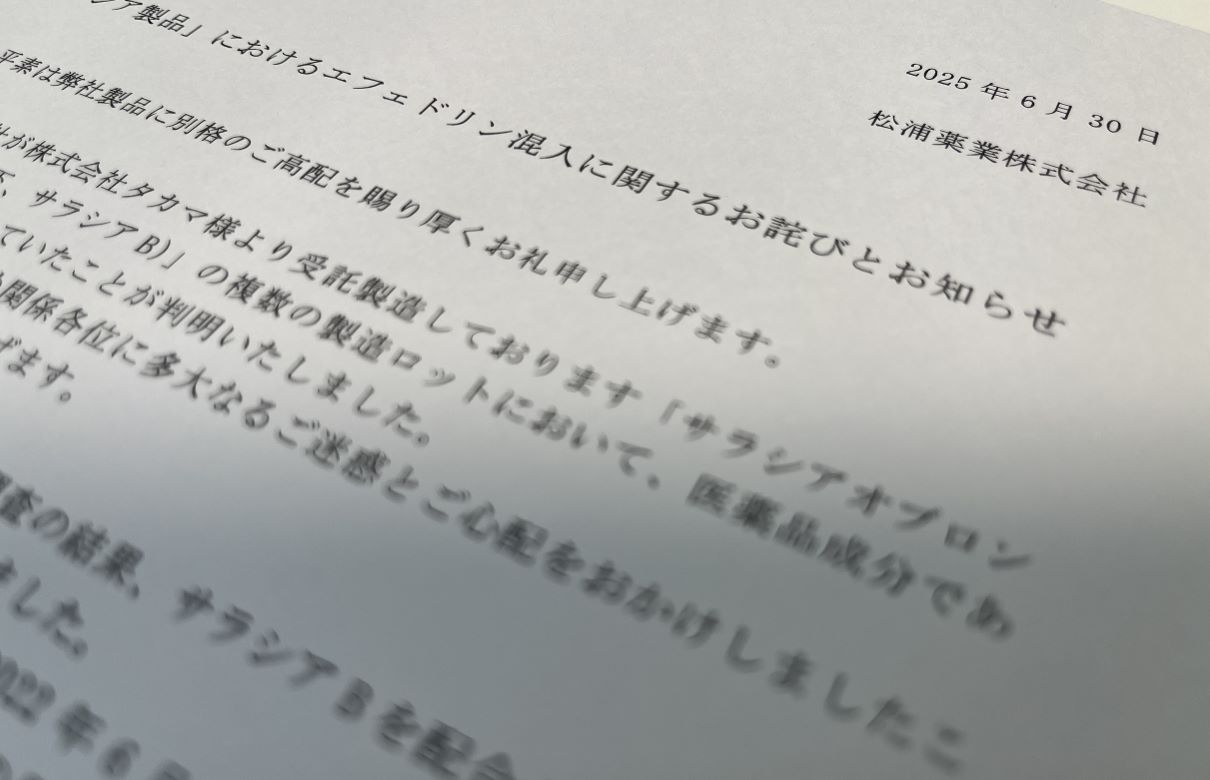エフェドリン混入問題、経緯と考察 【サプリ受託製造の今とこれから】見えざるリスク抱えた原材料にどう対応するか
含まれることが想定されない成分を含んでしまった原材料。最終製品製造工場の受け入れ検査でそれを見破ることは困難を極める──機能性表示食品にも多く利用されている原材料の一部ロットに医薬品成分が混入していたことが判明し、最終製品の大規模な自主回収へと至った問題は、そのことを改めて痛感させる。小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題と同様、原材料の製造・品質管理に疑問符が付く問題がまた生じた。
混入リスク、認識していたのは誰か
ことの発端は茨城県が2024年度に実施した「いわゆる健康食品」の買上調査。県内の店舗やインターネットで32品目を買い上げ、医薬品成分含有の有無を分析したところ、交感神経系などに作用する医薬品成分のエフェドリンが1品目から検出された。
普通、公表すると思われるが、県は、検出値を踏まえ、「人の健康に影響を及ぼすような値ではない」(薬務課)ことを理由に製品名等の公表を控えた。というのも、当該製品(錠剤)から検出されたエフェドリンはわずか0.51µg/g(0.00051mg/g)。県としても、悪質性のない意図せざる混入が原因と考えたのだろう。
一方、非公表の理由は他にもあった。県は、24年度の買上調査で、検査機器を入れ替えていた。その結果、従来であれば「不検出(ND)」の量でも検出可能になっていた。そうした事情も考慮して公表しなかったという。
ただ、検出量の多寡はどうあれ、医薬品成分が含まれる食品の流通は、医薬品医療機器等法の第55条第2項、いわゆる「無承認無許可医薬品」の製造・販売等の禁止規定に抵触する恐れがある。そのためだろう。県は、当該製品の販売者等を管轄する自治体に情報提供するとともに指導を依頼。結果的にこれが、健康食品業界に波紋を起こすことになった。
茨城県の買上検査でエフェドリンが検出された理由は、当該製品の原材料にあったことが後に判明する。血糖値の上昇抑制機能があることで知られ、機能性表示食品から「その他のいわゆる食品」まで健康食品に広く使用されているサラシアエキス末。そのBtoB(対事業者)販売で国内最大手の㈱タカマ(山口県下関市)の委託を受け、医薬品の製造販売も行う松浦薬業㈱(愛知県名古屋市)が2021年11月から22年10月までの間に製造したその一部ロットにエフェドリンが微量、含まれていたことが、第三者機関の分析で確認された。エキス末における検出量は、最大3.8µg/gであったとされる。
この量について松浦薬業は、「市場のサラシア製品の配合されている1日配合量の場合、エフェドリンの1日最小有効量である12.5mgの約10,000分の1」に過ぎないと説明。「効果を発現しない程度の量であることから、健康被害の可能性は極めて低い」との見解も併せて示し、茨城県と同様、人の身体・生命に影響を及ぼすような量ではないことを強調した。
出荷前の分析で未然防止できた可能性
だが、極めて微量であるにせよ、エフェドリンが検出された事実は揺るがない。なぜサラシアエキス末にエフェドリンが含まれていたのか。サラシアには本来、エフェドリンは含まれない。推定されている理由はこうだ。
松浦薬業の主力製造販売品目は医薬品。愛知県知多郡武豊町に置く製造拠点「冨貴工場」の生産品目には、エフェドリンを有効成分として含むことで知られる生薬のマオウを使用する医薬品、葛根湯エキスがある。同社はそれと同じ製造設備でサラシアエキス末を製造していた。だが、製造ラインなど設備の洗浄が不十分であったため、その製造工程でマオウの一部が微量、混入してしまった──いわゆる「コンタミ」、医薬品の専門用語だと「交叉汚染」が発生したのが理由だと考えられている。
そもそも医薬品と同じ製造設備で健康食品を作るのは違法ではないのか──業界関係者からはそのような疑問の声も上がった。結論から言えば、必ずしもダメではない。国が定めた医薬品GMP基準に関する法令では、「交叉汚染を防止する適切な措置をとる場合」に限って容認している。
ただ、それを行うためのハードルは高い。行政機関で医薬品GMP監査などに従事した経験を持つ人物はこう指摘する。
「洗浄バリデーションにより、共用している製品(例えば食品)なども含めた洗浄性などを確認していれば、ある程度できる部分はある。ただ、食品についても管理を医薬品レベルに引き上げないといけないなど、なかなか大変」
実際の原因は、松浦薬業が行う原因究明調査の結果を待つ必要がある。だが、原因が何であれ、そのように医薬品成分が混入した健康食品の原材料が製造、出荷され、それが製剤化されて最終製品として市中に広がったことの帰結は、機能性表示食品を中心とするサプリや健康食品の大規模な自主回収だった。その数量は、サラシアサプリを代表する富士フイルム㈱(東京都港区)をはじめとする販売大手3社の対象製品のみで合計100万個超。原材料1g当たり最大3.8µg程度の医薬品成分の混入という、医薬品医療機器等の視座で見なければある意味とても小さな問題が、400億円とも500億円とも言われるサラシア市場を揺るがすことになった。
問題の背景、第三者視点の欠如も
松浦薬業は冨貴工場についてウェブサイトでこうアピールしている。「医薬品GMPに則して製造、品質管理、衛生管理し、更なる向上を目指し日々稼働しており、健康食品および食品原料の製造においても、医薬品製造で培ったノウハウを活かし、医薬品GMPに準拠した管理基準を導入し、安心・安全な製品の製造に努めています」
実際にそうしていたのだろう。葛根湯エキスを作るときは医薬品の基準で、サラシアエキス末を作るときは健康食品の基準で──などと製造品目毎に管理基準を変更するほうが手間に違いない。「普通、高いほうの基準に合わせる」と医薬品GMPの専門家は指摘する。
だからなのだろうか。冨貴工場は、民間機関が第三者として認定する健康食品のGMP認証を受けていない。そのため、医薬品に関しては所轄の薬務課による医薬品GMP監査を受けていたにせよ、健康食品に関しては、専門知識を持つ第三者の視点、視線で検証されない自己完結型の製造・品質管理に終始してきたと考えられる……
(続きをお読みいただけるのはWNG会員のみです。会員申込はこちら。全文は「会員ページ」の「月刊誌閲覧」内「Wellness Monthly Report」2025年8月号(第86号)特集「サプリ受託製造の今とこれからVol.1」の12~13頁)
【石川太郎】
(冒頭の写真:6月30日付で松浦薬業がウェブサイトに載せたエフェドリン混入を巡るお詫びとお知らせ)
関連記事
:【サプリ受託製造の今とこれから】規制の矢面に立つ受託メーカー 品質への信頼、回復させる役割担う
:【サプリ受託製造の今とこれから】医薬品GMP専門家・櫻井信豪教授に聞く 規制強化とともに品質文化の醸成を
:【サプリ受託製造の今とこれから】製造現場を業界団体はどう支えるか JAOHFA「GMPチーム」の取り組み、原材料とOEMを繋ぐ