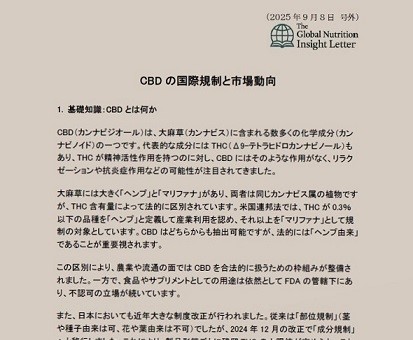CBDを巡る混乱と規制の現在地 CBD製品の適正使用~リスクと法の盲点
9月1日、サントリーホールディングス㈱(大阪市北区、鳥井信宏社長)の新浪剛史前会長が辞任した。辞任を巡る報道は業界全体に衝撃を与え、(一社)健康食品産業協議会(JAOHFA)が注意喚起を発表するなど、CBDを取り巻く制度と実態が再び注目されている。㈱グローバルニュートリショングループ(GNG、東京都豊島区、武田猛社長)が号外として発信したCBDに関するレポートでは、安全性評価や国際規制の現状が多角的に分析され、拙速な判断を戒める姿勢が示された。制度整備が進む一方で、科学的裏付けや消費者理解が追いついていない現状に、改めて冷静な視点が求められている。
サプリ使用問題が引き金に
9月1日、サントリーホールディングスの新浪剛史前会長が、自ら購入した海外製サプリメントに関する問題を受けて、突然辞任した。関係筋によれば、捜査の詳細は明らかにされていないものの、違法性が疑われるCBD製品が関係しているのではないかと報道されており、業界に大きな波紋を広げている。同社は同品がサントリー製ではないことを明言し関与を否定しているが、企業の信頼性とサプリメント産業の健全性が問われる事態を招いた。
CBDの制度整備と現実のギャップ
CBD(カンナビジオール)は、大麻草に含まれる成分の1つであり、精神活性作用を持たない天然由来の物質である。日本においては2024年に法改正が実施され、それまでの「部位規制」から「成分規制」へと制度が転換された。これにより、CBD製品は残留THCの基準値を下回る限りにおいて輸入・流通が可能となったが、公的機関による食品原料としての安全性評価はまだ行われていない。法改正によって定められたTHCの基準値が極端に低いことにより、すでに市場に出回っている製品においても法に抵触する恐れが否定できないためである。
(一社)日本ヘンプ協会の佐藤均理事長(静岡県立大学薬学系大学院客員教授)は、「CBDが時間をかけて徐々にTHCに変換していく」可能性を指摘している。
JAOHFAは今月3日、今回の事案を受けて、公式ホームページで「CBD 原料、CBD製品の適法性についてご確認のお願い」という注意喚起を行っている。
今回の件は個人の行為に起因するものであり、サントリー製品とは無関係だが、業界全体の信頼性に影響を与える可能性があるため、CBD製品の適法性の確認を行うよう会員企業に呼び掛けている。
また、GNGは8日、CBD(カンナビジオール)に関する特別レポートを会員向けに配信した。配信の動機について同社の武田社長は、近年「CBDサプリは合法である」とする一部報道が出回ったことを受け、①食品・サプリメントとしての安全性についての再考、②諸外国政府の対応を事実に基づいて提示、③日本政府の現状スタンスの客観的理解――の3点を意図したものだと説明している。
国際比較が示す規制のばらつき
同レポートでは、CBDの基礎知識から始まり、国際機関や米国における規制の歴史、市場動向、評価の分かれ方、国際比較、日本への示唆、用量と医薬品との相互作用までを10ページにわたり、包括的に取り上げている。
CBDは大麻草由来の成分であり、精神活性作用を持たない点でTHCと異なる。米国ではTHC0.3%以下を産業用ヘンプと定義し、農業・流通面で区別している。日本では2024年12月に「部位規制」から「成分規制」へと移行し、オイルや粉末製品では10ppm、水溶液は0.1ppm、その他は1ppmという厳格なTHC残留基準が設けられた。違反すれば刑事罰の対象となる。
CBDが注目される契機となったのは、2013年の米CNNの医療番組による小児てんかん治療の特集。その後、WHOが天然由来CBDに関して「耐容性が高く、依存性は低い」と評価。米国では2014年に産業用ヘンプの研究栽培が可能となり、2018年にはFDAが大麻由来の抗てんかん薬「Epidiolex」を承認した。
しかし、「医薬品として承認された成分は食品やサプリメントに使用できない」とする米国の基本原則により、CBDは依然として食品用途ではFDAに認められていないという。
GRAS(一般に安全と認められる物質)にも指定されず、NDI(新規ダイエタリー原料)通知も受理されていない。23年にはFDAが「既存の枠組みでは安全に管理できず、新しい立法が必要」との声明を出し、最終判断は議会に委ねられている。州ごとに異なる法整備が進んでおり、連邦と州との間の規制の二重構造が混乱を生んでいる。
市場動向を見ると、CBDは2010年代後半に急成長を遂げた。19年は「The Year of Hemp」と称され、CBD関連製品が一気に拡大。米国のCBDサプリ市場は前年の153百万ドルから268百万ドル、2020年には280百万ドルと急拡大したが、21年以降は減少に転じている。要因として、製品の品質問題、FDAの規制不在、COVID-19以降の消費シフトを挙げ、結果として、参入を見送る大手サプリ企業が増えたことから新興企業の多くは市場から撤退したという。
拙速な参入を避けるために
この他、EU・英国・カナダ・オーストラリア・中国・ASEANにおける各国の規制についても詳報。CBDという素材が持つ可能性と、それに伴うリスクを冷静に見極める視点の重要性を訴えている。拙速な判断ではなく、制度・科学・消費者受容の3要素を俯瞰し、長期的な視野で意思決定を行うことが肝要であると結んでいる。
(一社)日本ヘンプ協会の佐藤理事長は、「非常によく出来たレポートで、内容も正確」と高く評価している。
【田代 宏】