唐木氏・宗林氏を招き公開座談会 「消費者が安心して使える仕組みを」(宗林氏)、「事故の99%がヒューマンエラー」(唐木氏)
㈱ウェルネスニュースグループ(WNG、東京都港区)は18日、公開座談会「どうすれば防げたか~エフェドリン混入問題の出口を探して」をオンラインで開催した。健康食品原料メーカーや受託製造メーカー、販売メーカーなどの関係事業者はもちろん、行政・団体・有識者やメディア・法曹関係者など、幅広い層から170人を超える申し込みがあった。
まず初めに、WNGの石川記者が、「エフェドリン混入問題の経緯と現在」と題して取材報告を行った。茨城県の健康食品試買検査が端緒となった本事案。各事業者らの対応とその具体的な内容など、時系列で振り返った。
続いて宗林さおり・岐阜医療大学薬学部教授が「原料工場・最終工場・届出者の協力 外れ値(ロット)の科学的監視」と題して講演。宗林氏は、「昨年発生した小林製薬の紅麹サプリ事件を受け、消費者の機能性表示食品に対する安心感が揺らいでいる中、機能性表示食品の届出者による大規模な自主回収事案が発生した。原料会社や流通会社、最終製造工場、届出者、自治体間で、どこまで情報共有がなされていたのか、改めて検証する必要がある」と指摘。身体被害があった小林製薬の問題、身体被害はないものの薬機法違反の可能性があり大規模回収事案となった今回のエフェドリン混入問題、「全く内容は違うが、いずれも気付かないうちに消費者まで届いてしまった。消費者が安心して使えるように、科学データの受け渡しをしっかりと行うことが重要」と話した。
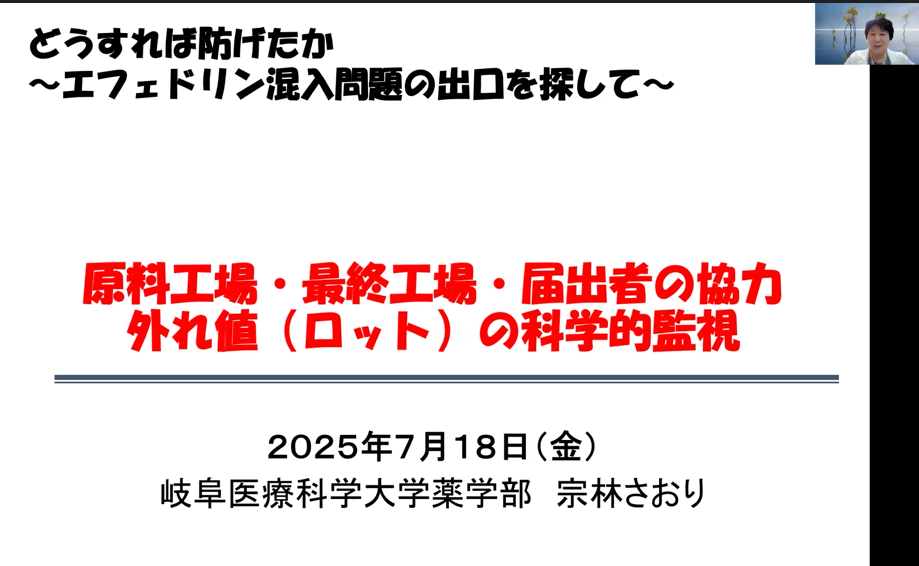
唐木英明・東京大学名誉教授は「問題の原因と再発防止に向けた提言」と題して講演。唐木氏は、「実質的な健康リスクがないにも関わらず、規制上および企業防衛上、社会的な『危機』が生み出された象徴的なケース」と指摘。「混入防止の努力は必要だが、それは『ゼロリスク』という幻想ではなく、科学的なリスク評価という土台の上に築かれた、新たな安全をめぐる『社会契約』の構築が必要。そのために、①規制の現代化(PDE導入)、②業界による規範遵守、そして③メディアや消費者を含む全ての関係者による知的な対話が求められる」と話した。
また唐木氏は、業界の対応に対して「サプリ業界が、なぜ明確なコメントを出さないのか。小林製薬の紅麹サプリ事件の時もそうだったが、消費者に対する説明責任を業界が果たしていない」と指摘した。
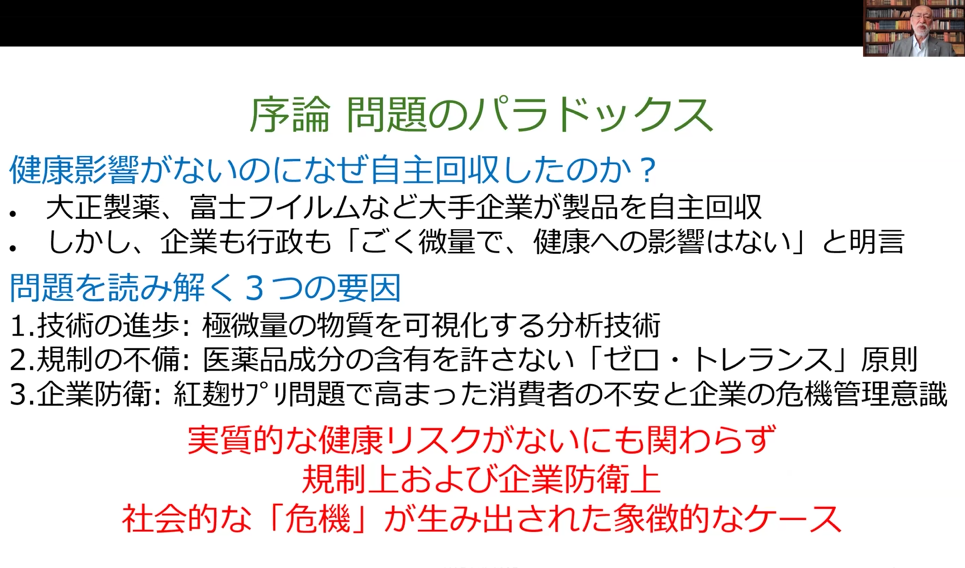
責任の所在について議論
今回の問題に関する責任の所在について宗林氏は、消費者が商品を選択する際、その判断材料はあくまでもその販売会社や商品名・ブランド。つまり機能性表示食品に関して言えば、届出者ということになる。そのため、対消費者責任は販売者が追うことになる。その上で、それ以上の被害拡大を防ぐための責任の所在を事業者間で明らかにする必要があると指摘。唐木氏も、消費者に対する販売者(届出者)の責任は免れないが、「責任はもう1つあり、それが事件・事故を起こしてしまった責任ということ。原因をいち早く究明し、被害拡大を防がなくてはならない」と話した。
座談会では、その他、医薬品と健康食品を同じ製造ラインで作ることの是非、科学的リスク評価(許容限界値=PDE)の導入の実行可能性と実現手段などについて意見が交わされた。宗林氏は「関係者間でどこまで情報が共有されていたのか検証し、消費者に届く前にストップし、消費者が安心して商品を手にすることができる仕組みづくりが必要と話した。
唐木氏は「紅麹サプリ事件と今回のエフェドリン混入事件と、たて続けに事件が発生したが、リスクを完全にゼロにすることは不可能。HACCPやGMPといった安全対策を取ることは最低限として、事故の99%がヒューマンエラーによるものということを再認識する必要がある。精神論になるが企業のトップがそこを意識し、安全文化を築いてもらいたい」と締めくくった。
アンケート回答者の約9割が満足
参加者からは、「回収すべきだったのかどうかについて同意できた」、「分析機械の性能が上がっている現代で、今後も起こり得る事態だと理解できた」、「医薬品製造での残留物質と比較しての話はとても分かりやすく、問題点がどこにあるのかも分かりやすかった」という感想が寄せられた。
その他、「原料の安全性について、機能性表示食品の制度を踏まえて考察してもあまり意味がないと思った。圧倒的に、機能性表示食品ではないサプリメントの方が多いため、いつまでも食品とサプリメントの法律が同じということに問題があるのではないか」、「今回の件、規制当局はどのように捉えているか。何もする必要はないと考えているのか、それとも何らかの規制が必要と考えているのか。自治体の対応がバラバラなのも含め、その辺りが気になった」、「原料メーカーが主として取り組んでもらわなければ、届出者、加工製造所だけでは限界があると考えている。業界の自主基準も必要だが、行政の強制力も必要ではないかと思う」といった意見もあった。
【藤田勇一】






















