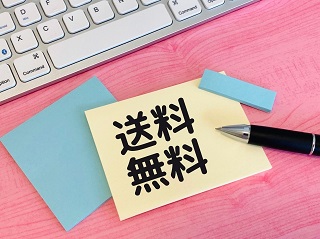物流問題と送料無料表示を再考(8) 【回顧ドキュメント】表示の見直し「協働」で築く持続可能な物流
2023年11月8日に開催された第9回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会は、消費者団体の代表者たちによる議論の最終ラウンドとなった。登壇したのは、消費生活アドバイザーの大石美奈子氏、主婦連合会の河村真紀子氏、(一社)日本消費者協会の河野康子氏、(公社)全国消費生活相談員協会の増田悦子氏である。
「送料無料」が生む過剰配送とその影響
大石氏は、「送料無料」表示が消費者にとっては一見魅力的に映るが、実際には物流にも環境にも負荷がかかっていると指摘。消費者がその“実感”を持たないまま日常的に個別配送を繰り返すことが、過剰な配達需要を生んでいるとし、「送料当社負担」などの実情を反映した表現への転換が、エシカル(倫理的)消費の第一歩であると訴えた。
一方で河村氏は、「送料無料」表示が、再配達の削減や意識変容には一定の効果があるとしても、そもそも「表示問題」と「労働環境の改善」、「輸送力不足」とは別の課題であることを明確にすべきと主張。問題が「送料無料表示」にあるのか「送料無料」にあるのか、課題の本質を誤らないよう、複数の政策的手段を分けて講じることの重要性を訴えた。
表示だけでなく構造的課題の議論へ
河野氏もまた、「送料無料=無料だと誤認する消費者は少数派」であるとの認識を提示。特に宅配便の荷物量が物流全体に占める割合は限定的であり、むしろ企業間物流の改善に注力すべきとした上で、「消費者が協力できる余地は多いが、それを実現するには企業側の説明責任や工夫も不可欠である」と論じた。
増田氏は、表示の見直しそのものが即座に再配達削減や労働負荷の緩和に直結するわけではないという現場感覚に立脚しつつ、ポイント還元や宅配ロッカーの整備、事前通知システムといった“実効性のある仕組み作り”の必要性を強調した。
表示の見直しから始まる協働の第一歩
この回で共通していたのは、「送料無料」表示だけを悪者にしても問題は解決しない、という視点である。むしろ、表示をめぐる議論が、消費者、事業者、物流業界というサプライチェーン全体の“協働”に向けた第一歩となることこそが重要であるという認識が共有された。9回に及ぶ意見交換会は、形式的な表示ルールの議論にとどまらず、物流を取り巻く構造的課題、労働者の処遇、消費者の意識変容といった複合的なテーマへと展開した。
消費者庁は、これらの意見を踏まえ、2023年12月、法規制には踏み切らず、「送料無料」表示の自主的な見直しを事業者に要請するという方針を打ち出した。今後は、表示のあり方に加えて、再配達削減やサステナブルな物流への投資、事業者・消費者の教育といった多方面での取組みが求められる。
「送料無料」表示への誤解と対立~ある通販会社の主張
某通販会社の社長は「送料無料表示」について次のような見解を述べている。
「まず論点がずれている。ユーザーは、送料無料と書かれていても、企業側が負担していることを理解している。宅配会社や配送業者がコストを無料で担っているとは思っていない」と指摘。その上で、「実際には、通販業界側へのけん制、あるいは難癖に過ぎなかったのではないか」と疑義を示した。
例として「金利手数料無料」という広告を挙げ、「これも企業のサービスとして提供しているものであり、クレジット会社を軽視しているわけではない。送料無料表示もまったく同じ性質のものである」と述べ、論点のすり替えであると批判した。
通販業界や通販協会にとって、「送料無料」の表示は販売戦略の一環であり、誤認を与えるものではないという立場が強い。一方で、トラック協会は、現場の負担や配送の価値が矮小化されることへの危機感をにじませている。
表示のあり方を巡るこの議論は、単なる言葉の選び方の問題ではなく、物流と小売りの関係性、そして消費者との信頼形成にかかわる構造的課題を内包している。今後の制度設計には、誤認防止とともに、現場の実態を丁寧にすり合わせる視点が求められる。
国土交通省では先月26日、物流の効率化に向けた「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」が立ち上がった。同検討会では、「置き配」の標準化に向けた議論が進められている。
1つの表示から始まった議論は、「誰のための物流か」という根本的な問いにまで踏み込んだが、多角的な側面から、持続可能な物流社会への転換が、これから本格的に試されていく。
(了)
【田代 宏】
関連記事:物流問題と送料無料表示を再考(1)
:物流問題と送料無料表示を再考(2)
:物流問題と送料無料表示を再考(3)
:物流問題と送料無料表示を再考(4)
:物流問題と送料無料表示を再考(5)
:物流問題と送料無料表示を再考(6)
:物流問題と送料無料表示を再考(7)