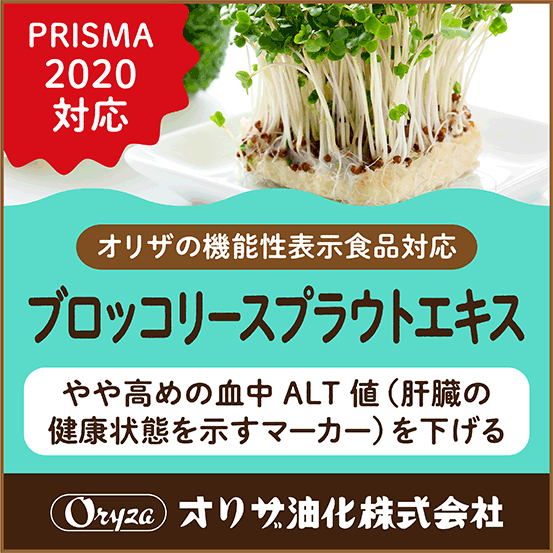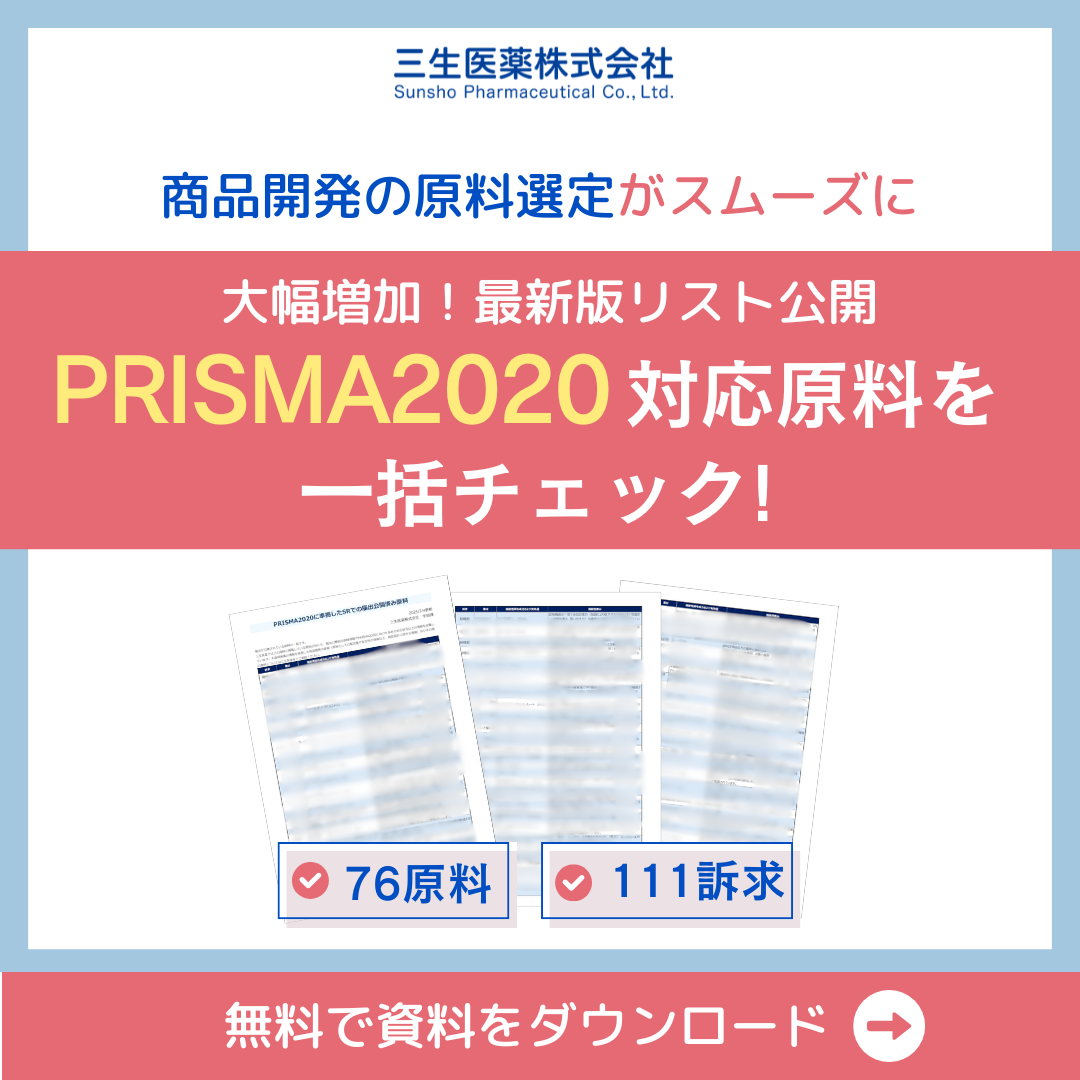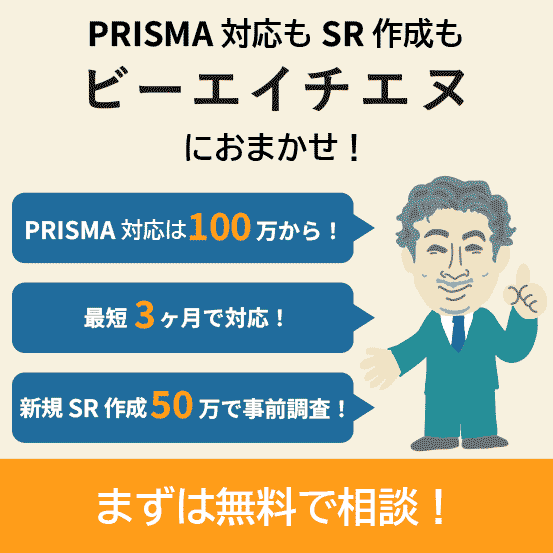法施行後3年、官民協議会節目の会合 消費者庁、第7回「取引DPF官民協議会」開催
消費者庁は13日、第7回「取引デジタルプラットフォーム官民協議会」(取引DPF官民協議会)を開催し、取引DPF消費者保護法の運用状況について議論した。事業者団体の取り組み状況、CtoC取引における「隠れB」問題、警察庁による知的侵害事件に対する取り組みなどについて討議。最後に議長による総括が行われた。
法施行3年の節目、運用状況を議論
最初の議題として、同法第3条「取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務」および第5条「販売業者等情報の開示請求」の運用状況、事業者の取り組みや改善点について議論。法に基づく事業者団体の取り組み、特にAmazonなど7社で設立したアジアインターネット日本連盟(JICA)やオンラインマーケットプレイス協議会(JOMC)の事例が紹介され、消費者団体からの要望や事業者の連絡先表示義務と消費者相談対応体制の改善状況を巡る意見交換が行われた。
CtoC取引「隠れB」問題に高まる懸念
次に、デジタルプラットフォームにおけるCtoC取引や隠れB(企業を偽装した個人)の問題について議論した。具体的なトピックとしては、消費者保護の観点から必要な法的対応、取引の透明性を確保するための措置、フリマサイトやオークションサイトでのトラブルの実態、そしてプラットフォーム提供者の責任について話し合われた。会議では、既存のガイドラインの適用や改正について多くの意見が交わされ、今後の施策や法的措置の必要性を検討した。
知財侵害事件の実態と警察の対応
最後に、警察庁からインターネットオークションやフリマサイト上で多発する知的財産権侵害事案への取り組みについて報告があった。利便性の向上とともに、インターネットを悪用した犯行が常態化しており、警察が検挙した商標法違反や著作権法違反事件の8割以上がインターネットを通じたものであることが示された。
具体的な事例としては、高級腕時計の偽造品販売を巡る詐欺・商標法違反事件や、人気キャラクターの海賊版プラモデルを販売していた著作権法違反事件が紹介された。いずれも消費者からの通報やサイバーパトロールによって発覚し、捜査により検挙されている。
警察は検挙活動に加え、不正商品撲滅の広報啓発にも力を入れており、不正商品対策協議会と連携したキャンペーンを各地で実施。本物と偽物を比較する展示やクイズなどを通じて、知的財産保護の意識向上に努めている。また、警察庁のホームページでも被害防止策や相談対応、補償制度の情報を提供している。
制度運用の成果と課題
消費者保護を目的とした取引DPF消費者保護法は、2022年5月1日の施行から3年が経過した。これを受け、京都大学大学院教授の依田高典議長がこれまでの運用状況について所見を述べ、今後の課題と展望を提示した。
同法制定当時、3つの主要な課題が指摘されていた。まず「プラットフォーム提供者の努力義務の実効性」、次に「行政による要請の実効性」、最後に「CtoC取引の場としてのプラットフォーム提供者の役割」――である。
努力義務の実効性については、出席した関係者の尽力により相当程度の取り組みが進展していると評価した。特に、販売業者の身元確認や、消費者からの苦情対応など、プラットフォーム提供者が取引の特性を踏まえた対応を講じている点は高く評価されるべきとした。一方で、こうした取り組み状況を消費者に分かりやすく開示するという観点では、なお課題が残されているとし、官民協議会で示された「開示イメージ」を活用した一層の推進が期待されると述べた。
行政による要請の実効性に関しては、法施行後に7件の要請が行われ、それに対し迅速な対応が取られていることが報告された。現時点では大きな問題は見られないが、製品安全性に関する改正製品安全4法との連携を視野に、今後の制度運用の強化が必要とした。
CtoC取引におけるプラットフォーム提供者の役割については、いわゆる「隠れB」問題が中心的な課題として指摘された。形式上は消費者であっても、実態は事業者である販売者が存在する可能性が高く、まずはこうした「隠れB」への対策強化が喫緊の課題であるとした。さらに、真に消費者による取引であっても、販売主体としての責任が問われにくいCtoC構造においては、プラットフォーム側の機能や責任が重要となる。こうした背景を踏まえ、ガイドラインの改正案が示されており、今後の正式な改定と、それに基づく実務の強化が求められると指摘した。
「今日の議論は出発点」依田議長が総括
依田議長は、これら一連の取り組みにより法制度全体として一定の成果が見られるとしつつも、通信販売の適正化と紛争解決を目的とする同法の趣旨を踏まえれば、引き続き措置の実施が必要であると強調した。とりわけ、CtoC取引と隠れB問題については、官民一体となって実態調査を進め、適切な制度設計と実務対応を図るべきであると訴えるとともに、事務局に対し、柔軟かつ真摯な対応を要請した。
官民協議会の発足から3年を経て一層の深化を迎える中、依田議長は「今日の議論は結論ではなく出発点である」と述べ、今後も率直な意見交換と実効的な規制が両立する場作りを進めていく決意を示した。次回開催は秋頃を予定している。
編集部では、会合で話し合われたポイントを16件のQ&Aにまとめてみた・・・(⇒つづきは会員専用記事閲覧ページへ)
Q1: 販売業者の連絡先が表示されていない、または表示されていても連絡がつかない場合の対策は?
A1: 消費者庁は特定商取引法に基づき、販売業者が連絡先を表示しないことは許されないとし、連絡がつかない事業者に対しても厳正な対応が必要としている。さらに、事業者に対して連絡先表示を義務付け、また連絡がつかないという事態を防ぐための体制を求められている。
Q2: 消費者が取引プラットフォームに対して情報開示を請求できるのはどのような状況か?
A2: 消費者が販売業者に1万円を超える金銭債権行使のため必要な情報が不明な場合、取引プラットフォーム提供者にその情報の開示を請求できる。ただし、開示請求件数は減少傾向にある。
Q3: 事業者の安全情報提供に関する取り組み状況は?
A3: Amazonなどの事業者が消費者に対してリコール情報を提供するためのプラットフォームを設けており、購入者へのパーソナライズメールによってリコール情報や商品の安全性に関する情報が提供されている。
Q4: 消費者団体が求める販売店表示義務についての意見は?
A4: 消費者団体(NACS)は販売店の連絡先表示が義務付けられるべきであり、実際に消費者が連絡を取れない状況に対して強い懸念を表明している。相談員の業務を阻害する事業者には、体制の整備が必要とされている。
Q5: 消費者の安全に配慮した積極的な情報提供は行われているか?
A5: Amazonなどのプラットフォーム事業者は、リコール情報の提供を強化しており、消費者庁や国民生活センターなどと連携し、購入後の安全使用方法に関する情報のメール配信を行う取り組みも進行中。
Q6: 特商法違反事業者への対応はどうなっているか?
A6: オンラインマーケットプレイス協議会は、こうした事業者へ厳正に対応する必要があるとし、具体的な対応策についての情報を会員間で情報交換することを表明した。また、消費者庁も違反があった際には通知するよう求めている。
Q7: CtoC取引での「隠れB(事業者)」について、どのように法的に対応する必要があるか?
A7: 「隠れB」とは、本来事業者として特商法に基づいた対応が必要であるにも関わらず、個人を装うことによって表示義務などを回避する脱法的行為を指す。これに対しては実際の事案に応じて個別具体的に判断し、必要に応じて消費者庁に相談し指針を受けることがでる。また、消費者庁はガイドラインに基づき、CtoC取引における事業者該当性について、特商法の観点から対応している。
Q8: CtoC取引プラットフォームにおける「場の提供者」としての責任は何でか?
A8: CtoC取引において、プラットフォームが唯一の事業者として場の提供を行っている以上、トラブルに対する監視責任や安全で安心な取引環境の整備が求められる。具体的には、問い合わせ内容の適正な対応、取引の監視、規定違反の防止、そしてエスクローサービスの導入による安全性の向上が求められている。
Q9: 「隠れB」問題についての調査はどのように行われたか?
A9: 「隠れB」問題に関する調査は、フリマサイトやオークションサイト、クラウドファンディングなどで販売業者該当性を持つ可能性のある者について行われた。調査は、出品数や継続性、提供する商材の内容などを基に進められ、これにより隠れBの比率がフリマサイトで約7割、オークションサイトで68%と判定された。
Q10: 消費生活相談で寄せられるCtoC取引関連の主なトラブル内容は何か?
A10: 相談の大部分は、商品の不具合や契約解除に関する問題、支払い方法や配送に関するトラブル。また、誹謗中傷などの問題もあり、それらの多くはプラットフォームを通じた適切な対応と問い合わせ対応の改善で解決が期待できるとされている。
Q11: 官民協力体制における取り組みの重要性は何か?
A11: 官民協力体制の下では、独自に定められた基準や制度を利用して、CtoC取引の実態を精査し、トラブル防止や消費者被害の減少に努めることができる。例えば、特定商取引法に基づくガイドラインの提供や、関係事業者との連携を通じて安全安心な取引環境を作り上げる努力が行われている。
Q12: インターネット上の取引において消費者が加害者にならないためにどのような取り組みが必要か?
A12: インターネット上の取引は比較的簡単に行えるため、知らずに犯罪を犯してしまう可能性がある。警察庁は被害者だけでなく加害者にならないよう、周知啓発の場での啓発を進めていくとしている。
Q13: 偽ブランド商品などが発見された場合、警察庁からプラットフォームへの情報提供はどのように行われるか?
A13: 警察庁はプラットフォームに対して個別に情報交換を行い、偽物についての情報を提供している。ただし、削除の要件についてはプラットフォーム側が判断するため、個別の事案により対応している。
Q14: 偽物かどうかの発見や判断はどのように行われているか?
A14: 警察庁は偽物の判断に関して権利者団体との連携を通じ、またインターネット上でのパトロールによる疑わしい事案を探し出して対応している。権利者と警察が連携して偽物かどうかを確認する。
Q15: 関税法による水際での差し止めの効果は?
A15: インターネット経由での不正商品対策として、関税法での水際での差し止めが有効な手段となるが、全ての偽物を止めることは難しいため、警察と関税関係者の連携が重要。
Q16: オークションやフリマサイトの加害者は一般消費者と事業者のどちらが多いか?
A16: 警察庁によると、統計はないものの、一般消費者や事業者の両方が加害者となる可能性がある。どちらであるかは事案によるため、一概には言えない。
【田代 宏】
当日の会議資料はこちら(消費者庁HPより)
関連記事:第6回取引DPF協議会、議事録公開 法改正のポイント、トラブルの事例分析など紹介
(冒頭の写真はイメージ)