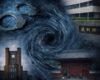令和6年産米の価格が高水準を維持 主要銘柄で前年比160%超の上昇も
「コメは買ったことがない」発言で辞任に追い込まれた2世議員・江藤拓前農林水産相の問題で揺れる農水省。同省が発表した令和6年(2024年)産米の「相対取引価格(25年4月分)」によれば、全国的に米の取引価格が前年に比べて大幅に上昇していることが明らかとなった。相対取引価格とは、全農などの集荷業者が卸に販売する時の価格のこと。全銘柄の平均価格は玄米60㎏あたり2万7,102円(税込)で、前年同月比161%となった。取引数量は9万3,889トンで、前月より44%減少している。
北海道・東北産米が価格上昇をけん引
特に北海道産「ななつぼし」は前年同月の1万5,655円から2万8,237円へと約1.8倍に上昇(179%)。「ゆめぴりか」や「きらら397」も同様に大きく値上がりしており、需給の逼迫が価格に反映されている。青森県の「まっしぐら」も前年より98%増で、3万602円に達した。
一方で、岩手・宮城・秋田などの東北地方でも価格上昇が顕著であり、例えば秋田県の「あきたこまち」は前年比176%、2万6,937円を記録した。
関東・甲信越も価格高騰が顕著
茨城県産「コシヒカリ」は4万883円と非常に高い値を付け、前年の1万5,235円から実に2.4倍(239%)の価格上昇となった。栃木や埼玉でも「コシヒカリ」や地域品種で160〜180%水準の上昇が見られる。
新潟県の「魚沼産コシヒカリ」は3万2,738円(前年比158%)と引き続き高値で推移しており、ブランド力が価格を下支えしていることがうかがえる。
西日本でも価格高止まり傾向
西日本地域でも、岡山・広島・福岡などで価格上昇が見られる。特に鹿児島県の「あきほなみ」は3万3,626円と前年(1万5,115円)比で222%の上昇率となった。福岡の「夢つくし」は2万6,880円で、前年比174%の水準となっている。
今期の相対取引価格の上昇は、24年産米の作柄に対する期待や流通在庫の偏在、政府備蓄米の放出状況など、複合的な要因によるものと考えられる。
スポット的な取引増が原因
農水省は取材に対し、「集荷量が少ないことが価格上昇の主な原因で、JAなどの集荷業者が“買い負け”ている状況にある」と価格高騰の理由を説明。つまり、通常の取引先以外でのスポット的な取引が増加しているのだという。例えば大手外食チェーンや大手スーパーによる”買い”の他にも、生産者が自分で販売するケースも増えており、従来の流通経路以外での取引が活発化しているのも米価高騰の要因を作っているようである。
【田代 宏】