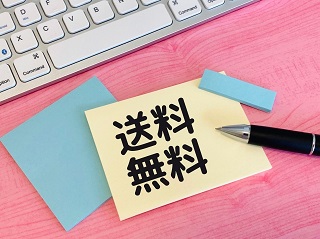物流問題と送料無料表示を再考(2) 【回顧ドキュメント】「送料無料表示」は本当に悪者か?
第2回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会は、2023年8月9日に開催された。登壇したのは、アジアインターネット日本連盟(AICJ)の他、アマゾンジャパン、メルカリ、ヤフーなどの大手プラットフォーマーを会員に持つ業界団体であり、いわば「送料無料」表示の恩恵を受けてきた側の代表と言える。
業界団体が反論「送料無料」見直しの目的が不透明と指摘
AICJの竹廣克氏はまず、政府が掲げた「物流革新に向けた政策パッケージ」の方向性には一定の理解を示し、再配達削減などの課題解決には連盟としても協力していく姿勢を明言した。その一方で、送料無料表示そのものに対しては「禁止すべきではない」と、慎重な姿勢を崩さなかった。
竹廣氏が強調したのは、「送料無料表示」の目的があいまいであるという点だった。表示の見直しが消費者の行動変容を促すためなのか、それとも消費者への価格転嫁を進めるためなのか、政策の立脚点が不透明であると指摘。「消費者が再配達を減らす意識を持つきっかけとしての表示変更」であるならば、周知・啓発の工夫が必要である一方で、「物流費の透明化」ならば費用構造の提示が必要だという主張である。
「送料無料」は合理的なビジネスモデル
また、「送料無料」という表示が、消費者に過度な誤認を与えているとの一部意見に対しても反論した。竹廣氏は「消費者の多くは、運送コストがかかっていることを理解している」とした上で、「送料無料」はあくまで販売事業者が費用を負担するというビジネスモデルの1つであると説明。その上で、仮に表示を見直すのであれば、「送料当社負担」や「送料込み」といった現実的かつ誤認を生みにくい表現への変更が望ましいとした。
さらに、連盟としては消費者への理解促進に積極的に協力する考えを示し、置き配やまとめ買いの促進、配送時間帯指定の柔軟化など、物流の効率化に寄与する企業努力を紹介。再配達の削減など、物流負担の軽減に向けた地道な取組が進行中であることも強調された。
この第2回意見交換会は、「送料無料」表示を単なる“悪”と位置づけるのではなく、それが成立している背景や、企業・消費者双方にとっての合理性について改めて問い直す機会となった。表示変更は単なる「言葉の修正」ではなく、価格政策、物流構造、そして消費者行動全体に波及するものであるという認識が共有されつつある。
議論はますます複雑性を帯び、次回には新経済連盟など別のネット業界団体も登場する。果たして「送料無料」は変わるべきなのか、それとも守るべきものなのか。
新経済連盟も参戦「表示の一律規制は危険」
2023年8月10日に開催された第3回意見交換会には、(一社)新経済連盟(JANE)が登壇した。同連盟は楽天グループをはじめとするEC事業者やテック系企業で構成されており、通販・物流に関わる政策に対して積極的な発言を行っている。
この日、連盟の片岡康子氏が強調したのは、「送料無料」表示があたかも物流業界の不利益の原因であるかのように単純化して論じられる傾向への懸念だった。片岡氏は、消費者はすでに「無料」であっても、送料はどこかが負担しているという現実を理解しているとした上で、送料無料表示をやめたからといって、再配達が減る、あるいは運送業者の待遇が改善するという明確な因果関係は立証されていないと主張した。
また、消費者ニーズの側面にも触れ、「送料無料」が価格比較の基準となっている現状を指摘。EC事業者としても、消費者の利便性を高めるための1つの工夫として表示を導入しているに過ぎず、それを一律に規制すれば、結果として価格の不透明化や購買行動の混乱を招きかねないとの懸念を示した。
連盟は、「物流2024年問題」の原因が販売事業者から消費者への送料費目の表示のあり方にあると言われると、本当にそうなのかと疑問を覚えるとし、「BtoB」と「BtoC」の話、運賃と送料の話が混同されており、表示1つで解決される問題ではないと指摘した。
消費者の理解と啓発こそが重要と強調
配送事業者の苦労には敬意を表する。物流問題のネックの1つが「再配達」にあることはEC事業者も理解している。非効率な再配達をいかになくしていくかが大事。配達者への「ありがとう」という言葉や感謝の気持ちを伝える消費者の行動変容を促すことが、「再配達」を減らすことにつながるのではないか、そういう1人ひとりの努力が大きな成果につながるのではないかと訴えている。
「〇〇円(送料込み)」や「送料は当社が負担」などの表現と送料無料表示を比較し、後者の方が分かりやすさを求めている消費者の購買行動に合っていることを、実際の計算式などを例に引きながら紹介している。
片岡氏は、「表示は表示でも、EC事業者を含め、関係事業者や行政による物流環境に関する消費者への周知・啓発コンテンツの表示を行ってはどうか」と提案。要するに、「敵を作って正義を振りかざすよりも、問題を共通課題として丁寧に向き合うことこそが必要だ」と訴えた。
意見交換会は、単なる立場の対立にとどまらず、各主体の現実的な認識の違いと価値観の擦り合わせへと展開していく。第4回では、より広い視点から「インターネット社会の安全性」と表示問題の接点が語られることになる。
(つづく)
【田代 宏】
関連記事:物流問題と送料無料表示を再考(1)
:物流問題と送料無料表示を再考(2)
:物流問題と送料無料表示を再考(3)
:物流問題と送料無料表示を再考(4)
:物流問題と送料無料表示を再考(5)
:物流問題と送料無料表示を再考(6)
:物流問題と送料無料表示を再考(7)
:物流問題と送料無料表示を再考(8)