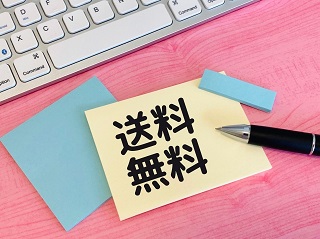物流問題と送料無料表示を再考(1) 【回顧ドキュメント】「送料無料」は本当に無料か?
消費者庁が設置した「『送料無料』表示の見直しに関する意見交換会」は、23年6月23日~11月8日まで9回にわたって開催。同年12月19日に物流「2024年問題」と「送料無料」表示の見直しについて、意見を取りまとめた。
会合では、ドライバー不足に悩む物流業界の実態が明らかになるとともに、送料無料表示に対する理解において、消費者と販売会社との間で大きな隔たりがあることも浮き彫りとなった。再配達の削減や置き配の推進など、改革へ向けた成果を得た一方、送料無料表示の見直しそれ自体については将来に課題を残した。とはいえ、同じ土俵で認識を共有することができたのは大きな成果の1つに違いない。
会合から1年余りが経った。9回に及ぶ意見交換会を改めて振り返りつつ、何が変わり、何が変わらなかったのか、そして今後、何を変えなければならないのかを共に考えたい。
「送料無料」表示に再考の機運
「送料無料」という言葉が、われわれの日常に浸透して久しい。ネット通販が日常化し、商品の価格に含まれるかたちで「送料込み」が常態化する中、その表示がもたらす影響を多角的に議論する場が設けられた。2023年6月23日、消費者庁は「第1回『送料無料』表示の見直しに関する意見交換会」を開催し、長年積み重なってきた課題に一石を投じた。
この会合は、同年6月2日に政府が発表した「物流革新に向けた政策パッケージ」を受けた施策の一環として実施されたものだ。背景には働き方改革の一環としての労働時間上限規制が「2024年問題」と呼ばれるトラックドライバーの労働時間規制強化による物流機能の低下リスクを生み出そうとしていた。ドライバー不足や再配達の増加が物流業界全体を圧迫する中、その根底に「送料無料」という表示が影響しているのではないか、という仮説から議論が始められたのである。
「2024年問題」と送料無料表示の接点
第1回目の意見交換会で登壇したのは、(公社)全日本トラック協会(全ト協)。副会長の馬渡雅敏氏は、「送料は運送の対価として収受するものであり、無料ではない」と明言し、「送料無料」という表示が消費者に誤解を与えていると訴えた。
「物流を軽く見ているような印象を与えてしまい、業界の地位が著しく低下している」、「再配達などでドライバーの業務負担は増しているのに、それが見えにくくなっている」、「送料無料という言葉は、業者の不都合な真実を隠すために使われている言葉。物流業界にしわ寄せが来ている」と現場の声を代弁した。
「言葉の問題」では済まされない構造的なゆがみ
トラック協会が問題視するのは単なる言葉の問題ではない。物流コストが「見えにくい」ことで、消費者の物流サービスへの敬意が薄れ、また荷主企業(通販事業者など)と物流会社の力関係が固定化され、運賃が適正に転嫁されにくくなる構造を作っているという。実際、営業損益率では、保有車両台数が10両未満の小規模事業者では軒並みマイナスとなっており、体力のある大手運送会社以外は慢性的な赤字体質が続いている。
この問題を受け、トラック協会ではこれまでにも「送料無料じゃありません」と銘打った啓発広告をインターネット(Yahoo!JAPAN)、NHKのWEBニュース、業界新聞などで配信、消費者への認知拡大を試みてきた。しかし効果は限定的だった。そこで今回の意見交換会を機に、消費者庁や関係省庁にも連携を呼びかけ、より体系的な対策を求めている。
「共通認識」構築への第一歩
第1回会合は、「送料無料」という表現の社会的意味を再考する出発点となった。物流は単なる流通ではなく、社会インフラである。その価値を正当に評価し、消費者・荷主・物流事業者が「共通認識」を持つことの必要性が初めて公的に共有された。「送料無料」ではなく、「送料は当社負担」、「送料○○円」など、送料の存在を明示する表現への変更案が提案された。
この場を皮切りに、「送料無料」表示に対する多面的な意見が今後も続々と提示されることになる。
同会合では、「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」の観点から、「送料無料」の文言が不当表示に当たるのではないかとの指摘もにわかに浮上し、議論の方向性として法規制の可能性も示唆されることとなるが、それはまだずっと後のことである。
(つづく)
【田代 宏】
過去9回の「意見交換会」の資料はこちら(消費者庁のHPより)
関連記事:物流問題と送料無料表示を再考(1)
:物流問題と送料無料表示を再考(2)
:物流問題と送料無料表示を再考(3)
:物流問題と送料無料表示を再考(4)
:物流問題と送料無料表示を再考(5)
:物流問題と送料無料表示を再考(6)
:物流問題と送料無料表示を再考(7)
:物流問題と送料無料表示を再考(8)