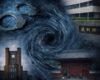偽サイト・偽物被害に注意喚起 東京都がSNS広告経由の被害実態を分析
インターネット通販の普及に伴い、SNSやメッセージアプリを経由して偽サイトへ誘導し、代金を支払ったにもかかわらず商品が届かない、または偽物が届くといった被害が急増している。東京都はこのほど、こうしたトラブルの相談件数や被害の特徴をまとめた調査結果を公表した。
相談件数は5年間で4倍以上に
東京都によると、SNSが関与した「偽サイト・偽物」に関する相談件数は、2019年度の449件から23年度には1,901件へと、約4.2倍に急増。24年度上半期も前年同期比115.2%のペースで増えており、引き続き高水準で推移している。
被害の中心は50代以上、女性が多数
年代別では、50代(249件)、60代(210件)、40代(204件)の順で多く、特に中高年層の被害が目立つ。性別では、全ての年度で女性の相談件数が男性を上回っている。職業別では「給与生活者」が59.9%と最多だった。
ブランド品やペット用品が狙われやすい
商品別では、紳士・婦人用洋服(185件)が最も多く、次いでペット用品やフィギュアなど(64件)、かばん(56件)が続いた。特に書籍・印刷物、音響・映像製品、医療用具といったカテゴリーで、前年からの相談件数が急増している。
被害手口も巧妙化 決済アプリを悪用した詐欺も横行
相談内容では、「返金」(606件)、「電子広告」(504件)、「詐欺」(477件)が上位を占めた。特に、商品の欠品を理由に「返金手続き」と称して決済アプリに誘導し、逆に送金させる手口が拡大。23年度の関連相談は前年度比60倍以上となり、24年度上半期も高止まりしている。
平均契約購入金額は約3万円。被害額は5万円未満が9割以上を占めるが、中には数十万円単位の被害も報告されている。
東京都は、偽サイトの特徴として「不自然な日本語表現」、「大幅な値引き」などを挙げ、「少しでも不審に思ったら購入を控える」、「会社情報をネット検索し、連絡が取れるか確認する」、「被害に気付いたらすぐにカード会社・金融機関に連絡する」、「決済アプリを使った返金手続き誘導は詐欺の可能性が高いため応じない」などの注意を呼び掛け、不審に思った場合は速やかに消費生活センターなどに相談することを推奨している。
発表資料はこちら(東京都のホームページより)