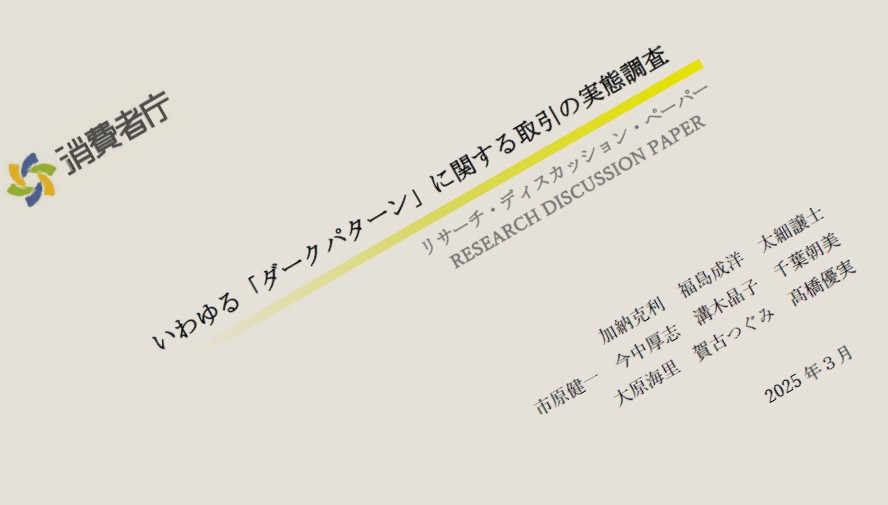ダークパターン巡る消費者被害調査 国際消費政策研究センターが報告書まとめる
消費者に不利益を与えるウェブサイトやアプリのデザインと操作画面、いわゆる「ダークパターン」に関する取引の実態調査が行われた。消費者庁の新未来創造戦略本部国際消費者政策研究センター(徳島市万代町)の研究者らにより「リサーチ・ディスカッション・ペーパー」がまとめられた。
同調査は、国内外で問題視されているダークパターンの実態を把握し、政策立案に資することを目的に行われたもの。消費生活相談(PIO-NET)や売上高上位のECサイトを対象に、実際のウェブ表示やユーザーインターフェース(UI)を精査した。
代表的ダークパターンを分類
ダークパターンとは、ウェブサイトやアプリの設計上の工夫によって、消費者に意図しない行動(購入・登録など)を取らせる手法で、「誘導・強制・欺瞞により選択を操作」、「事業者の利益に資するかたちで消費者の最善利益を損なう」などの特性を持ち、景品表示法や特商法などの国内法に抵触する場合もある。
報告書では、代表的なパターン分類を抽出している。
初期状態でオプションが選ばれており、ユーザーが気づかずに承諾する構造「事前選択(Preselection)(75サイト)」、推奨されたボタンを目立たせ、それ以外を見づらくして選択を誘導する「偽りの階層表示(False Hierarchy)(69サイト)」、利用者の声としてポジティブな意見を強調し、否定的情報を隠す「お客様の声(Testimonials)(56サイト)」、購入や問い合わせ時にアカウント作成を強制する「強制登録(Forced Registration)(45サイト)」、クッキー情報や個人情報の利用において、明確な同意を得ずに処理する「みなし同意(Deemed Consent)(22サイト)」――など。
ダークパターンの問題点
ダークパターンでは、「偽りの階層表示」と他の分類といった複数のダークパターンが組み合わさるケースが多く、複雑かつ巧妙な設計になっているという。
「未成年者の法定代理人同意確認」などが見られた他、「みなし同意」については、我が国の現行法上、直ちに違法あるいは不当とまでは言えないにしても、消費者の利益の擁護の観点からは検討の余地があると思われる。さらに、ウェブサイト上の表示ないしデザインで強調されている事項については、商品・サービスの内容や取引条件ではない事項であっても、消費者の意思決定の際に重要な影響を及ぼしている可能性があることがうかがえたとしている。
ダークパターンが問題とされるのは、消費者が「気付かないうちに」、「間違った判断を誘導される」ことにある。サブスクリプションの自動更新や、有料オプションへの誘導などがその典型例で、消費者の正しい判断を妨げ、意図しない契約・課金・情報提供につながる恐れがある。特に高齢者や教育水準の低い参加者において、ダークパターンにより、本来ならば行わない選択を行うことが明らかになっている。
未成年者の契約時における法定代理人の同意確認についても、「同意を得ている」とのチェックボックスがあり、みなし同意に至るリスクが懸念される。
実証実験の必要性と今後の分析課題
調査では、ダークパターンが消費者の意思決定にどのような影響を与えるのかを検証するための実証実験の必要性が強調されている。OECDなど海外の研究においても、複数のパターンを組み合わせることで、誘導効果が2倍以上になるなどのデータが示されており、実証的エビデンスの蓄積が急務としている。
境界が曖昧な「マーケティング」との線引き
また、説得的な広告と操作的なダークパターンの境界線が不明確であることも課題として指摘された。一部の表示は、事実であれば消費者に有益な情報となる一方、虚偽や誤認を招くものであれば、明確に不当表示として認定されるべきとし、不当性の評価にグラデーションを付けるという新たなアプローチが必要だと提言している。
事業者の倫理と自律的取組の推進
さらに、ダークパターンを利用することで消費者の信頼が損なわれ、事業者にとってもブランドイメージの低下というリスクがあることが示された。これを受け、今後は「信頼されるウェブサイト」としての認証制度や、情報の正確性を保証するガイドラインの策定など、倫理的対応を促す制度設計が求められるとし、事業者のモラルの重要性が指摘されている。
【田代 宏】