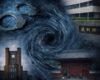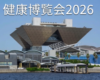食中毒、コロナ前と同水準に~厚労省 第3回厚生科学審議会食品衛生監視部会
厚生労働省は26日、「第3回厚生科学審議会食品衛生監視部会」を開催した。オンライン会議の様子をYouTubeでライブ配信した。今回の議題は①令和6年食中毒発生状況について、②令和7年度輸入食品監視指導計画(案)について、③食品ロス削減の推進についてなど。
昨年(2024年)の食中毒事例は、件数1,037件、患者数1万4,229人、死者3人となった。担当者は、コロナ前が概ね1,000件で推移していたことから、現状、コロナ前と同水準になってきている状況だと説明。
昨年発生した食中毒事例のうち、患者数が500人以上のものが1件で、大分県で湧き水を使用した食事によるノロウイルスの事例だった。また死者が出た事例は2件で、イヌサフランと毒キノコを食べた事例だった。
病因物質別にみると、昨年の事例ではアニサキスなどの寄生虫が年間を通じて確認される状況だった。また1月から4月に関しては、ノロウイルス食中毒の件数が増加。発生した施設別に見ると、飲食店による事例が最も多く、23年の47.9%と比較して52.8%と増加した。一方、家庭内での事例は、23年の11%と比較して10.4%とわずかに減少した。病因物質では、多い順にアニサキス、ノロウイルス、カンピオバクターで、アニサキスは23年の432件に対して昨年は330件、ノロウイルスは23年の164件から276件に増加したとしている。
食中毒に対する厚労省の主な対応
昨年発生した主な食中毒への厚生労働省の対応について説明があった。湧き水を原因とする食中毒への対応については、源泉での衛生的な管理ができなかったことによる事例紹介を通じ、一般衛生管理の徹底の普及啓発を行う。また、8月に集中して発生しているということもあり、自治体宛に通知する夏季一斉監視にも、使用水の管理について記載したいとしている。
ノロウイルス食中毒への対応について、多くは従業員からの二次感染という事例がある。従業員には普段から不顕性感染を想定した丁寧な手洗いの徹底、使い捨て手袋袋の使用などの普及啓発する。また、冬場の流行期前から従業員の検便検査にノロウイルスを加えることについて、年末一斉監視の通知に記載する。
ウエルシュ菌食中毒への対応について、特に高齢者施設や社会福祉施設などの大量調理施設に対して、調理後の温度管理や小分け保存、速やかな喫食について普及啓発を行う。加熱不十分な食肉等の提供による食中毒への対応については、脂肪注入等の加工肉や食鳥肉等の食肉の加熱の重要性について、消費者や食品事業者に対し引き続き普及啓発を行うとした。
輸入食品のモニタリング検査を計画的に実施
厚労省では、輸入食品の安全性を確保するために、食品衛生法の第23条に基づき、毎年度、次年度の4月からの監視指導計画、輸入食品の監視指導をどのように行っていくかという計画案を作成することとなっている。「令和7年度輸入食品監視指導計画(案)」については、1月20日から2月18日までの間、パブリックコメントを実施。さらに、2月3日と5日、東京と大阪でそれぞれ意見交換会を開催した。
23年度の輸入食品の状況は、輸入届の件数が約235万件、輸入重量が約3,000万トンだったが、これは、22年度に比べて若干減少している。24年の4月から9月までの上半期の速報値では、23年度に比較して若干増加しているという状況となっている。また、輸入食品に対して、モニタリング検査や検査命令等の監視指導、輸出国における対策として二国間協議や担当官による現地調査等に基づき監視指導を行った。
25年度の重点項目として、モニタリング検査を計画的に実施すると説明。モニタリング検査とは、輸入される食品が食品衛生法に合致しているかどうかということを幅広くトレンドを見るために実施している検査で、前年度同様、約10万件を実施するという計画案となっている。
対象品目や検査項目は、過去の違反事例や海外での健康被害の発生状況等を踏まえて調整し、効率的な監視が実施できるように努めるとしている。輸入食品の制度やこの監視指導の状況については、引き続き事業者や消費者への丁寧なリスクコミュニケーション、検疫所で監視指導にあたる全国の食品衛生監視員の資質向上と合わせて、輸入食品の安全性確保に引き続き取り組むとした。
食べ残しの持ち帰りを促進
2030年度までに2000年度比で食品ロス量を半減させる目標達成に向けて、22年12月22日に開催された食品ロス削減推進会議において、「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」が取りまとめられた。同パッケージに盛り込まれた施策を中心に、関係府省庁が地方公共団体や関係民間団体とも連携しながら来年度中に着実に実行し、来年度中に予定している「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」(20年3月31日閣議決定)の見直しに反映させるとしている。
同パッケージに基づき、厚労省食品監視安全課では、飲食店における食べ残しの持ち帰りを促進するにあたり、昨年の7月から12月にかけ検討会を開催。消費者庁と連名で、食べ残しの持ち帰り促進ガイドラインを昨年12月25日に作成した。ガイドラインに基づき、注意事項を十分に理解して自己責任での持ち帰りをすることにより食品ロス削減につなげることについて、関係省庁と連携して普及啓発を進めるとしている。
これについて戸部依子委員((公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)会員)が、「食中毒事例が発生した際、それが飲食店などの施設での発生なのか、それとも持ち帰り食品によるものなのか、また持ち帰り食品の提供状況、持ち帰った消費者の保存状況によるものなのか分けて分析する必要がある」と意見を述べた。
これに対して厚労省担当者は、「食中毒事例が発生した際、持ち帰り食品に絞って調査をするわけではなく、これまで食べたものについて調査を行い判断することになる。調査の結果、例えば調理時点など明らかに事業者に非があれば事業者の責任が問われるが、例えば、持ち帰り後、長時間常温に放置したなど消費者側に原因があれば、消費者側の非になるということになる。分析に当たり、ガイドラインに基づき、消費者に対しても保健所の調査に協力してもらうなど周知徹底が必要」と指摘した。
FFC健康被害情報対応小委員会、「生鮮食品を除く」削除
機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会では、各都道府県から収集する機能性表示食品等の健康被害情報については、生鮮食品である機能性表示食品などの健康被害情報についても収集の対象としている。それを踏まえ、「機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会の設置について」を一部改正した。
具体的には、「生鮮食品を除く」という記述を削除。「機能性表示食品の中には生鮮食品もあるということを踏まえ、それを含めて検討するということの変更」とした。
次回の厚生科学審議会食品衛生監視部会開催は、現在調整中。
【藤田勇一】
(冒頭の写真:YouTube(厚労省専用チャンネルMHLWchannel)でライブ配信した)