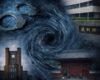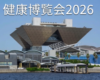有事食料法の基本方針を公示 「困難事態」の基準示す、3月5日までパブコメ募集
農林水産省は4日、「食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針案」を公示した。来月5日まで、同方針についてパブリックコメントを募集する。
施行へ向け基本方針策定へ
食料供給困難事態対策法は昨年5月23日に第213回通常国会で成立し、6月21日に公布された。今年4月1日から施行されることが決まっている。
同法第3条において、「食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針」(基本方針)を定めることとされており、同対策の実施に関する基本的な方向や推進の体制および方法の他、そもそも供給困難事態とは何かを示す「基準」を設けることが定められている。
基準は特定食料が2割以上減少
同対策法では、食料供給困難事態について、「食料供給困難兆候」と「食料供給困難事態」の大きく2つに分けている。そのいずれにおいても、「国内における単一または複数の品目の特定食料の供給が平年と比べて全国的に2割以上減少するかその恐れがある場合」を基準としている。
そして「――困難事態」とみなされる状況を、「特定食料や当該特定食料を原材料とする食品の価格の高騰、事業者や消費者の買占め、買い急ぎ等の調達・購買行動の混乱等が生じ、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に支障が生じたと認められる場合」と定めている。一方、「――困難兆候」は、このような対策を講じなければ、「食料供給困難事態の発生を未然に防止することが困難と認められる場合」と規定する。
【解 説】
戦争や自然災害によって引き起こされる食糧危機に備えて、「米穀」、「小麦」、「大豆」などの国が定める特定食料をキープしなさいという同法を巡っては、農業従事者から強い反対も起きている。
「コメ作りは利益率が低い。ただでさえ低い自給率がさらに落ちる」、「外資が入ってくることで日本の農家がなくなる」、「農業を知らない人間が作った絵空事」、「バカにするなと言いたい。いざ有事となって国民が困ったら、全国の農家は精一杯増産のためにやらせてもらう」
今年1月22日、同法に対するパブリックコメントの締め切り前日には、島根県でトラクター22台が行進するデモも起きた。
食料供給困難事態対策法は通称「有事食料法」とも呼ばれている。同法では、特定食料が2割以上減少した時に、事業者に対して国からの要請が指示に切り替わり、計画を出すことが求められる。そして、生産計画で全体量が不足すれば、今度は増産が指示され、増産計画を出さなかったら罰則、罰金が科せられる。さらに計画通りに生産しなかったら公表される、という社会的制裁が加えられる。同法の改正を巡り、昨年5月9日に開かれた第213回国会「衆議院 農林水産委員会」では、平時の食料確保の施策こそが重要ではないかとの議論が行われた。
参考人として招致された生産者からは、「消費者を含めて、一次産業を担っている人たちが社会からリスペクトされて、胸を張っていけるような仕事で初めて、有事になった時に、よし、それなら皆さんの期待に応えてやるぞということが成り立つと思うので、やはり平時が問われていると思う」との熱い思いが語られた。
我が国の食料自給率は38%(カロリーベース)と低水準、コメはほぼ自給可能だが、小麦・大豆・畜産物は輸入に依存している。漁業の生産量は減少し、自給率57%に低下。農業従事者の高齢化(平均年齢68.4歳)と耕作放棄地の増加が深刻化している。これに対して政府は自給率向上に向けて、スマート農業の推進、国産飼料の活用促進、休耕地の活用と企業参入の促進、持続可能な漁業・養殖業の強化、国産小麦・大豆の生産拡大――などを推進しているが、目に見える効果は表れているのだろうか。それに加えて、輸入リスク(戦争・気候変動・円安)への対応も課題とされており、今回の新法制定に踏み切ったと言われている。
【田代 宏】
パブコメの募集はこちら(e-GOVより)