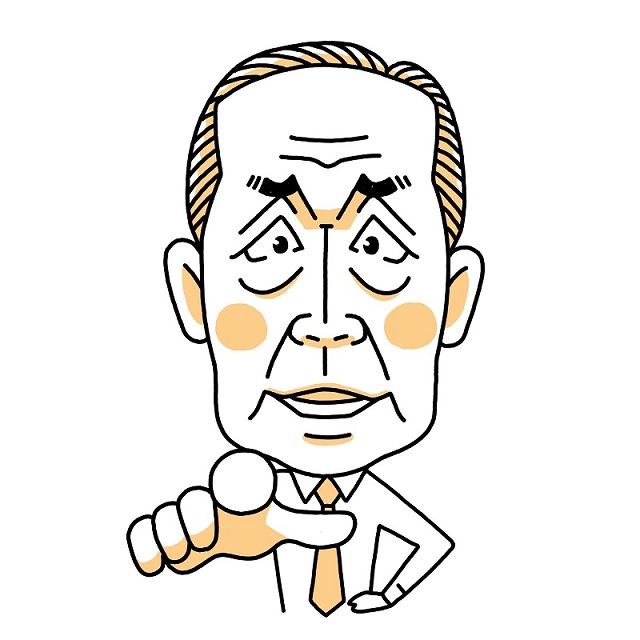農水省、備蓄米運用の見直し決定 【寄稿】消えたコメ17万トンの行方は?
元食品表示Gメン 中村 啓一
依然としてコメの高値は続いている。そのような中、17万トンにも及ぶコメが行方不明になっているという。そこで政府は備蓄米運用の見直しを決めた。1993年(平成5年)に我が国を襲った平成の米騒動当時、農水省「消費者の部屋」の責任者として連日、消費者からの苦情に対応した元食品表示Gメンの中村啓一氏がコメ事情を解説する(編集部)
政府が備蓄米放出へ方針転換
農林水産省は、1月31日に開いた「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」で「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」を変更し、深刻な不作や災害時などに限って市場に放出するとしていた備蓄米をコメの流通が滞っていると判断した場合にも放出できるよう見直しを決定した。
備蓄運営の基本的な考え方を示した基本指針は、従来の深刻な不作や災害時に加え、「主食用米の円滑な流通に支障が生じる場合であって、農林水産大臣が必要と認めるときは、備蓄の円滑な運営を阻害しない範囲で、買受資格者に対する主食用としての備蓄米の売渡しを、政府が当該買受資格者から一定期間後(1年以内)に当該備蓄米と同等同量の国内産米の買入れを行うとの条件を付した上で、できることとします(買戻し条件付売渡し)」としている。
昨年夏から高騰したコメの価格も新米が出回れば落ち着くとしていたが、年を越しても収まる気配のないことから、追い込まれたかたちで農水省が避けていた「備蓄米放出による民間流通の価格への影響」を期待した運用の見直しとなってしまった。
見直し案には疑問点も
安定供給のため備蓄米を機動的に活用することは歓迎されるが、「放出した同等同量を1年以内に買い戻す」とする放出の条件には疑問を持たざるを得ない。放出後の需給事情に関係なく期限を切った買戻しは放出の効果を薄める懸念もある。基本指針は100万トン程度を現行の適正水準として、需給状況を踏まえつつ必要な数量の米穀を保有するとしており、円滑な流通のため放出したコメについても期限で縛ることなく流通の状況を見極めながら順次買い戻すべきではないだろうか。
ウェルネスデイリーニュースで提言
そもそも、昨年夏に有効な対策が講じられていれば、今日の状態は避けられたかもしれない。筆者は昨年8月の時点で「必要があればいつでも備蓄米を放出する」という政府の姿勢を国民に示すべきとウェルネスデイリーニュースで提言している。
昨年は猛暑による品質の低下などからコメが不足気味とされていた中、8月8日に宮崎で最大震度6弱の地震が発生。気象庁が「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表したことから、家庭内備蓄用の水や食料など災害に備えた仮需が発生し、コメも店頭の棚から消える事態となった。このため、備蓄米の放出を求める要望が出たが、農水省は流通に影響を与えるとして否定し、新米が出回れば改善するとしていた。
巨大地震注意の情報下で災害時に準じた対応も可能ではなかったか。少なくとも国として消費者の不安を抑える何らかの対応(メッセージ)が必要ではなかったか。スーパーでコメが買えない状況下で備蓄米放出の要請を農水大臣が否定したことから、不安を覚えた消費者の買い急ぎをあおることとなり、結果として「品薄商法」と同じ現象を呼び込んでしまったのではないかと考えられる。
消費者の入手ルートは多様化
筆者は、平成米騒動といわれた1993年の米不足時に農水省の消費者窓口「消費者の部屋」を担当していたが、当時は高値を提示したフリーの業者による農家での庭先取引や、生産者が親類や知人へ送る縁故米の増加が本来の流通に影響して米不足に拍車をかけているといわれていた。
今回も同様の現象が起きているのではないか。統計から試算すると、少なくともコメ約17万トン(茶わん26億杯分)が市場に出回らず「行方不明」になっており、これが価格高騰につながっているといわれている。産直やふるさと納税返礼品など消費者のコメの入手ルートは平成米騒動当時とは比較にならないほど多様化しており、農水省も分散している在庫の状況を把握できていないようだ。
長年にわたり続けられてきたコメの供給を抑えて、米価を維持する政策も見直しが求められている。コメの生産を調整するために都道府県ごとの生産量を決めた減反政策は2018年に廃止されたが、コメから他の作物に転作する生産者への補助金など生産抑制の仕組みは継続されている。農水省は同日、27年度からのコメ政策を見直すとの方針も示しており、審議会での議論を注視したい。
消費者の理解と支援も不可欠
消費者にも理解を求めたい。コメに限らず、昨年夏の記録的な猛暑や10月の天候不順、さらに12月の低温と水不足などの影響により、キャベツや白菜などの農産物も高騰し家計を圧迫しているが、収穫が天候に左右されやすいのは農業の宿命だ。また、農業生産の継続を可能とするためには生産者の経営を助ける必要もある。
国内で安定した食料供給を維持するためには、農業経営の規模拡大や新技術の普及など、生産現場の努力とともに農業に対する消費者の理解と支援が不可欠だ。
<筆者プロフィール>
1968年農林水産省入省。その後、近畿農政局 企画調整部 消費生活課長、消費・安全局 表示・規格課 食品表示・規格監視室長、総合食料局 食糧部 消費流通課長などを経て2011年に退官。著書:『食品偽装・起こさないためのケーススタディ』共著(ぎょうせい)2008年、『食品偽装との闘い』(文芸社)2012年など。
「元食品表示Gメンの事件簿シリーズ」はこちら