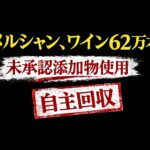神代から令和まで健康食品のルーツを探る~歴史から見えてくる課題は何か?(23)
東京大学名誉教授。(公財)食の安全・安心財団理事長。唐木英明
<『メディスキン』にFOOCOMが疑義>
『メディスキン』は米由来グルコシルセラミドを含む製品で、肌の保湿力を高め、肌の調子を整える機能があるとして機能性食品制度が発足した2015年4月に届け出が行われ、受理された。この製品の機能性を示す届出情報に不備があるとして6月に消費者庁に疑義情報を提出したのが(一社)Food Communication Compass(FOOCOM)で、その内容は以下のようなものだった。
メディスキンに含まれる米由来グルコシルセラミドの機能性を示す根拠として8つの論文を届け出ているが、それらの論文で使用しているグルコシルセラミドの起源は米だけでなく、コンニャク、トウモロコシ、ビート、パイナップルなど多岐にわたっている。米以外の植物から得られたグルコシルセラミドの効果が、米由来のものと同一と言えるのか、その根拠が書かれていないのはおかしい、というものだった。
<「同一性」か「同等性」か>
これに対して『メディスキン』の販売企業は「事実無根であり、営業上の不利益を被っているため、直ちに申し入れを撤回し、ホームページなどからの削除と謝罪を求める」と主張し、さらに消費者庁ガイドラインでは「同一性」ではなく「同等性」を求めていると反論した。
FOOCOMは、「5種類の作物のグルコシルセラミドの構造には多少の違いがあるが、それらの有効性は同じであること、さらに、同じ作用機序で効果を発揮することが科学的根拠に基づいて考察されなければ、ガイドラインを満たさない」と再反論し、販売企業は届け出資料の同等性に関する記載の一部が不十分であったことを認めて、7月に届け出資料の修正を行い、この件は終了した。
<事後チェック機能が支える制度>
FOOCOMのグルコシルセラミドに関する主張も重要だが、さらに重要な指摘は次の点である。
「機能性表示食品には事前チェックの仕組みはなく、届出後の事後チェックが重要であることは、消費者庁の国会答弁や長官の記者会見などで、繰り返し述べられています。消費者庁は、監視のために消費者等などからの疑義情報を求めています。そして、その精査を自分たちが実行し、要件を満たしていないと判断すれば撤回を求めることで監視を行う、と明言しているのです。私たちは、この考え方に則って、疑義情報を消費者庁に提出しました。それが妥当であるのかないのかの判断は消費者庁が行うものであり、私たちの活動は適正な消費者活動です」
機能性表示食品制度の発足にかかわった筆者は事後チェックのシステムを構築しない限り機能性表示食品に対する消費者の信頼は得られないと考えていたのだが、制度発足後に起こったこの制度に対する批判を見てその感をますます強くし、外部評価機関の立ち上げに努力することになる。
(つづく)
<プロフィール>
1964年東京大学農学部獣医学科卒。農学博士、獣医師。東京大学農学部助手、同助教授、テキサス大学ダラス医学研究所研究員などを経て東京大学農学部教授、東京大学アイソトープ総合センターセンター長などを歴任。2008〜11年日本学術会議副会長。11〜13年倉敷芸術科学大学学長。専門は薬理学、毒性学、食品安全、リスクコミュニケーション。