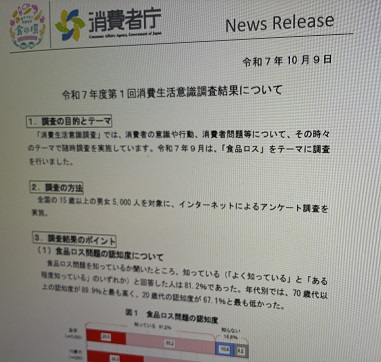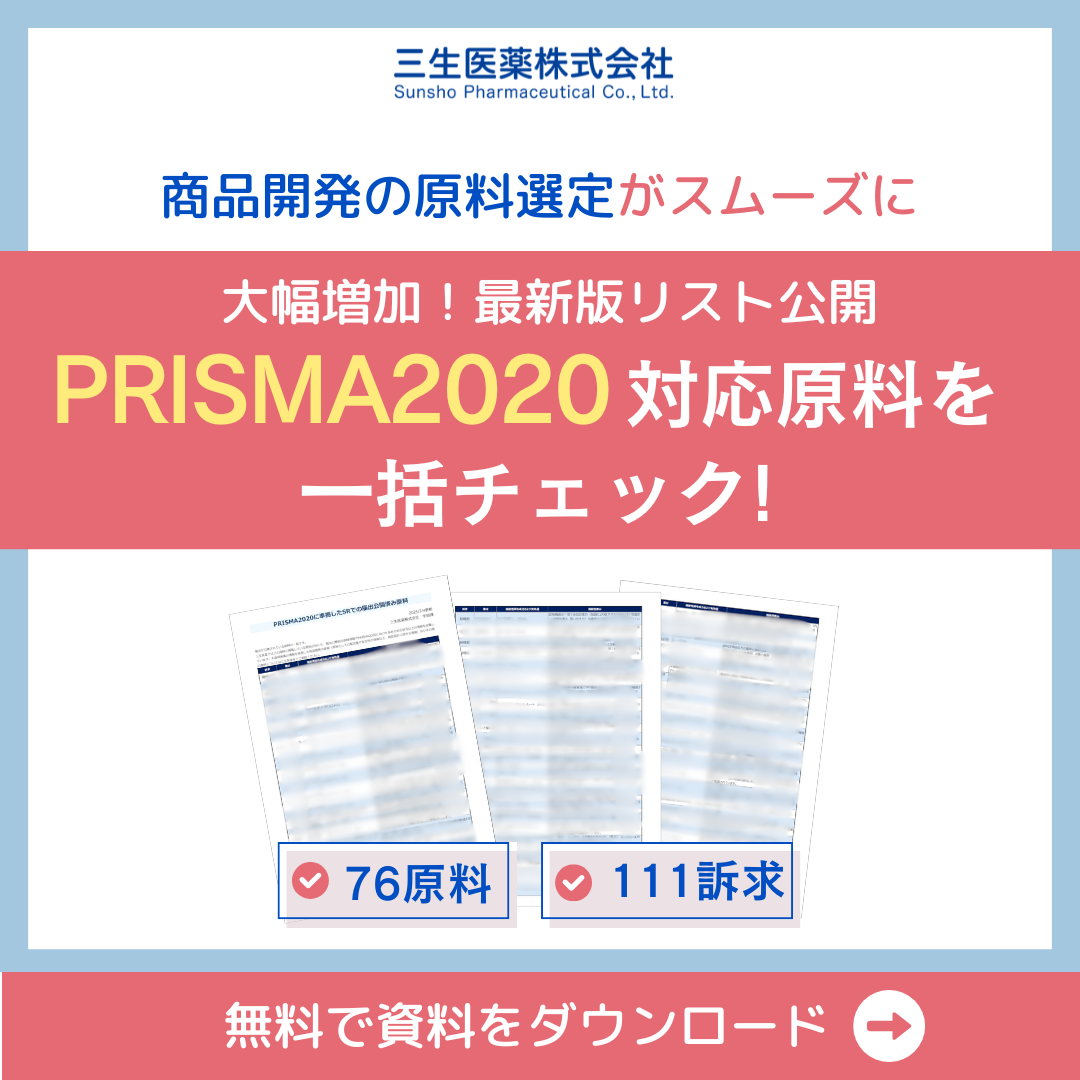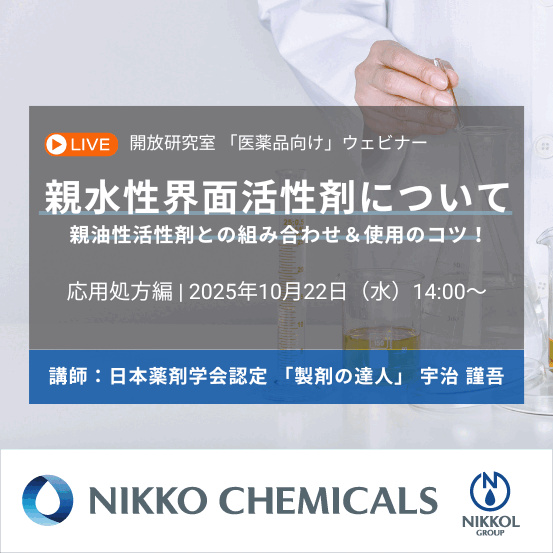消費者庁、「食品ロス」テーマに調査 認知度8割超、若年層に低い傾向
消費者庁は9日、2025年度(令和7年度)における「第1回消費生活意識調査」の結果を公表した。「食品ロス」をテーマに、全国の15歳以上の男女5,000人を対象にインターネットによるアンケート調査を実施した。
食品ロスの認知度は81.2%
食品ロス問題を「よく知っている」または「ある程度知っている」と回答した人は81.2%だった。年代別では、70歳代以上が89.9%と最も高く、20歳代が67.1%と最も低かった。過去の調査結果と比較すると、2022年度(令和4年度)81.1%、23年度(同5年度)80.9%、24年度同6年度)78.9%と、ほぼ横ばいの傾向を示している。
賞味期限・消費期限の理解は7割超
賞味期限・消費期限を「理解している」と回答した人は76.6%だった。理解度は22年度78.0%、23年度77.2%、24年度75.2%と微減傾向にある。
また、食品を購入する際に「消費予定に関係なく、なるべく期限の長い商品を購入している」と回答した人は44.9%だった。こちらも過去の調査と比較すると、22年度47.3%、23年度45.6%、24年度46.3%と同様の水準で推移している。
余った食品の寄附、「安全管理への配慮」が鍵
家庭で余った食品を寄附するための効果的な取り組みとして、「寄附先が食品の安全に配慮し、適切な温度管理や衛生管理をしている」と回答した人が31.9%で最も多かった。次いで「回収ボックスの設置」(29.5%)が挙げられた。一方で、「寄附をしたくない」と回答した人は34.5%であった。年代別では、60歳代が寄附に肯定的な傾向を示した。
外食時の残食、「持ち帰らない」理由も多様
直近1年間に飲食店で食べきれなかった経験については、「食べきれなかったことはない」との回答が44.5%で最も多かった。食べ残しを持ち帰らなかった理由としては、「持ち帰るという発想自体がなかった」が8.7%と最も高く、「衛生的に気になる」(8.5%)、「持ち帰ってまで食べる気にならない」(6.8%)などが続いた。
認知と実践の両立は77.2%
食品ロス問題を認知し、かつ削減に取り組んでいる人の割合は77.2%だった。政府は「第2次食品ロス削減推進基本方針」(令和7年3月閣議決定)において、同割合を80%とする目標を掲げている。
【編集部】
発表資料はこちら(消費者庁HPより)