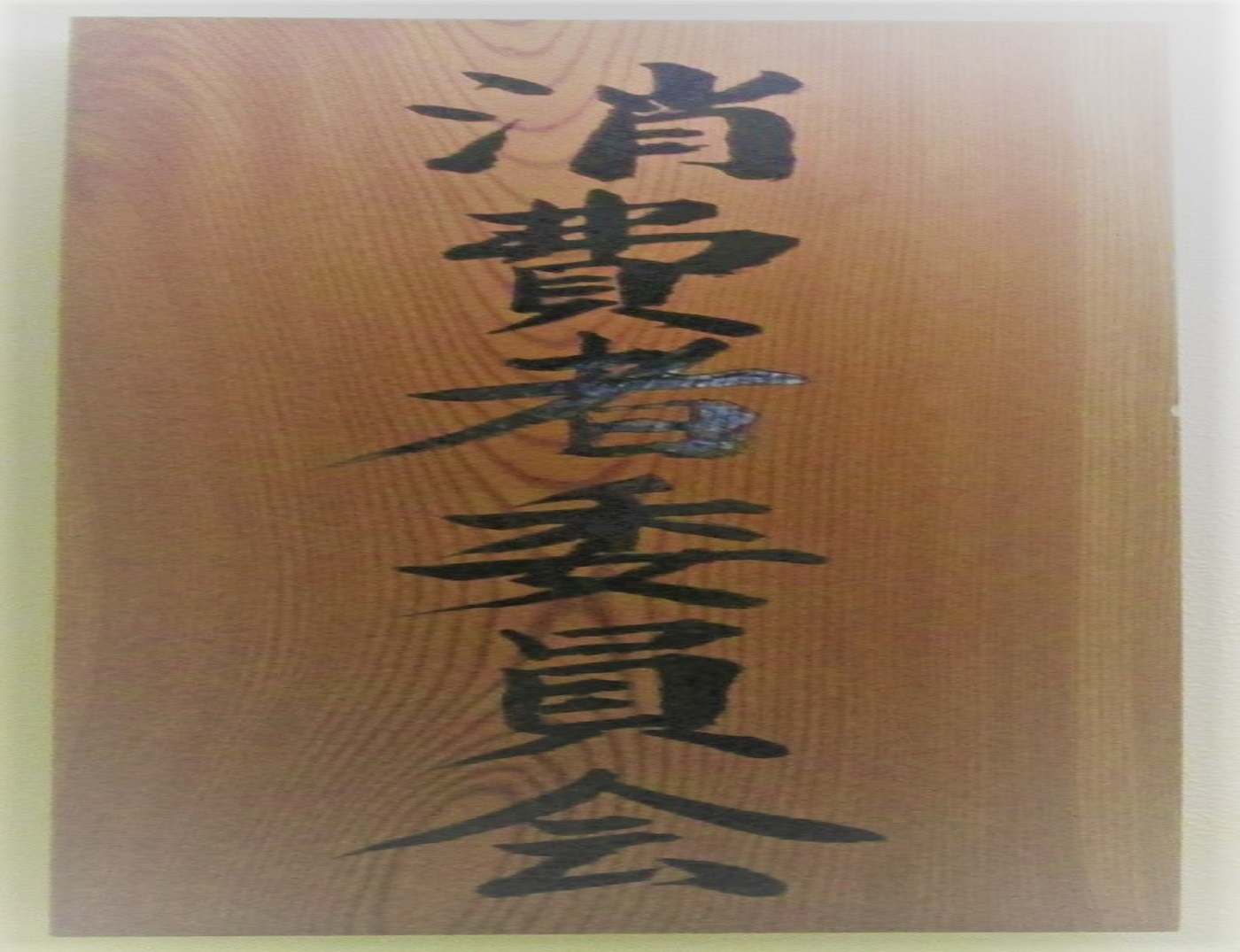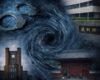国立栄研DBトラブル、栄研に伝える? 消費者委第72回表示部会エピソード
きのう20日、消費者委員会が第72回食品表示部会を開催、紅麹サプリ事件を受けた消費者庁の食品表示基準改正を巡り議論した。
その中で、(一社)Food Communication Compass代表の森田満樹委員が国立健康・栄養研究所(国立栄研)のデータベースが休止している問題を取り上げた。(消費者委YouTube1時間14分~)
国立栄研DBは消費者庁のセカンドオピニオン事業だった
6月9日午後にNHKが報道したニュースを紹介し、同データベースが有効性情報しか公開していない点を指摘。「機能性しか読めない。機能性は読める。こんなにいいことばっかりなのに、肝心の安全性のデータが読めないというような状態が長く続いている」と問題視した。
同委員は、「これはそもそも、消費者庁がセカンドオピニオン事業として安全性情報を参考にするようにということで消費者庁のウェブサイトにもそうやって案内がある。私もいろいろなところで、このサイトはとても役に立ちますよということで消費生活センターとかでお話ししている。安全性はここで見ることができるので、自分の気になる方はその成分をちょっと調べてみましょうと。消費者庁もこれは事業として推奨していたと思うので、できるだけ早く安全性情報を見られるように進めていただきたい」と述べた。
これは、第5回「機能性表示食品を巡る検討会」のヒアリングで同委員が述べた意見を補足したもの。同部会の事前意見としても森田委員が述べており、それに対して消費者庁は「ご意見として承る。国立健康・栄養研究所に伝える」と書面で回答している。ただし、今回の部会では消費者庁は森田氏のこの発言を無視した。
実はこの問題は、ウェルネスデイリーニュース編集部が継続的に報じてきた問題でもある。消費者庁は編集部の問いに対して、「事業者固有の問題なので当庁は関与しない」と一貫して回答している。にもかかわらず、同庁はどういう意図で森田委員に対し、「伝える」と答えたのか? 国立栄研とナチュラルメディシン・データベース、国立栄研と消費者庁との関係についてなんら説明がなく、口先だけのその場しのぎの回答としか思われない。
GMPは原材料にかかるのか?かからないのか?
また同部会では、消費者委員会と消費者庁の間でかなりぎりぎりのやり取りが行われた。原材料GMPをめぐる議論において、消費者庁は食品表示企画課保健表示室の今川正紀室長の他、与田学審議官、終盤には清水正雄食品表示課長も参戦。その際、「消費者委員会委員のモヤモヤ」(消費者庁)を解消するためとして、3者が躍起になって答弁している姿が印象的だった。
原材料の製造にGMPを義務化するかどうかという議論について、行政用語で表面的な説明を続けていた今川室長だったが、そのうち依田審議官が参戦。告示化について詳しく説明した。令和6年3月11日付発出の食品審査基準課長通知「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針(ガイドライン)」及び「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)」において、最終製品におけるGMPについて書いているのが「別添2」、原材料の自主点検と製品設計に関するガイドラインが「別添1」で「これらを両方告示とするため表示責任者(届出者)はこの両方に責任を負う」と説明。「原料メーカーにGMPの義務をかけろとは同通知では言っていない。あくまで自主点検をしろと。その趣旨をそのまま告示にしたい。具体的には、原材料に関しては原材料メーカーが自主点検をしなさいという要件はかかる。GMPという言い方をしていないだけで義務はある。また、届出者はそういうことを求める最終製品の製造者から届出者の責任において製品を調達しなければならないということになる」と解説した。説明を聞いた上で原材料メーカーにGMPはかからないが実質かかるという点が理解しづらい。「(以後の審議で)資料化して説明していただきたい」と繰り返す消費者委員会の委員。そして最後に、清水課長が登場してこう述べたのだ(YouTube1時間50分あたりから)。
「小林問題は特殊な問題、現実とは違う」(清水課長)
「今日のご議論ですと、どうしても小林製薬のあの商品が念頭にありますので、紅麹があって、それをあの形にしてっていうところになってると思いますけれども」と切り出した。一般的には複数のいろいろな原材料から1つの製品を作るというのがほとんどの場合。その原材料そのものも機能性関与成分だけではなく、いろいろな材料から作っているというのが一般的だと前置きし、「あの商品を念頭に置いてだけ考えると、現実とだいぶ違うことになっちゃうかなという部分もある」と述べた。
そうだろうか? 同表示部会もそうだが、「機能性表示食品を巡る検討会」をはじめとした一連の議論は、小林製薬の紅麹サプリ事件を受けてのことである。このような問題を再び起こさないための対策を有識者で重ねて議論している場で、この問題は特殊な問題だとする同課長のこの発言には驚いた。関係者からも、このような発言は今回被害を受けた人に対しても不謹慎で、不適切な発言という声が上がっている。
原材料GMPを巡る議論について関係者は、「原材料のGMP以外で、例えば全成分検査によって受入れ検査を自力で行い、安全性が確認されている製品標準と同一性を点検せよ」などと具体的な方法を示すべき。消費者委員会は、GMPが義務化ではないという理解はした。しかし方法論はどうなのか。そこを放置するのかどうか、条文を見るまでは見解を保留するということではないか」と述べている。
【田代 宏】
関連記事:NHKが報道、国立栄研の安全性情報DB 9日午後のニュースで閉鎖を問題視
:機能性表示食品、R6年通知が急浮上 制度見直しで法令化、原材料の安全性自主点検も要件に