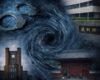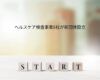培養肉で生食用レバーの販売が可能に? めざす会が第9回勉強会、テーマは「人工肉」
22日、衆議院予算委員会で岸田首相は、肉や魚の細胞を培養して育てる「細胞農業」の産業育成に乗り出す考えを示した。
今後、培養肉などの新たな市場形成に期待がかかる中、食の信頼向上をめざす会(唐木英明代表)は同日、第9回ZOOM情報交換会を開催。「人工肉とは何か」をテーマに、東北大学大学院助教で日本細胞農業協会代表理事の五十嵐圭介氏と、NUProtein㈱研究員の板谷知健氏を講師に招へいした。
代替タンパク質の文化的意義と課題
五十嵐氏は、「新食材“代替タンパク質”はなぜ求められているのか」と題して講演。統計資料を示しながら、2100年頃から世界の人口が減少に向かう中でも、中所得国では肉類の需要が大きく増加すると説明。気候変動による食料生産への影響などに対して、畜産物以外のタンパク源の摂取が求められるとした。期待されるタンパク源として、大豆やえんどう豆・アーモンドなどの植物系、キノコ類の真菌系、ユーグレナなどの藻類系、コオロギなどの昆虫系、酵母などの微生物系に加えて、食肉・乳卵を新たな方法で生産する細胞培養が考えられるとし、さまざまな代替食品を紹介した。
また、効率的・工業的な食糧生産を目指す「細胞農業」について、「国」、「宗教」、「社会倫理」などの違いを挙げ、文化的意義と課題を提起した。
同氏は、「代替タンパク質によって食材の選択肢が増え、個々人がそれぞれの考え方や主義主張に基づいて食べるものを選ぶことで、より豊かな食の未来が実現される」と述べた。
培養肉とは何か?
板谷氏は、代替食を製造するために、細胞を使ったタンパク質合成試薬の開発などに携わっている。同氏は、人口増加、飼料の高騰、飼育スペースの拡大、環境汚染、アニマルウェルフェアの広がりなどの要因を挙げ、培養肉のニーズがなぜ高まって来たのかその背景を説明し、培養肉の製造法やコスト、現在の市場動向などを詳しく紹介した。
また、培養肉の製造に重要なウシ胎児の血清や成長因子の作用について解説。成長因子は1㎎数十万円と高額だとし、いかに安く作るかが参画企業の目標になっていると話した。
また、現在試みられているさまざまな方法について解説する中で、オオムギ種子やタバコ葉に蓄積させれば格段に安くなると紹介した。
さらに最近、小麦胚芽抽出液は細胞増殖を阻害しないことが分かったとし、このことで試薬は不要となり、試薬に含まれる緩衝液やアミノ酸ミックスを食品グレード・食品添加物由来のものに置換することが可能になったなどと、最新の技術も紹介した。
これら培養肉は、無菌下で培養されるため、現在禁止されている生食用レバーの販売が可能になるのではないかとの期待もあるという。