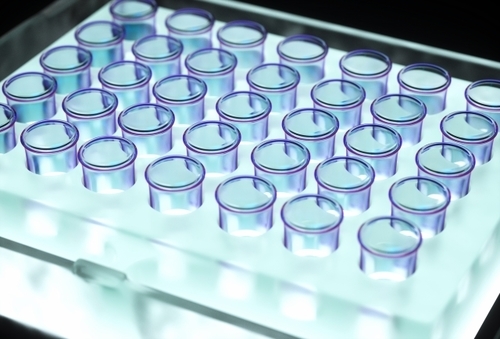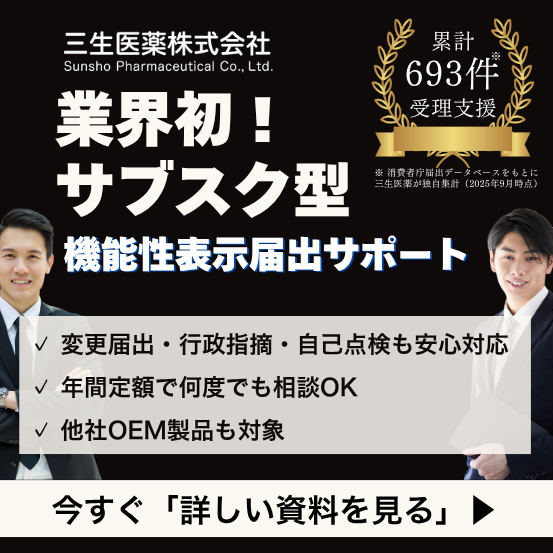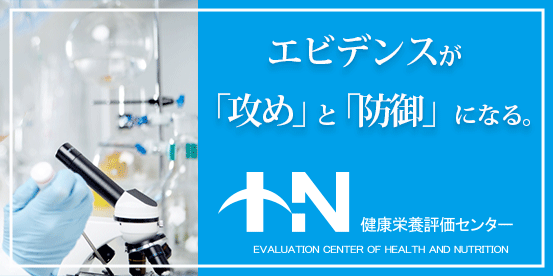エビデンス入門(8)臨床試験の例数設計(続)
関西福祉科学大学 健康福祉学部 福祉栄養学科
講師 竹田 竜嗣 氏
前回の続きで、例数設計について述べる。前回は、例数設計の意味や必要性について説明した。今回は、実際に例数設計をするための方法について述べる。
例数を設計するためには、いくつかのアプローチがある。まず、試験の目的が有効性試験の場合、本来は小規模の予備試験や用量設定試験などを行って、試験目的が達成できそうかどうかを確認する。この小規模の試験を行うと、例えばプラセボ対照の試験であれば、試験品の効果量や各群のばらつきといった情報が得られる。この得られた情報を基に、本試験の例数を設計する。これが、本来の臨床試験実施の流れである。
しかし、そのようなことが予算的に難しい場合や、動物試験など何らかの情報からヒト試験を行って効果が確認できるという確信がある場合などでは、予備試験の実施を割愛するケースもある。その場合は、類似する過去の試験の情報を参考にするなど、直接的ではないが、間接的に情報を利用できる試験を文献などから探す。
次に、実際に例数設計を行うために必要なパラメーターについて述べる。まずは、効果量である。効果量は、プラセボ対照試験であれば、プラセボと試験品との差になる。効果量は小さいと、臨床的な効果に疑問が付く。そのため、効果量が臨床的に意味のあるものかどうかの検討は必要である。
また、その効果量のばらつき、通常は標準偏差も必要である。標準偏差は大きければ、有意な差は生じにくく、小さい方が有意な差が付きやすい。そのため、標準偏差は慎重に設定する。
過去の試験があれば、その数字を参考にする。または、参考になる試験があればその数字を採用するが、気を付けないといけない点は、参考にする集団の特性である。自身が計画している試験と同じ特性の集団化を確認しながら設定しないといけない。アウトカムの特性によっては、年齢層や男女比などによって分布が変化するものもあるため、十分な吟味が必要である。
その次に必要なパラメーターは、有意水準である。有意水準は5%が一般的である。そして、前回に述べた第2種の過誤と関連が深い検出力である。検出力は上げれば上げるほど、設定したパラメーターを到達すれば有意な差が付きやすくなる。一方で、例数が多く産出される。有効性確認試験であれば、確実性をある程度担保するために検出力は80%とすることが多いが、探索的な要素もまだ残っているようであれば、70%と設定する場合もある。
以上が例数設定に必要なパラメーターである。これらのパラメーターを基に統計ソフトなどで例数を計算できる。例数を計算できれば、最後に試験の脱落数を上乗せする。試験の脱落とは、試験に参加していたが、同意撤回などで被験者が参加を辞めることである。
通常はそこまで頻繁に起きることはないが、だいたい5~10%程度は見込んでおくと安心できる。つまり、統計的計算で必要な例数が1群15人、2群で30人と算出された場合、試験終了時に30人のデータを確保するために、脱落者を見込んで32人を試験に必要な例数として試験を開始する。こうすることで、試験終了時に脱落が多少出ても、統計的に必要な例数が担保されることになる。
(つづく)