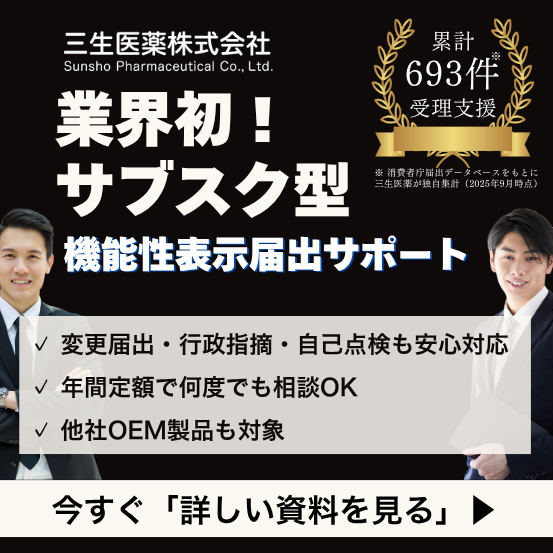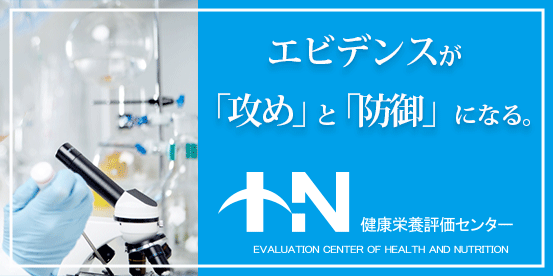エビデンス入門(7)臨床試験の例数設計
関西福祉科学大学 健康福祉学部 福祉栄養学科
講師 竹田 竜嗣 氏
今回は、臨床試験を実施する際によく行われる例数設計とは何かを解説する。
例数設計とは、簡単に言うと「エビデンスがあるとされる差=臨床的有意差」を得るために必要な例数が、どの程度必要かということを計算により求める方法である。臨床試験を実施する前に結果を予測するというのは少し不思議な感覚であるが、臨床試験を実施する以上、期待した結果が得られるという確証がなければ、安全性などの倫理的な観点から問題があるとされている。
そのため、通常は小規模な試験(予備試験)を実施して、期待した効果があるかどうかを確認または予測する。小規模な試験で得られた効果から、設定したエビデンスが得られる(つまり意義のある効果=臨床的な有意差が得られる)と判断されれば、その結果から有効性確認試験を実施する上で必要な例数を決めるというのが、臨床試験の本来の流れである。
特定保健用食品(トクホ)の申請では、用量設定試験、有効性確認試験、過剰摂取試験などの臨床試験が通常必要であるが、有効性確認試験の例数を決める際に、用量設定試験の結果を参考に例数を設定する場合が多い。
このように臨床試験を実施する場合、機能性表示食品の届出で必須なのは有効性確認試験だけであるが、臨床試験の計画書を作成するに当たり、「例数の設定根拠」を求められることが多い。これは、試験を行って解析した(有意差検定した)結果、その解析結果が間違っている可能性が一定の確率で存在し、それらの確率が例数に影響を受けるためである。
解析結果が間違っている事例は、大きく分けて2通りある。1つは、真の結果は「効果なし」であるが、誤って「効果あり」という検定結果となった場合である。これを第1種の過誤という。この確率は有意水準であるα(通常は5%)と同じである。もう1つは、真の結果は「有意差あり」であるが、「有意差なし」と判断されてしまう場合である。これを第2種の過誤という。
第1種の過誤は有意水準と同じであるため、小さくする必要があれば、有意水準を小さくすればよいため、コントロールできる。一方、第2種の過誤は試験結果や条件、試験を実施した人数によって変動する。例数を多くすれば、第2種の過誤の確率が小さくなることは確かである。しかし、やみくもに多くの人数で試験を実施すると、未知の副作用などが発現した場合に多くの被害が出るといった問題があり、倫理的な配慮から、必要最低限で行うべきである。
そうした事情から、予め計算により、第2種の過誤をできるだけ小さくするために必要十分な例数を求める必要がある。具体的に、どのように設定するのかについては次回に詳述する。
(つづく)