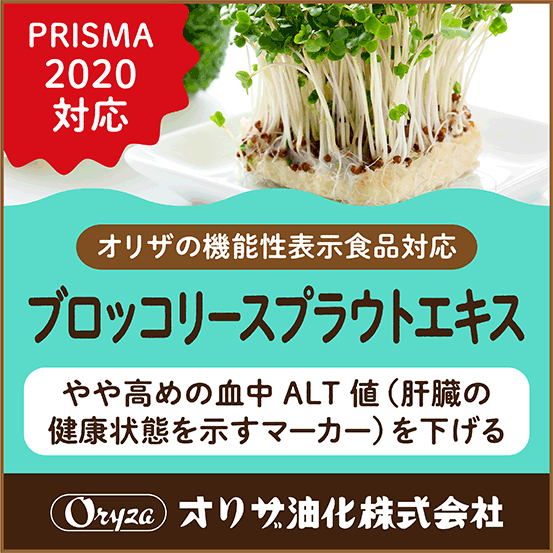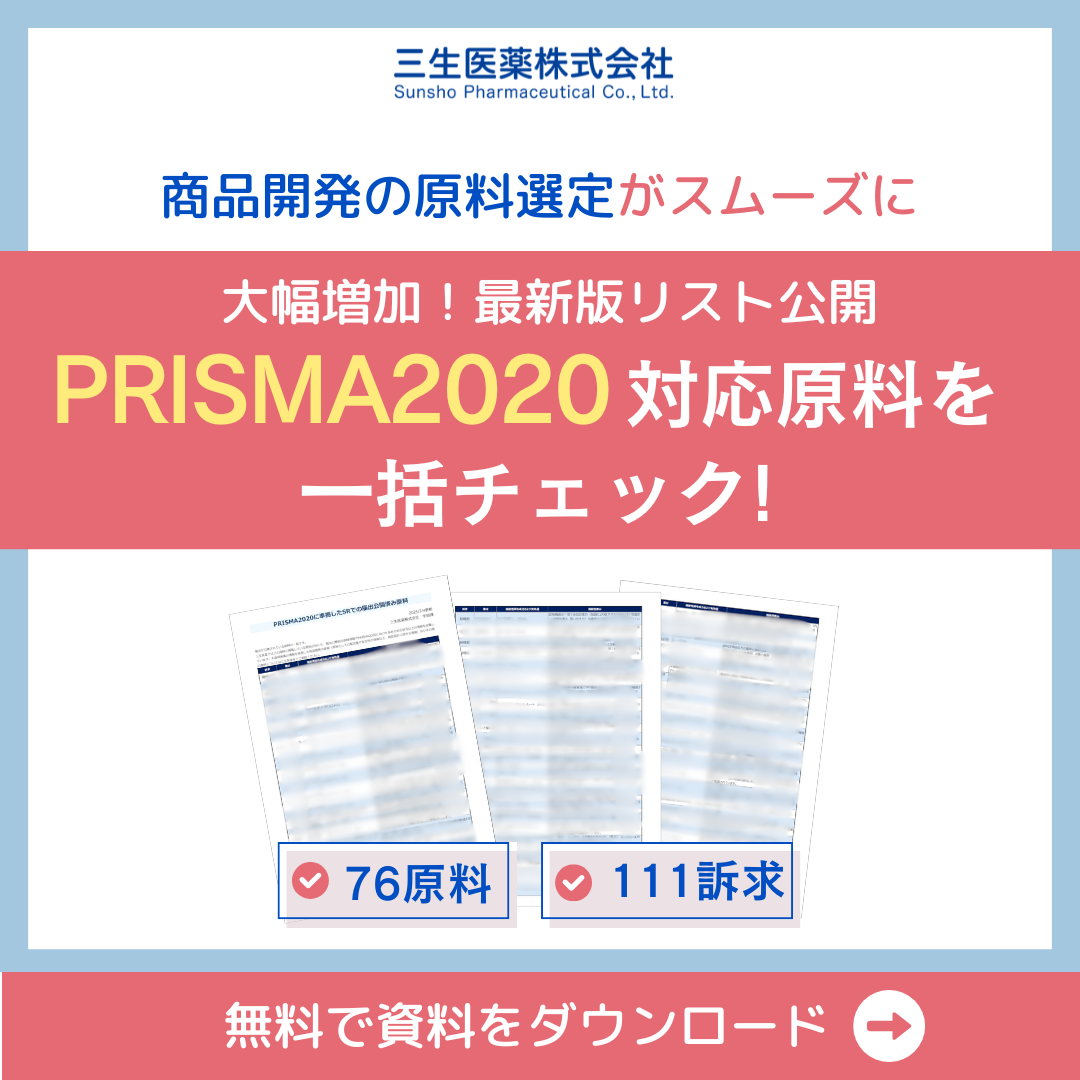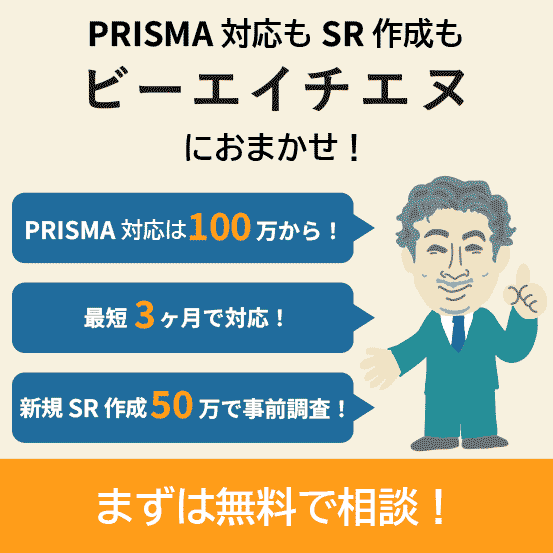エチケットサプリのリーディング企業 【九州のヘルスケア産業2025】グリーンハウス、横尾一浩社長に展望聞く
1996年創業の通販企業、グリーンハウス㈱(福岡市中央区)。主力商品は、2004年発売の健康食品『楽臭生活』。㈱リコム(東京都豊島区)が供給するシャンピニオンエキスを配合する同商品は、国内健康食品市場の「臭いケア」カテゴリーを代表する商品の1つだ。社長就任から10年の節目を迎えた横尾一浩社長(=写真)は、通販健康食品市場の現在をどう見ているのか。それを踏まえた事業戦略を聞いた。
消費者購買行動に変化、求められる強みの拡張
──グリーンハウスの主力商品は健康食品です。小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題の影響は避けられなかったと思います。直近、2024年9月期の業績を伺います。
横尾 健康食品メインの通販企業はほとんどどこも同じではないかと思うのですが、率直に言って大変でした。既存が大きくダメージを受けた。新規の獲得も難しくなった。今も、状況はそう変わっていないと思います(取材日=2025年6月18日)。広告に対するレスポンスが悪くなっているし、実質的な中身が悪くなっている。
──中身が悪く、というのは?
横尾 今、通常購入のニーズがものすごく高まっています。安くなくて構わない、通常価格で良いのでまずは試したい、というニーズ。初回定期購入を回避するユーザーが去年から明確に顕在化していて、通販健康食品でこれまで主流だったビジネスモデルが難しくなりつつあります。中身が悪くなっているというのはそういうことです。
通販健康食品のユーザーは今、初回は無料だったり、安く購入できたりといったメリットよりも、それによって縛られる定期購入のデメリットを強く意識しています。そうした傾向が、今のユーザー動向からはっきりと見えます。定期に縛られたくない、まずは試し、その商品の良し悪しを評価し、その上で購入を続けるかどうかは自分で決定したい、という思考が働いているのでしょう。とりあえずお試しで買ってみて、気に入らなければ解約するというのではなく、購入する健康食品をものすごく選別するようになった。いわば、石橋を叩くかのような購買行動に変わってきたと言えると思います。
──消費者の思考や購買行動がそのように変わったのはなぜでしょうか。
横尾 やはり、昨年の紅麹(サプリ健康被害問題)が影響していると思います。ただ、それはきっかけに過ぎなくて、より大きな要因としては、日本社会全体で消費が弱まっていることがありそうです。お米の価格が高騰したりなど生活の基盤になるところのコストが高まっている。そうすると、生活を守るために、嗜好品だと思われている健康食品に対する財布の紐はどうしても固くなる。当社もそうなのですが、長年購入してくれていたユーザーが、一定の割合で離れていってしまう傾向が去年から続いています。その背景には、紅麹の影響は薄まった一方で、消費者の生活防衛の意識が強まった結果、健康に対する意識は依然高いにせよ、健康食品の購入にかなり慎重になっているがことある。そのように考えています。
──そのような消費者の意識の変化に合わせていく必要がありそうです。
横尾 実際、変わり始めています。新規獲得のためにコストを投じるよりも、休眠顧客を掘り起こすことも含め、自社の基盤となるところにコストを割いたほうがリターンは大きいし、先も見通しやすい。そのように考え、その方向に動いている会社が増えていると思います。以前のように、新規を追い求めなくなっている。そうすると、フォーカスされる商材は、おのずと新規ではなく、自社の強みを出せる既存の商材になります。機能性表示食品がまさにそうですが、新規性のあるものがあまり出てこない。そのため、横並びの傾向が強まっている。仮に、新しい商材を始めたとしても、今の状況では投資の回収が見通しづらい。そのため、総合通販的に商材を広げるのではなく、自分たちの強みである商材をどう拡張していくのか、あるいは固めていくのか、というところの取り組みが求められていると思います。
我々のコアであり本丸、リソースはそこに割く
──グリーンハウスは以前から、オウンドメディア『からだタイムズ』を運営しています。ここにきてコンテンツの強化、充実化を図っているように見えますが、狙いは?
横尾 昨今の消費者の購買行動や検索アルゴリズムの変化に合わせながらコンテンツを増やしたり、古くなったコンテンツを最新の内容にバージョンアップさせたりといったことに、昨年から本腰を入れ始めました。リソースもかなり割いています。
私たちグリーンハウスのコアであり、守らなければならない本丸とは、商品で言えば『楽臭生活』。つまり「臭い」に対するニーズです。その本丸を守り、拡張していくための1つの手段として、臭いの関係に加え、臭いの基盤とも言える腸内環境に関係する専門的なコンテンツの発信を強化していこうということ。臭いというのは目に見えるものではありませんから、専門家の知見やデータをしっかり伝えていくことで、私たちの立ち位置を明確にしたいとしています。
私たちはこれまで、臭いというカテゴリーに時間を費やしてきました。その分、臭いに関するバックグラウンドを持っています。これまでに色んな商材を発売してきましたが、楽臭生活を長年販売している私たちにユーザーが強く求めているものは、やはり、臭いのところなのです。ですからコンテンツに限らず、私たちのコアである臭いのところにリソースを投下して、私たちの強みを最適化、最大化していくことは、ユーザーが求める方向性に合致すると思いますし、それは私たちが(通販健康食品市場で)勝ち残っていくためにも必要なことだと思っています。商材を増やすことに限られたリソースを割くよりも、臭いのカテゴリーのトップランナーであり続けることのほうが重要。今はそのように考えています。
──楽臭生活を機能性表示食品にするために、2年前、臭いに対する効果を検証する最終製品を使った臨床試験を行いました。自社の強みに対してリソースを投下したということだと思います。ただ、今のところ届出は実現していません。
横尾 臭いに対して訴求することの全てがダメだということはないのですが、厳しいですね。しかし、諦めたわけではありません。
一方で、機能性表示食品でなければならないという固定観念を持つ必要もないと考えています。そうした考えは、自分たちの事業に制約を作ってしまうことになりますから。そうではなく、私たちの強みを最大化していくための1つの手段として機能性表示の可能性を探っていけば良い。今はそう考えています。
いずれにせよ、制度が改正されたばかりですし、それを消費者がどう受け入れていくのかを見極める必要もあります。機能性表示食品は、時間をかけながら取り組んでいくのが良いと思っています。
コンテンツ拡充と基盤カテゴリーの強化
──グリーンハウスの強みを拡張していくために、今後どのよう取り組みを進めていきますか?
横尾 引き続きコンテンツを拡充させ、その露出量を増やしていく。そのようにして、顕在化層に対するリーチを最大化していきます。また、ひと口に臭いと言っても、臭いはさまざまですから、我々がこれまでリーチできていなかった部分にも手を広げていくことも必要だと考えています。これまでは健康食品だけでしたが、主力の楽臭生活を軸に、臭いというカテゴリーを全体的に強くしていく方向性もあろうかと思います。それに、腸内環境に関係する商品開発も進める必要もありそうです。今期中に目途を立て、来期から実行していきたいと考えています。
──ありがとうございました。
【聞き手・文:石川太郎】
<COMPANY INFORMATION>
所在地:福岡県福岡市中央区大名2-7-27 シティ18天神ビル2F
TEL:092-738-2828
URL: https://www.greenhouse.ne.jp
事業内容:健康食品・化粧品の通信販売、九州産食品の産直事業