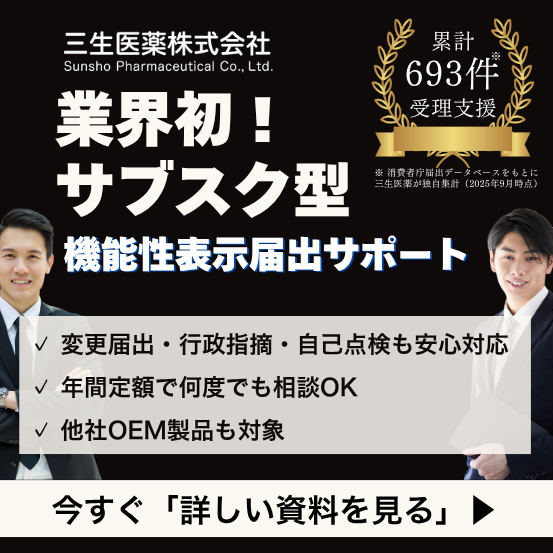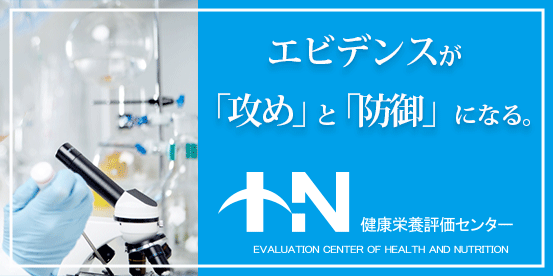【回顧】コロナに振り回された2020年を振り返る
東京大学名誉教授 (公財)食の安全・安心財団理事長 唐木 英明
<対立を生んだ医療とリスク管理>
2020年はコロナに始まりコロナに終わった。リスク管理の最大の課題は個人と社会の対立の調整である。コロナについて医療は「人命は地球より重い」という理念を持って対応し、だからこそ患者や家族から信頼される。そして人命救助のために感染者をゼロにしようと試み、都市封鎖と外出禁止を主張する。しかし、リスク管理者はそのような医療対策が社会と経済に壊滅的な影響を与えることを懸念する。こうして両者の対立が起こる。この問題を3つの要因から検討する。
コロナの実態は武漢での事例から早期に分かっていた。感染者の8割が軽症か無症状で、基礎疾患がある高齢者は致死率が高い。この1年の日本の死者は約3千人、感染者は約20万人で、これらの数は欧米と比べると数十分の1だが、それは対策の結果ではなく、免疫などの生理的要因のためと考えられている。
<偏見・差別を生んだ国の対応>
インフルエンザと比較すると、インフルエンザの年間感染者1,000万人、死者1万人よりずっと少ない。年初にはコロナのワクチンも治療薬もなかったが、年末には海外でワクチン接種が始まり、日本でも今年2月に始まる。治療法も確立して致死率は大きく低下した。要するに、コロナはインフルエンザとそれほど違わない感染症である。
対策について、東京都医師会が2月に発表した指針では、コロナの感染力と重症度はインフルエンザと同程度であり、感染しても多くは症状が出ないか、少し長めの呼吸器症状で完治し、肺炎になった場合の治療法は他の肺炎治療と大きくは変わらず、予防方法も標準的な感染症予防策で十分としている。ところが、国は実態とかけ離れた厳しい対策を実施した。ここで大きな役割を果たしたのは国が設置した専門家会議で、そのメンバーと関係者は連日テレビで「3密防止」、「接触の8割減少」などによる感染防止を呼びかけ、このままでは40万人の死者が出るなどと、仮想の数字で恐怖感を煽り、緊急事態宣言の発出を求めた。国民は外出自粛と営業自粛という過剰な対策に協力し、恐怖感から偏見・差別・自粛ポリスなどの多くの弊害が生まれ、社会と経済は重大な被害を受けた。これを見て政府は、専門家会議を廃止して感染症対策分科会を設置したが、実態は変わらない。
<実態を報道しないメディア>
分科会と医師会が感染対策を主張する根拠が医療崩壊の危機である。しかし、人口当たりのベッド数が世界最多の日本で医療崩壊が起こるはずがない。政府はコロナを感染症法上の指定感染症2類相当にして、軽症、無症状も含めて感染者全員を少数の指定医療機関に入院させることにしたが、それでも全国の指定医療機関のベッドの半分以上が空いている。そして、感染者が急増した地域の特定の指定医療機関だけが医療崩壊状態になっている。局地的な危機は全体の協力で防ぐことができるのだが、政府も分科会も医師会も、問題解決の努力を放棄し、医療崩壊を口実にして国民に自粛に求め続けている。2類扱いの被害は保健所にも及び、感染経路の調査や感染者の入院先の選定などに忙殺され、通常業務が困難になっている。しかしメディアはこのような実態を報道しないため、国民は医療崩壊が目前に迫っていると誤解している。
コロナを5類扱いに変更すれば、医療・社会・経済の多くの被害をなくすことができ、2類扱いに要した莫大な経費は高リスク者の感染防止と救命に集中することで、ずっと多くの人命救助が期待される。ところが厚労省は、来年1月で期限を迎える2類扱いを1年延長することにした。そうであればその運用を大幅に柔軟化して欠点を排除することで、天災に輪をかける人災を軽減すべきである。
新しい年にはワクチン接種が始まり、コロナ恐怖症が収まって明るいニュースが流れることを願っている。